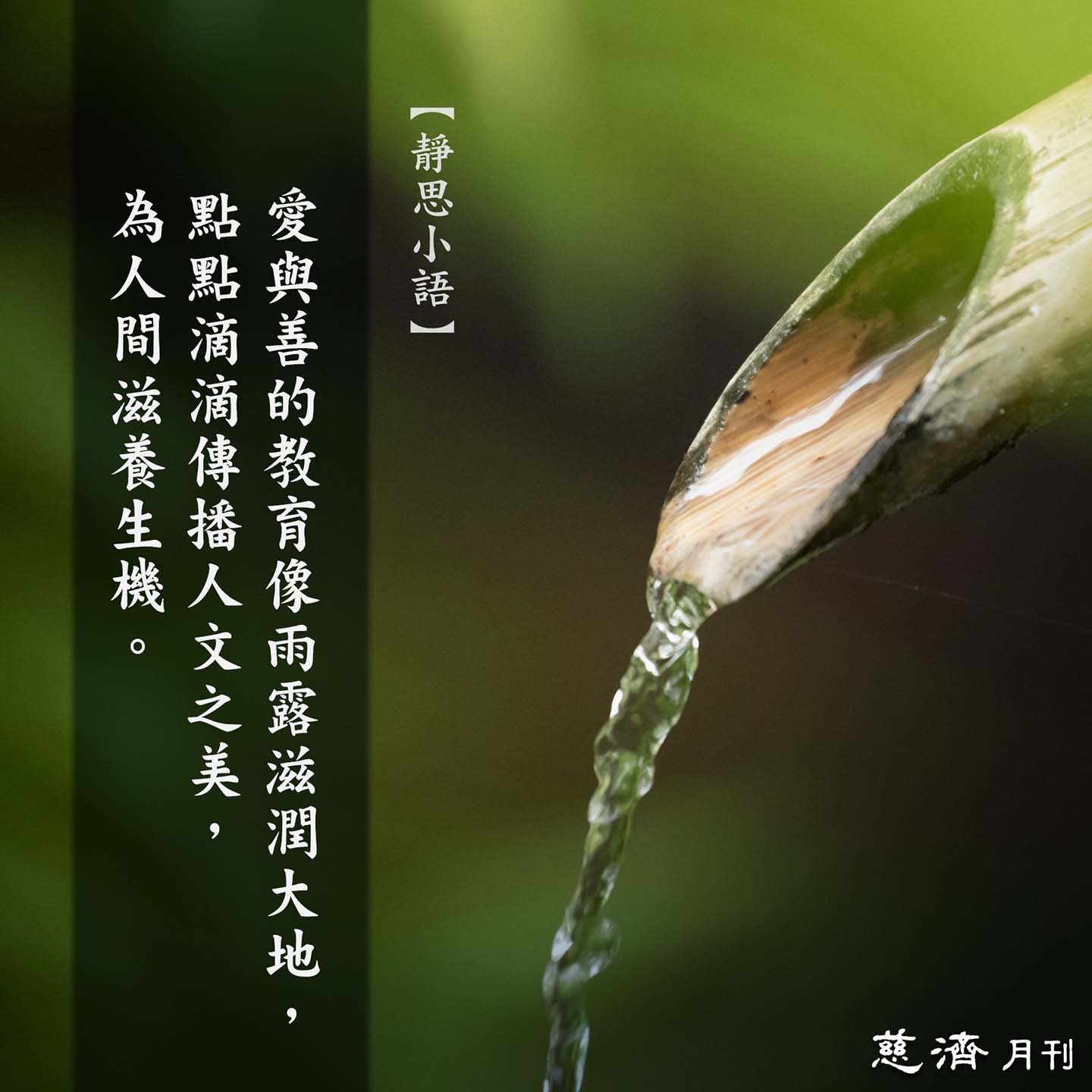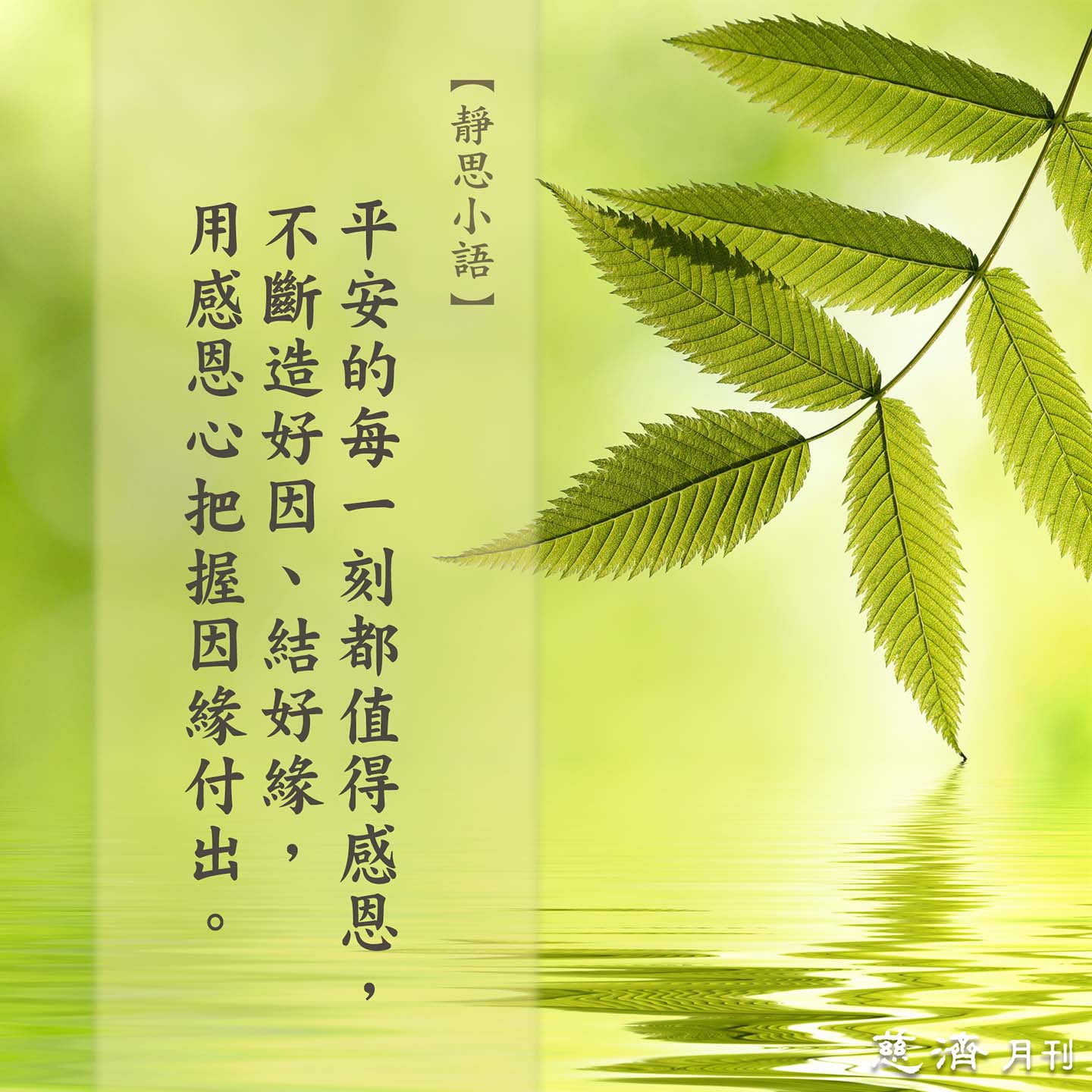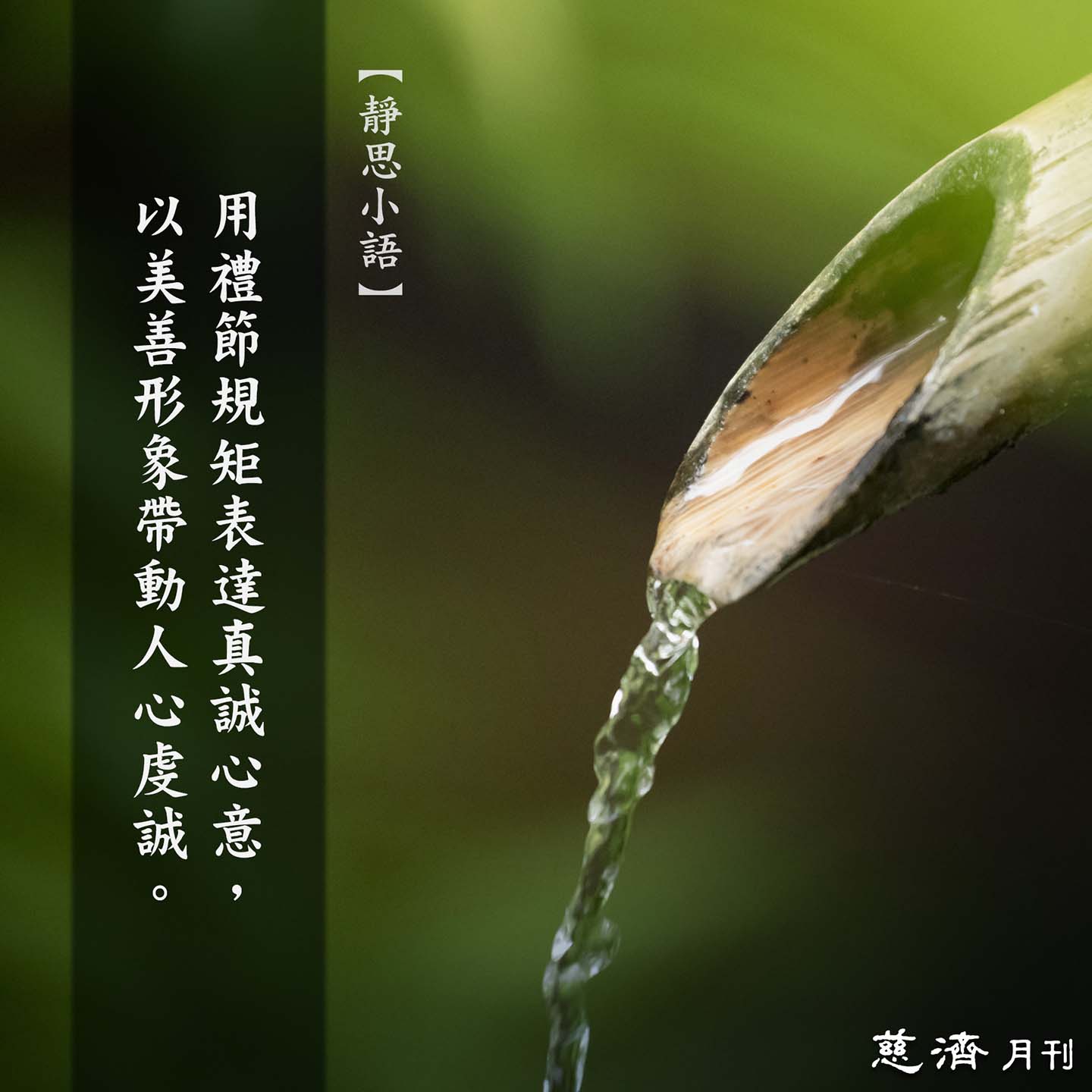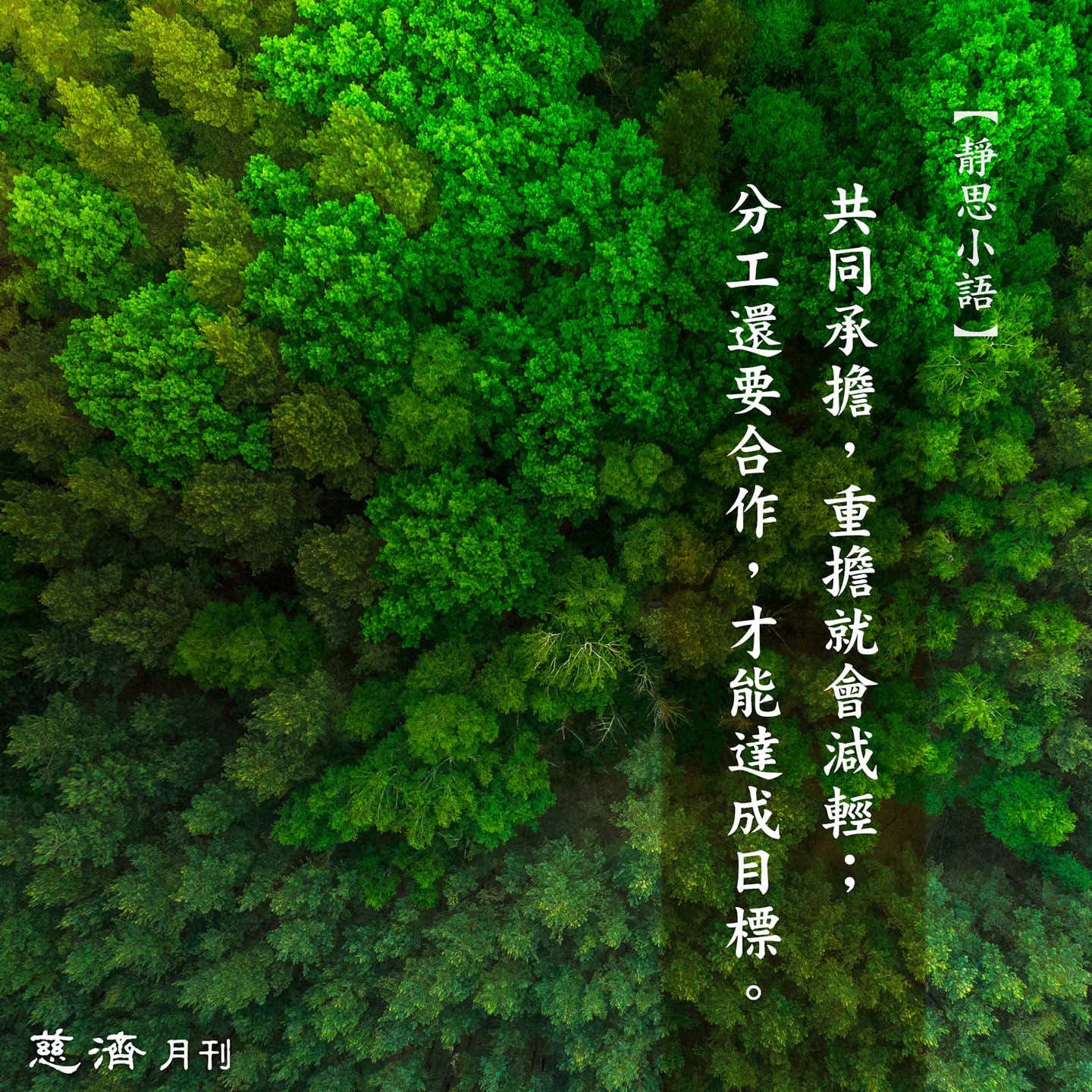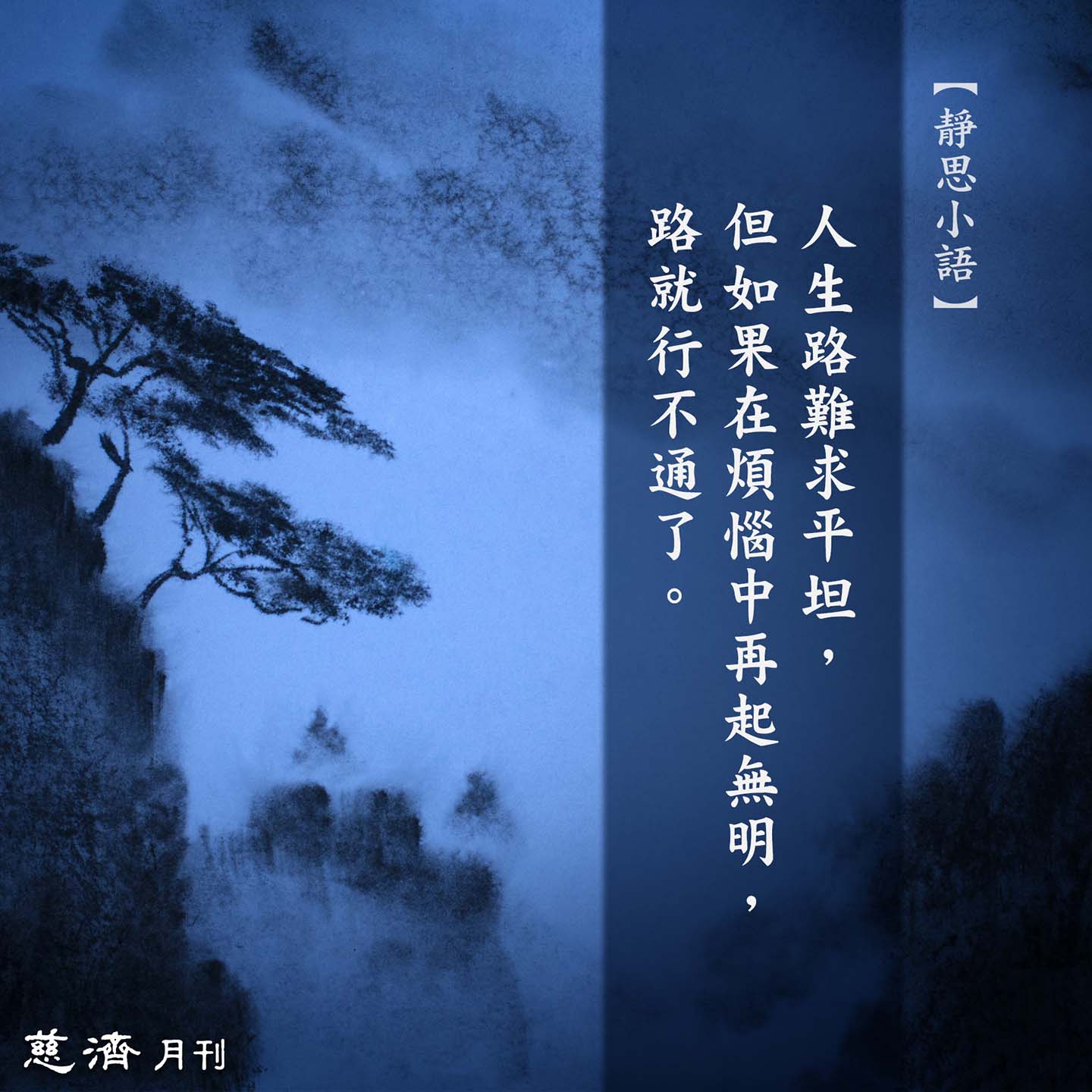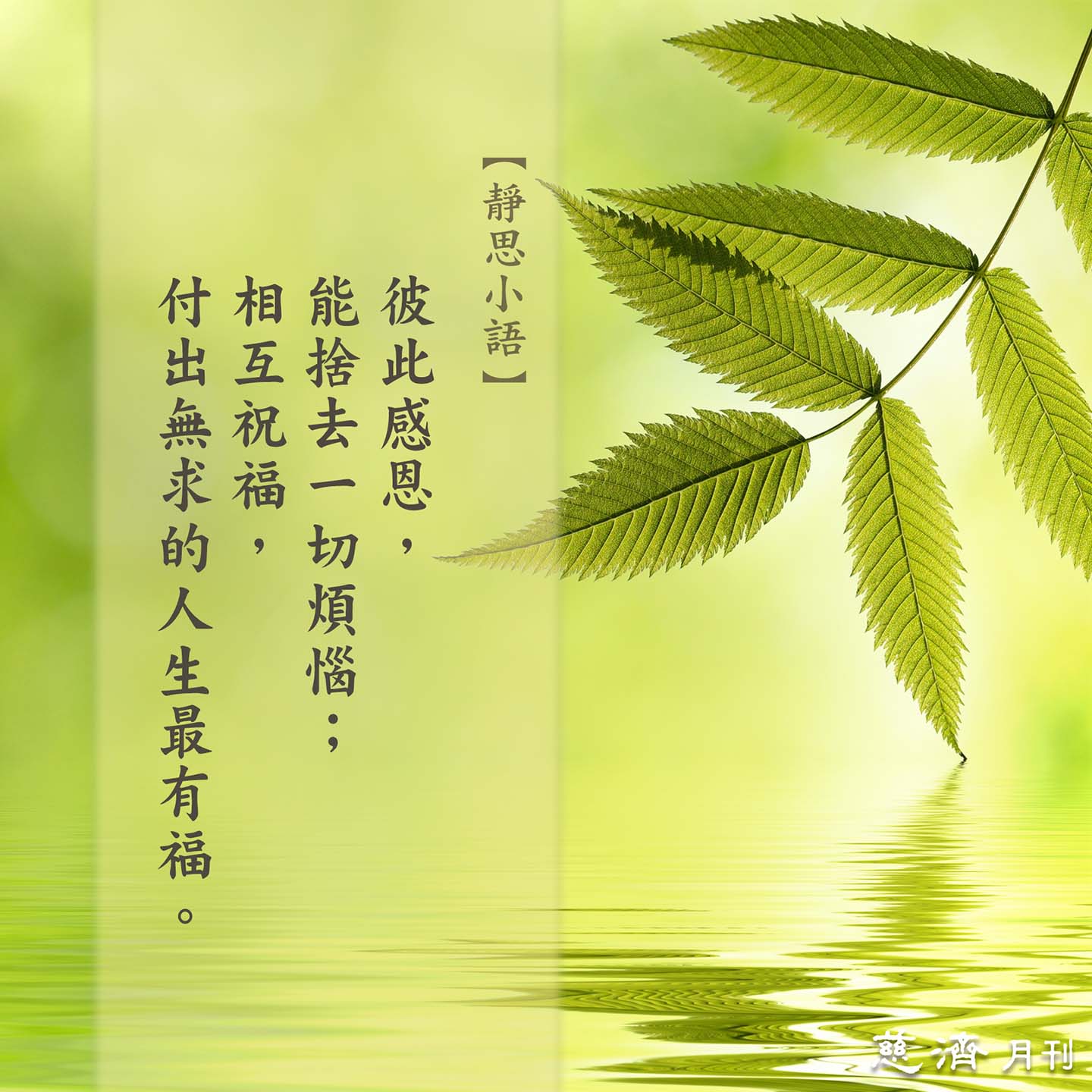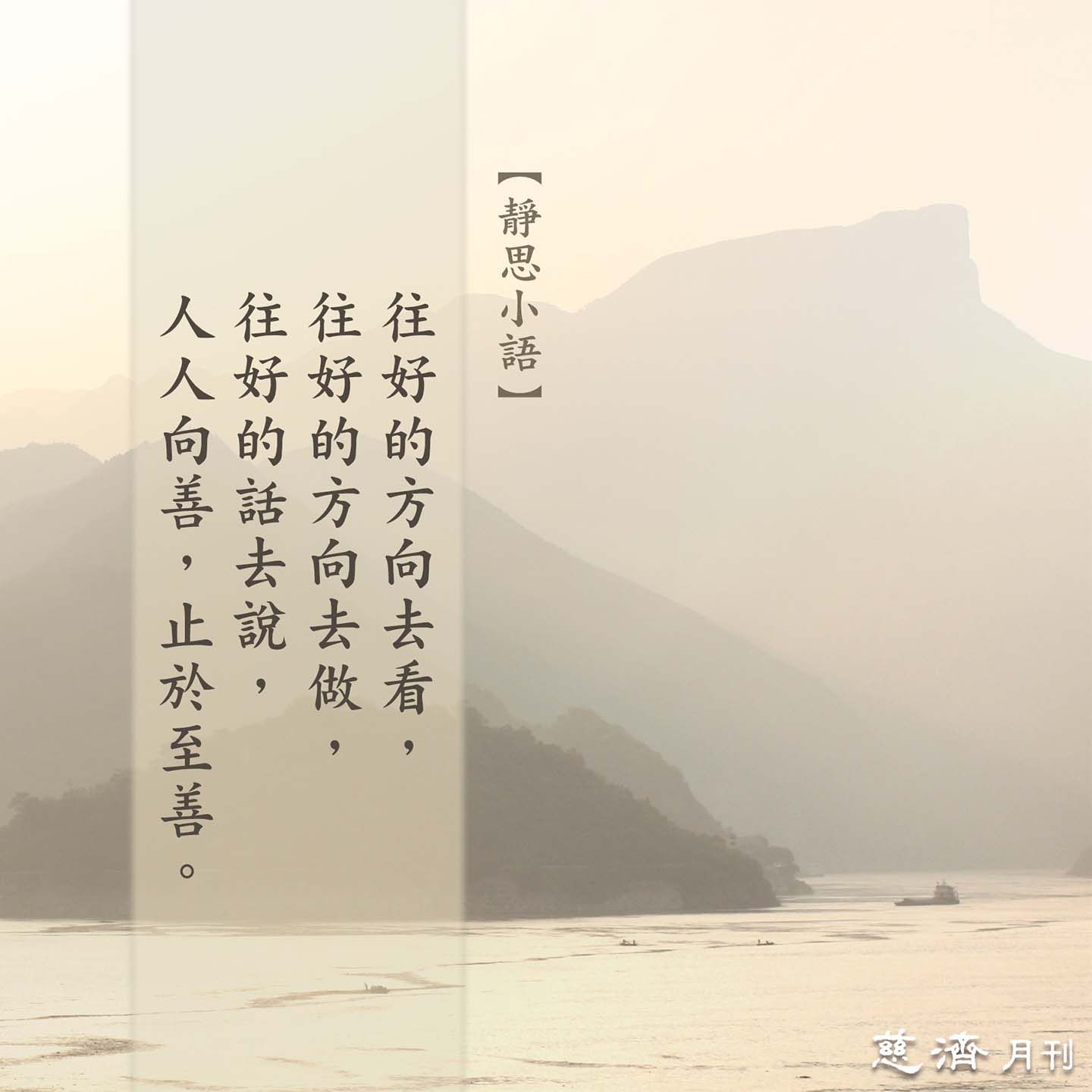3.7~8《農二月‧初五至初六》
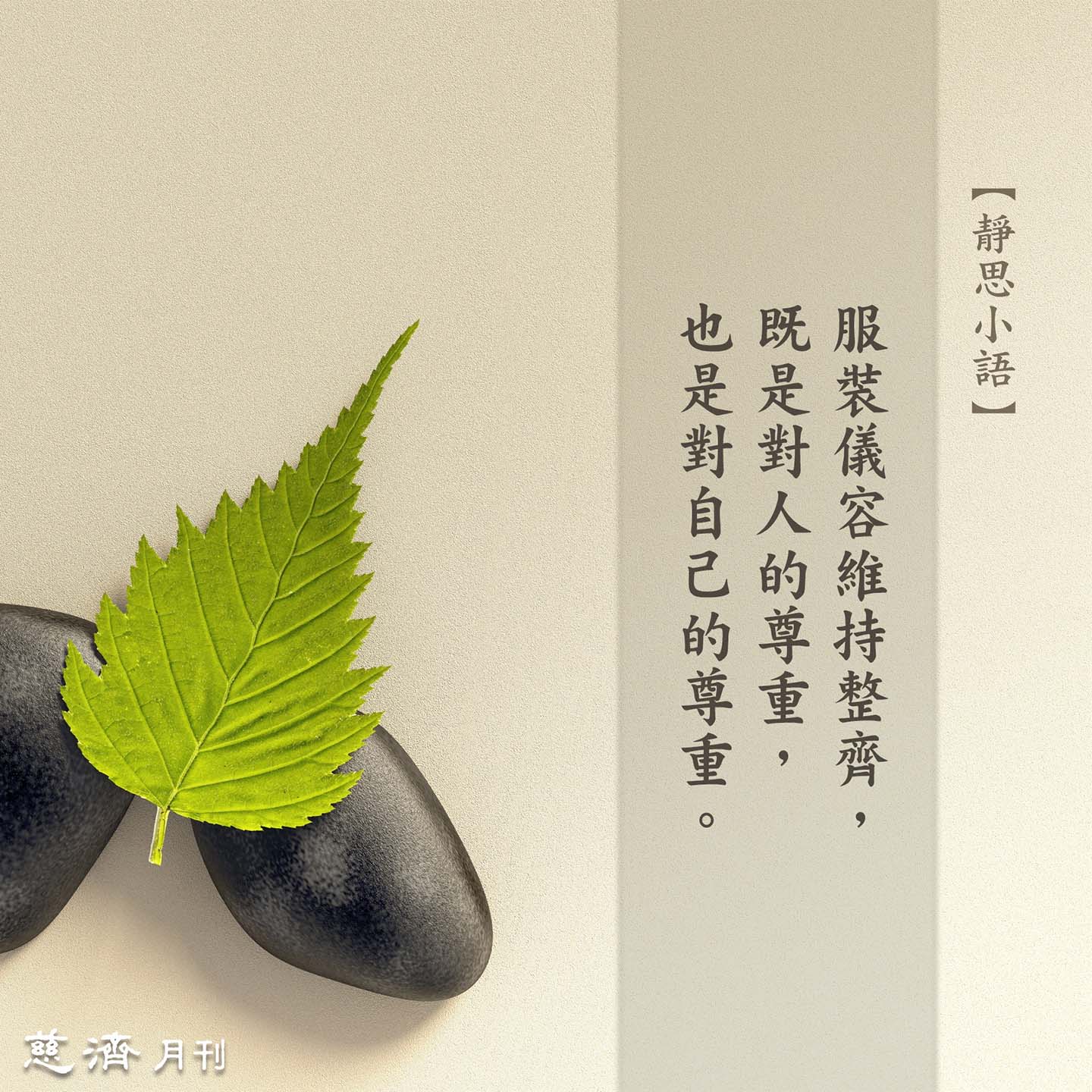
【靜思小語】服裝儀容維持整齊,既是對人的尊重,也是對自己的尊重。
當心念專注於呼吸
自從新冠肺炎疫情籠罩全球,人人談「疫」色變,三月七日志工早會,上人教眾持續戒慎虔誠,雖然為了防疫,人與人之間要拉開距離,但是不能失去對人的信心;假如對人沒有信心,彼此提防,人間就會變得冷漠,無形的心靈距離也會拉遠。此時更需要合和互協,提起愛心相互關懷,如規如矩,走在正確的人生軌道上。
上人強調愛是智慧的表態,所以有智慧的人不冷漠。在日常生活中待人處事,很清淨,不脫軌,疼惜、守護著眾生,就是智慧的愛。
面對驚世災難,要起警世覺悟;有覺悟就要改變生活習慣,從心靈到生活行為都要齋戒、虔誠。上人呼籲人人要盡量茹素,轉葷茹素只在一念心而已!這是考驗自己有沒有真誠的愛心,有沒有智慧的願力;有智慧的願力、有真誠的愛心,就能發揮清淨無染的智慧之愛,成就美好人生。
上人說,凡夫總是會被外境迷惑,而佛陀用覺悟的智慧觀天地萬物,能夠察覺到世間萬物都在持續不斷地變化之中。凡夫如何啟發智慧?就要把散亂的心收攝回來,先內觀自己,就如每天起床後先靜坐數息,將心念專注於呼吸,這時的心很靜、很定,不必看時鐘就知道幾個呼吸以後時間過了多久;不過離開這個境界,和大家互動、說話,注意力分散了,要知道時間過了多久,就要看時鐘。
「眼睛看時鐘,是眼識起作用,還無法達到與天地相合的智慧,所以修行功夫還是不夠。但只要我們將欲念一分一分地消減,將煩惱一分一分地淡化,自然心靜意定,就可以與天地宇宙合而為一,這就是修行。」上人說,人人都有與佛同等的智慧,但是從凡夫地要達到徹底清淨、覺悟圓滿的佛境界,還有很長的一段距離,需要從現在開始把心顧好、注意足下,好好地走人間路,才能接上菩薩道,一步步踏實而穩定地接近成佛的目標。
自我盤點生命價值
三月八日,大林慈濟醫院賴寧生院長帶領團隊返回精舍,報告醫療個案並與上人座談;上人感恩大林慈院團隊合和互協,就地照顧、守護鄉親的身體健康。
「我只有很單純的一念心─守護生命;建醫院就是為了守護生命,因為人間最苦莫過於病痛,尤其衰老又生病,是苦上加苦。大林地區老年人口多,我們要用感恩心面對這群年長的鄉親,沒有老一輩的辛苦,就沒有現在繁榮的社會。」上人教大家抱著感恩心面對所有人,對於自己則要自我盤點,肯定自己的生命價值。生命的價值無法以金錢評估,真正的價值在於發揮生命為人間拔苦予樂,「苦既拔已,復為說法」,讓人人身心安穩,輕安自在而無後顧之憂,這就是最好的醫療。
上人表示,在自己的心目中,醫師就如活佛,所以稱呼醫師為「大醫王」;救拔病苦的醫師廣受尊崇,醫師們也要自我尊重、自我信任,恆持最初選擇讀醫學系、從事醫療工作的心願與志向。「就如我選擇的志願方向是出家修行,而我修行是為了利益眾生,從最初發了那一念心到現在,我可以自信地說我做到了,四大志業步步踏實,就是因為我從來沒有脫離過那個念頭。」
上人說,培養人才也要給予正確方向,讓他們知道自己受栽培,不是為了成名、得利,只求名利的是庸才;所要栽培的好人才,要有承擔、能負責任,發心立願,對準方向往前精進。購入先進的科學儀器,不只能減輕醫師長時間投入手術的辛苦、減少進行手術所需要的時間,最重要的是對病患真正有幫助,能減輕他們的痛、減少住院的時間,快速恢復正常生活。
「我常教大家要『感恩、尊重、愛』,這是與人互動、共事,時時都要有的態度。你們能夠合和互協,就表示你們彼此尊重,包括服裝儀容都能維持整齊,既是對人的尊重,也代表自己的人格,即使獨處時也是如此,就是對自己的尊重。」
「要有自信,也要自愛,還要提升自己的生命價值。為人間做事,只靠自己一個人做不到,要彼此合力,相互幫助、相互成就。就如你們為病患開刀,不能只靠主刀醫師,還要有麻醉醫師、護理師等等,而且只要醫師一個手勢,旁邊的人就知道該遞上什麼工具、如何補位等等,這是長久培養的默契,也是合和互協的精神。」
上人強調成功的手術、優秀的醫療,所倚靠的從來不是儀器而是團隊,優秀的團隊懂得將儀器的功能發揮得淋漓盡致,讓病患得到最佳的醫療效果。所以說最重要的還是人心,人的心念正,就能利益人間;假如人心方向偏差、脫軌,就會造成很嚴重的後果,所以天天都叮嚀大家恆持正向。
要有正念就要有正信,不論信仰什麼宗教,都不能脫離正道。慈濟醫院是基於佛教精神創立的醫院,「為佛教」更不能脫離佛教的宗旨;「為眾生」,眾生苦難偏多,尤其大家在醫療工作中接觸許多病患,有的家貧再加上生病,妻離子散、家庭破碎,他們唯一的希望與依賴就是醫師,殷切期盼經由醫療能恢復身體健康,這就是醫療的價值。

3.7~8《農二月‧初五至初六》
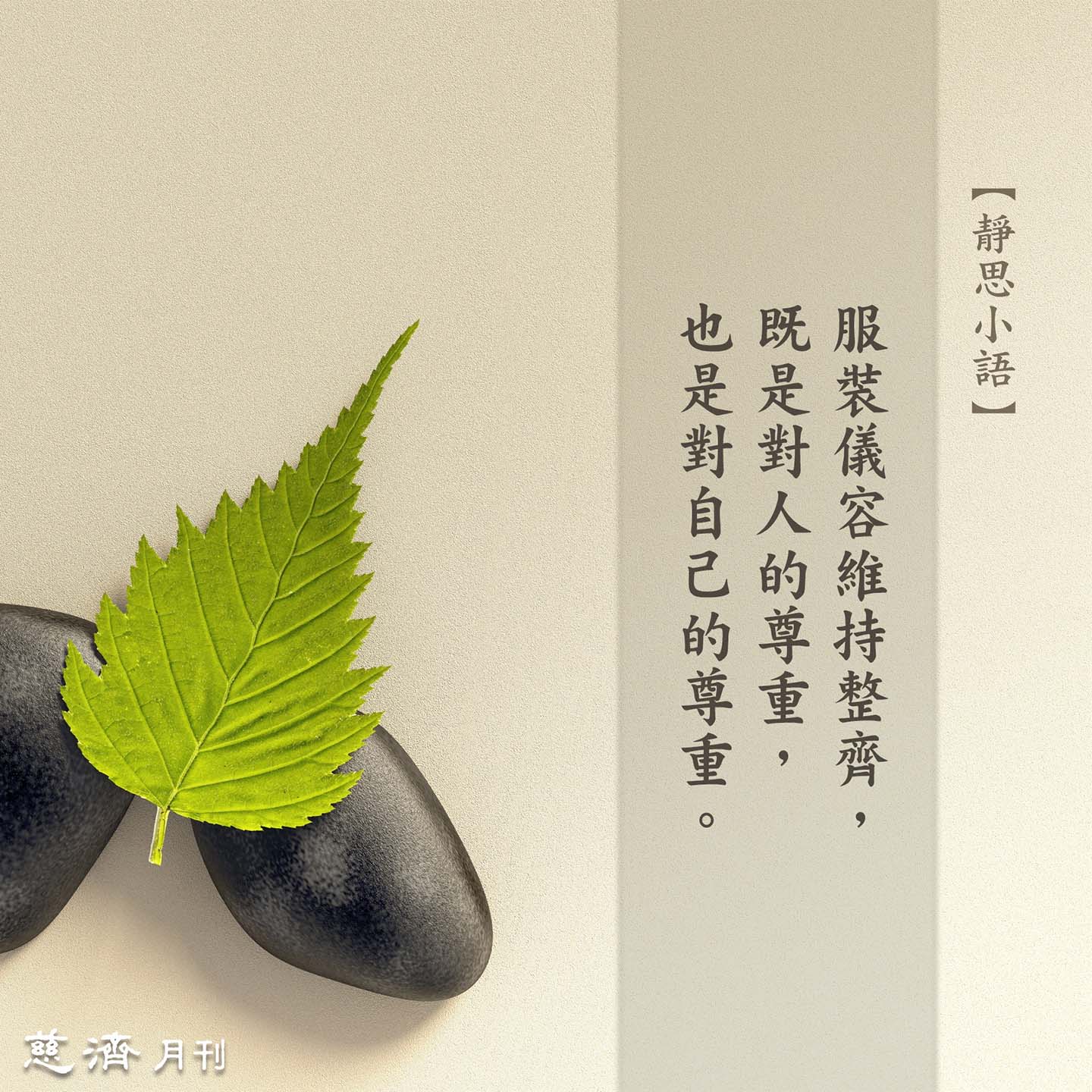
【靜思小語】服裝儀容維持整齊,既是對人的尊重,也是對自己的尊重。
當心念專注於呼吸
自從新冠肺炎疫情籠罩全球,人人談「疫」色變,三月七日志工早會,上人教眾持續戒慎虔誠,雖然為了防疫,人與人之間要拉開距離,但是不能失去對人的信心;假如對人沒有信心,彼此提防,人間就會變得冷漠,無形的心靈距離也會拉遠。此時更需要合和互協,提起愛心相互關懷,如規如矩,走在正確的人生軌道上。
上人強調愛是智慧的表態,所以有智慧的人不冷漠。在日常生活中待人處事,很清淨,不脫軌,疼惜、守護著眾生,就是智慧的愛。
面對驚世災難,要起警世覺悟;有覺悟就要改變生活習慣,從心靈到生活行為都要齋戒、虔誠。上人呼籲人人要盡量茹素,轉葷茹素只在一念心而已!這是考驗自己有沒有真誠的愛心,有沒有智慧的願力;有智慧的願力、有真誠的愛心,就能發揮清淨無染的智慧之愛,成就美好人生。
上人說,凡夫總是會被外境迷惑,而佛陀用覺悟的智慧觀天地萬物,能夠察覺到世間萬物都在持續不斷地變化之中。凡夫如何啟發智慧?就要把散亂的心收攝回來,先內觀自己,就如每天起床後先靜坐數息,將心念專注於呼吸,這時的心很靜、很定,不必看時鐘就知道幾個呼吸以後時間過了多久;不過離開這個境界,和大家互動、說話,注意力分散了,要知道時間過了多久,就要看時鐘。
「眼睛看時鐘,是眼識起作用,還無法達到與天地相合的智慧,所以修行功夫還是不夠。但只要我們將欲念一分一分地消減,將煩惱一分一分地淡化,自然心靜意定,就可以與天地宇宙合而為一,這就是修行。」上人說,人人都有與佛同等的智慧,但是從凡夫地要達到徹底清淨、覺悟圓滿的佛境界,還有很長的一段距離,需要從現在開始把心顧好、注意足下,好好地走人間路,才能接上菩薩道,一步步踏實而穩定地接近成佛的目標。
自我盤點生命價值
三月八日,大林慈濟醫院賴寧生院長帶領團隊返回精舍,報告醫療個案並與上人座談;上人感恩大林慈院團隊合和互協,就地照顧、守護鄉親的身體健康。
「我只有很單純的一念心─守護生命;建醫院就是為了守護生命,因為人間最苦莫過於病痛,尤其衰老又生病,是苦上加苦。大林地區老年人口多,我們要用感恩心面對這群年長的鄉親,沒有老一輩的辛苦,就沒有現在繁榮的社會。」上人教大家抱著感恩心面對所有人,對於自己則要自我盤點,肯定自己的生命價值。生命的價值無法以金錢評估,真正的價值在於發揮生命為人間拔苦予樂,「苦既拔已,復為說法」,讓人人身心安穩,輕安自在而無後顧之憂,這就是最好的醫療。
上人表示,在自己的心目中,醫師就如活佛,所以稱呼醫師為「大醫王」;救拔病苦的醫師廣受尊崇,醫師們也要自我尊重、自我信任,恆持最初選擇讀醫學系、從事醫療工作的心願與志向。「就如我選擇的志願方向是出家修行,而我修行是為了利益眾生,從最初發了那一念心到現在,我可以自信地說我做到了,四大志業步步踏實,就是因為我從來沒有脫離過那個念頭。」
上人說,培養人才也要給予正確方向,讓他們知道自己受栽培,不是為了成名、得利,只求名利的是庸才;所要栽培的好人才,要有承擔、能負責任,發心立願,對準方向往前精進。購入先進的科學儀器,不只能減輕醫師長時間投入手術的辛苦、減少進行手術所需要的時間,最重要的是對病患真正有幫助,能減輕他們的痛、減少住院的時間,快速恢復正常生活。
「我常教大家要『感恩、尊重、愛』,這是與人互動、共事,時時都要有的態度。你們能夠合和互協,就表示你們彼此尊重,包括服裝儀容都能維持整齊,既是對人的尊重,也代表自己的人格,即使獨處時也是如此,就是對自己的尊重。」
「要有自信,也要自愛,還要提升自己的生命價值。為人間做事,只靠自己一個人做不到,要彼此合力,相互幫助、相互成就。就如你們為病患開刀,不能只靠主刀醫師,還要有麻醉醫師、護理師等等,而且只要醫師一個手勢,旁邊的人就知道該遞上什麼工具、如何補位等等,這是長久培養的默契,也是合和互協的精神。」
上人強調成功的手術、優秀的醫療,所倚靠的從來不是儀器而是團隊,優秀的團隊懂得將儀器的功能發揮得淋漓盡致,讓病患得到最佳的醫療效果。所以說最重要的還是人心,人的心念正,就能利益人間;假如人心方向偏差、脫軌,就會造成很嚴重的後果,所以天天都叮嚀大家恆持正向。
要有正念就要有正信,不論信仰什麼宗教,都不能脫離正道。慈濟醫院是基於佛教精神創立的醫院,「為佛教」更不能脫離佛教的宗旨;「為眾生」,眾生苦難偏多,尤其大家在醫療工作中接觸許多病患,有的家貧再加上生病,妻離子散、家庭破碎,他們唯一的希望與依賴就是醫師,殷切期盼經由醫療能恢復身體健康,這就是醫療的價值。