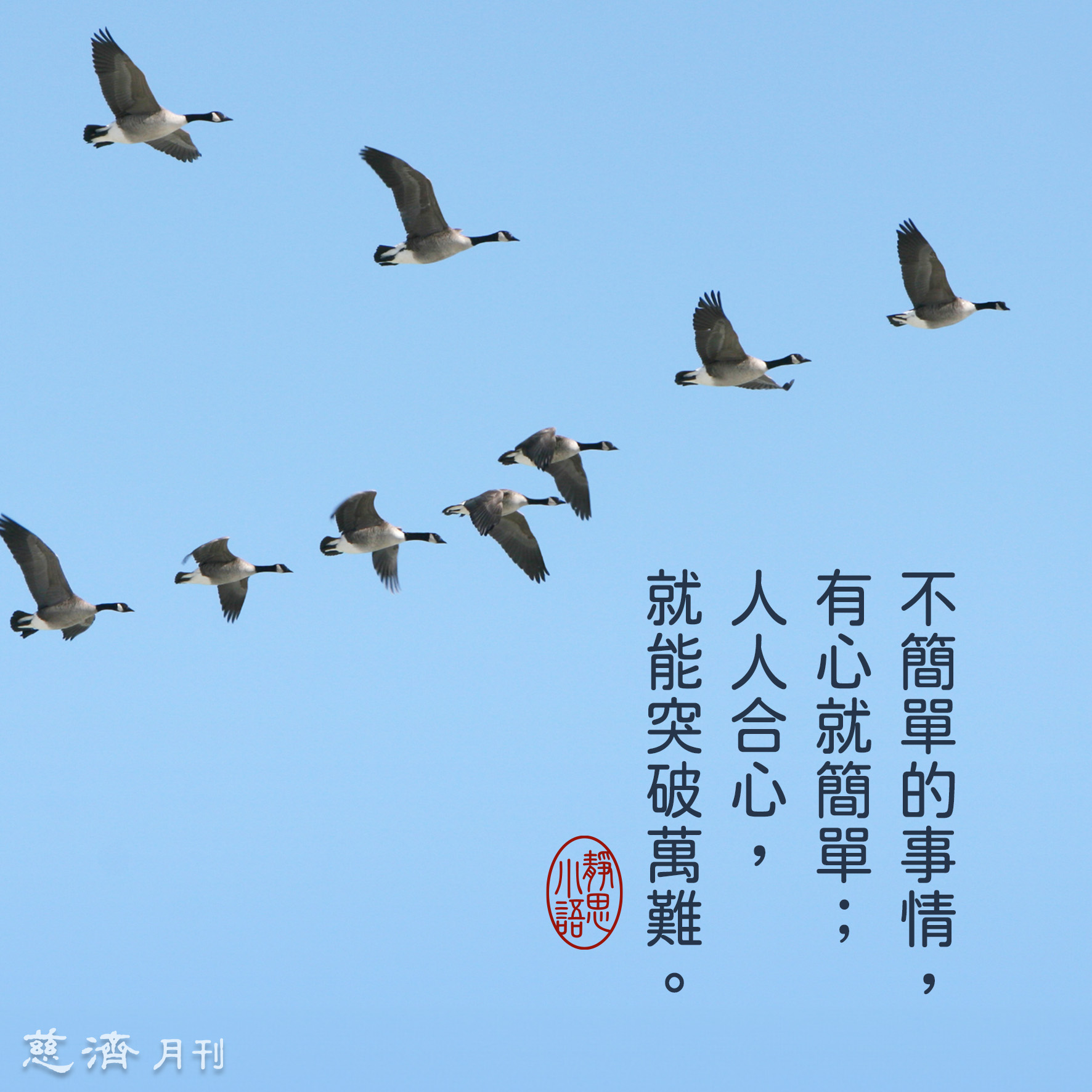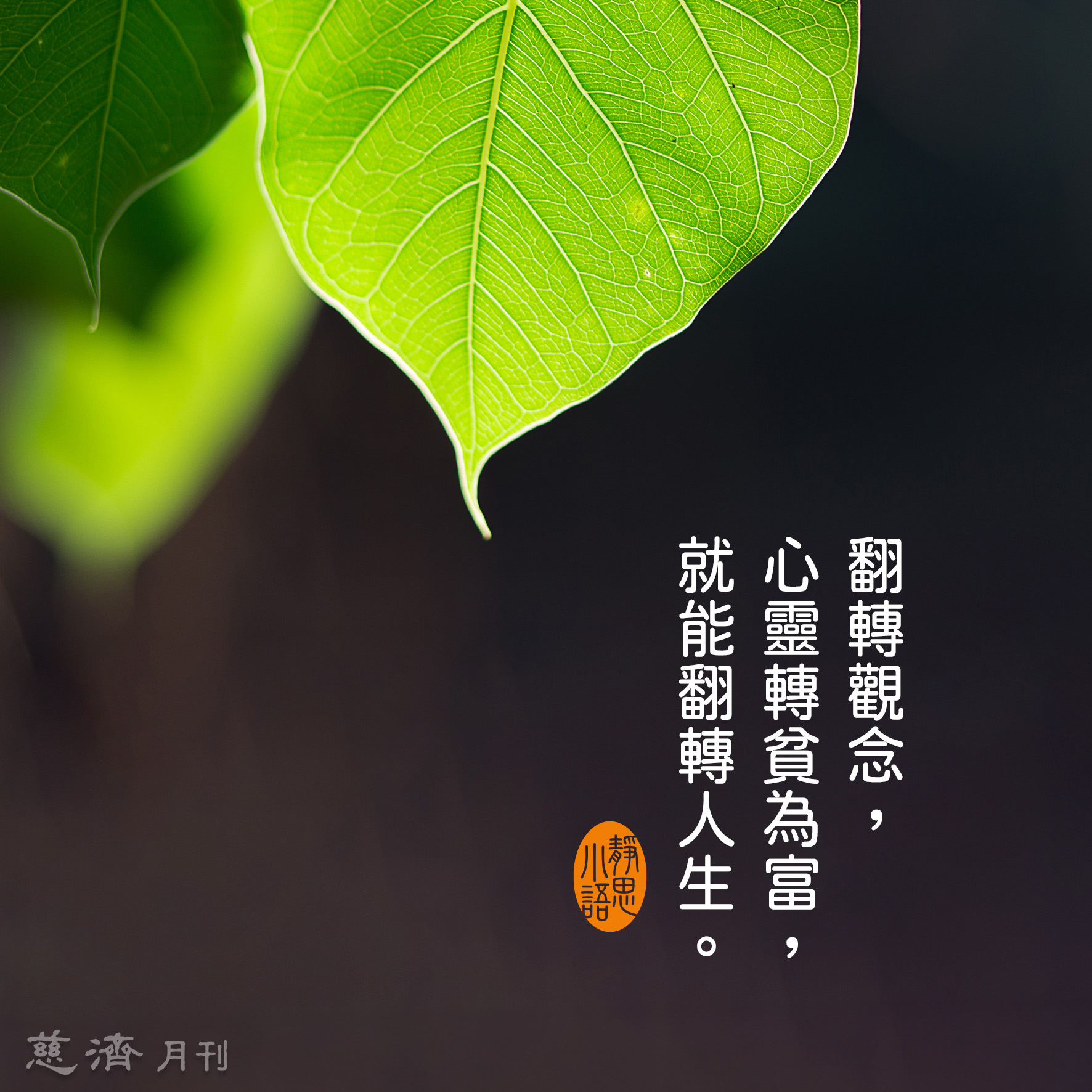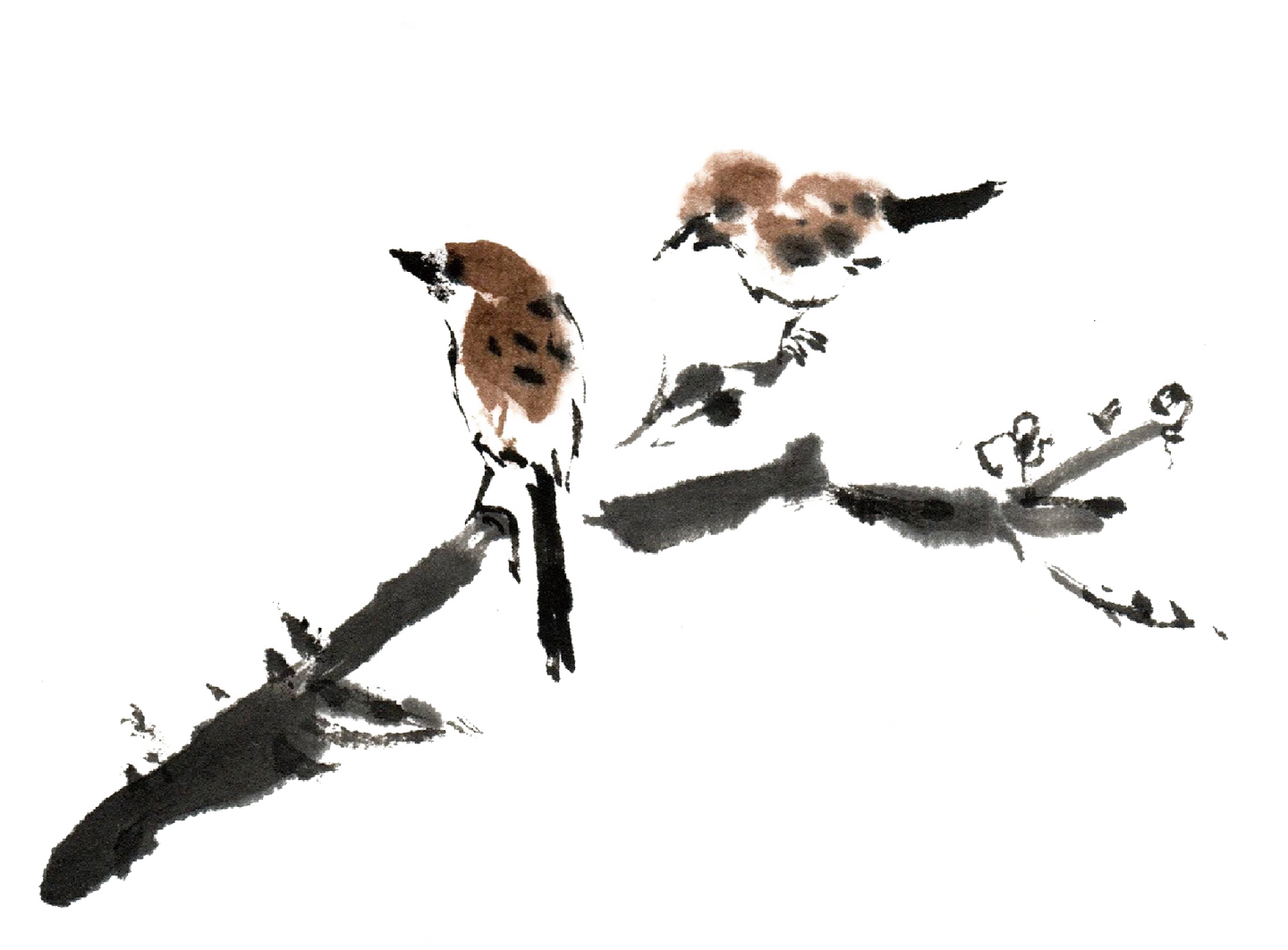11.16《農十月‧十六》

【靜思小語】不計較被批評、也不障礙自己,為人間付出,腳步更要踏得穩、做得好。
一念心,一秒間,一輩子
臺北慈濟醫院腸胃肝膽科、一般外科、大腸直腸外科團隊晨間分享後,上人說,人生苦,但是平安無事時不覺得,直到無常現前,身有病痛,或年老衰弱,感受就很深刻了。認知苦、空、無常的真實相,更要把握時間,把握那一秒鐘所發的一念心,那一秒鐘就是一輩子,因為那一念間的一秒鐘,所發的這一念,也許就是一生的方向。
「感覺這一輩子,活得很充分,也是很滿足,因為我每一分秒的生命沒有空過,而且腳踏實地,不是踏不到地面的太空漫步。」上人提到,七年前行腳到臺中,與烏克蘭籍的前蘇聯太空人卡德尼克談話,詢問他太空漫步的感覺,經由翻譯解說,歸納起來就是輕無飄渺之感。那次的對談讓自己印象深刻,但過不久驚聞他有一天出門晨跑,回程時在家門前倒下,經搶救不治往生。
「每一個人來到人間,都有各人的生命形態與因緣。而慈濟人有不同的生活背景,早期的資深慈濟人大多是家庭主婦,她們提著菜籃到市場買菜,記著師父說要省下五毛錢做慈善,在與菜販、攤商互動時自然提起,大家聽到五毛錢也可以救人,都踴躍響應。所以我很珍惜這群提菜籃的婆婆媽媽,有她們當初的行動,才有現在的慈濟。」
上人說,大家投入經藏演繹,要理解《無量義經》的經文意義,這部經可以說是《法華經》的精髓,也就是大乘菩薩法的精髓,而自己這輩子所走的路,就是從《法華經》深入,用《無量義經》帶著大家走菩薩道。
上人請大家用心讀,與醫療工作及日常生活面對的人事物結合,會很有心得。「不論你們信仰什麼宗教,都可以讀。我尊重所有的宗教,我的桌上有新舊約《聖經》,我不排斥其他宗教的經典,也希望大家不要排斥《無量義經》,這是慈濟的法髓。看大家投入經藏演繹,每一回我都很感恩,因為慈濟慧命在流傳;聽到梵唄的韻律,看到臺上大醫王、白衣大士整齊的隊伍,好有道氣!我總是深感震撼。」上人說,若醫師們讀《無量義經》,與生活見聞對照、印證而有心得,可以把握志工早會或座談時與師父分享,彼此以慧命相對,將有限的生命轉為永恆的慧命。
很感恩,很慶幸,很佩服
北區師兄師姊分享「溫妮颱風─汐止林肯大郡救災」、「納莉颱風─基隆團隊運送物資難行能行」、「象神颱風─內湖成立中央廚房」等北區慈濟團隊賑災歷史事蹟。
上人開示,回想過去,每一個災難畫面歷歷在目,都很感恩、很慶幸有慈濟,慈濟人勇於承擔。昨天也聽到二○一五年復興航空在基隆河南港段墜機事件發生後,臺北慈濟人在河岸成立服務中心,為搜救人員供應薑湯、熱食,並至多所醫院關懷傷患。「那時毛毛細雨,天氣很冷,人間菩薩不畏風寒且很勇敢,要照顧搜救人員,也膚慰著急痛苦的家屬。所以說,師父很佩服也很感恩慈濟人,感覺到臺灣有慈濟很好。」
「我們在人間付出,也要堪得忍耐,不只是忍著寒風刺骨、忍著日曬雨淋,還要忍受無明風;一邊做,一邊被人罵、被批評。如果去計較,反而障礙自己;總是提高警覺,不要得罪人,人家說什麼,我們雙手合十,彎腰鞠躬,虔誠感恩。總有批評的人,後來也改觀,對慈濟說:『了不起!』慈濟人在臺灣,腳步踏得穩,而且做得好,國際也看見了。」
上人表示,平安就是福,而有福的人,知道世界上哪裏有需要,就去哪裏幫助苦難人。很感恩慈濟人一直以來支持師父,去做師父想要做的事,去關懷師父想要關懷的苦難人,慈濟人都是救苦救難的真實人間菩薩。
溫暖手,溫暖心,溫暖身
日本能登半島在今年元旦發生強震災難後,日本慈濟團隊從元月十三日開始,於重災區穴水町提供熱食;在當地的二階段熱食發放,到三月二十九日圓滿,共提供熱食一萬三千零九十七份。日本石川縣穴水町町長吉村光輝等人,由日本分會執行長許麗香師姊等人陪同,前來新店靜思堂拜會上人,代表穴水町鄉親表達感恩之意。
上人說,慈濟人以真誠的心去關懷、幫助受災鄉親,而與鄉親建立真情。災難發生在寒冬,天氣很冷,慈濟人遠赴災區,供應熱騰騰的麵、飯食,讓鄉親的身心都得到溫暖的撫慰。「我看到當時回傳的畫面,一碗碗的熱麵或熱粥,端在鄉親的手中,感覺是先溫暖了手,進而溫暖了心,才溫暖到口腹。」
「我在臺灣看了很感恩,日本慈濟人將慈濟精神展現出來了。不過災後幾個月,發現受災鄉親仍然住在組合屋,重建之路漫長,慈濟雖然發放見舞金,可以在二、三個月的時間,讓他們過得比較輕鬆,接下來還是很期待,在日本政府決定如何安置這群受災的老人家以後,慈濟也可以盡一分心,讓他們有安穩的生活。」上人教日本慈濟人除了持續關心、幫助受災的年長者,亦密切注意當地政府的後續安排,與町長等人多互動,及時將訊息回傳本會。
《證嚴上人衲履足跡》,是「上人之日記」。
靜思精舍常住每日敬侍師側、記錄言行,經融會貫通於心,轉化為字字珠璣,彙整結集,每年四冊,依春、夏、秋、冬四季出版。
本專欄即精簡摘錄自《證嚴上人衲履足跡》,完整版本請關注每季最新出版品。

11.16《農十月‧十六》

【靜思小語】不計較被批評、也不障礙自己,為人間付出,腳步更要踏得穩、做得好。
一念心,一秒間,一輩子
臺北慈濟醫院腸胃肝膽科、一般外科、大腸直腸外科團隊晨間分享後,上人說,人生苦,但是平安無事時不覺得,直到無常現前,身有病痛,或年老衰弱,感受就很深刻了。認知苦、空、無常的真實相,更要把握時間,把握那一秒鐘所發的一念心,那一秒鐘就是一輩子,因為那一念間的一秒鐘,所發的這一念,也許就是一生的方向。
「感覺這一輩子,活得很充分,也是很滿足,因為我每一分秒的生命沒有空過,而且腳踏實地,不是踏不到地面的太空漫步。」上人提到,七年前行腳到臺中,與烏克蘭籍的前蘇聯太空人卡德尼克談話,詢問他太空漫步的感覺,經由翻譯解說,歸納起來就是輕無飄渺之感。那次的對談讓自己印象深刻,但過不久驚聞他有一天出門晨跑,回程時在家門前倒下,經搶救不治往生。
「每一個人來到人間,都有各人的生命形態與因緣。而慈濟人有不同的生活背景,早期的資深慈濟人大多是家庭主婦,她們提著菜籃到市場買菜,記著師父說要省下五毛錢做慈善,在與菜販、攤商互動時自然提起,大家聽到五毛錢也可以救人,都踴躍響應。所以我很珍惜這群提菜籃的婆婆媽媽,有她們當初的行動,才有現在的慈濟。」
上人說,大家投入經藏演繹,要理解《無量義經》的經文意義,這部經可以說是《法華經》的精髓,也就是大乘菩薩法的精髓,而自己這輩子所走的路,就是從《法華經》深入,用《無量義經》帶著大家走菩薩道。
上人請大家用心讀,與醫療工作及日常生活面對的人事物結合,會很有心得。「不論你們信仰什麼宗教,都可以讀。我尊重所有的宗教,我的桌上有新舊約《聖經》,我不排斥其他宗教的經典,也希望大家不要排斥《無量義經》,這是慈濟的法髓。看大家投入經藏演繹,每一回我都很感恩,因為慈濟慧命在流傳;聽到梵唄的韻律,看到臺上大醫王、白衣大士整齊的隊伍,好有道氣!我總是深感震撼。」上人說,若醫師們讀《無量義經》,與生活見聞對照、印證而有心得,可以把握志工早會或座談時與師父分享,彼此以慧命相對,將有限的生命轉為永恆的慧命。
很感恩,很慶幸,很佩服
北區師兄師姊分享「溫妮颱風─汐止林肯大郡救災」、「納莉颱風─基隆團隊運送物資難行能行」、「象神颱風─內湖成立中央廚房」等北區慈濟團隊賑災歷史事蹟。
上人開示,回想過去,每一個災難畫面歷歷在目,都很感恩、很慶幸有慈濟,慈濟人勇於承擔。昨天也聽到二○一五年復興航空在基隆河南港段墜機事件發生後,臺北慈濟人在河岸成立服務中心,為搜救人員供應薑湯、熱食,並至多所醫院關懷傷患。「那時毛毛細雨,天氣很冷,人間菩薩不畏風寒且很勇敢,要照顧搜救人員,也膚慰著急痛苦的家屬。所以說,師父很佩服也很感恩慈濟人,感覺到臺灣有慈濟很好。」
「我們在人間付出,也要堪得忍耐,不只是忍著寒風刺骨、忍著日曬雨淋,還要忍受無明風;一邊做,一邊被人罵、被批評。如果去計較,反而障礙自己;總是提高警覺,不要得罪人,人家說什麼,我們雙手合十,彎腰鞠躬,虔誠感恩。總有批評的人,後來也改觀,對慈濟說:『了不起!』慈濟人在臺灣,腳步踏得穩,而且做得好,國際也看見了。」
上人表示,平安就是福,而有福的人,知道世界上哪裏有需要,就去哪裏幫助苦難人。很感恩慈濟人一直以來支持師父,去做師父想要做的事,去關懷師父想要關懷的苦難人,慈濟人都是救苦救難的真實人間菩薩。
溫暖手,溫暖心,溫暖身
日本能登半島在今年元旦發生強震災難後,日本慈濟團隊從元月十三日開始,於重災區穴水町提供熱食;在當地的二階段熱食發放,到三月二十九日圓滿,共提供熱食一萬三千零九十七份。日本石川縣穴水町町長吉村光輝等人,由日本分會執行長許麗香師姊等人陪同,前來新店靜思堂拜會上人,代表穴水町鄉親表達感恩之意。
上人說,慈濟人以真誠的心去關懷、幫助受災鄉親,而與鄉親建立真情。災難發生在寒冬,天氣很冷,慈濟人遠赴災區,供應熱騰騰的麵、飯食,讓鄉親的身心都得到溫暖的撫慰。「我看到當時回傳的畫面,一碗碗的熱麵或熱粥,端在鄉親的手中,感覺是先溫暖了手,進而溫暖了心,才溫暖到口腹。」
「我在臺灣看了很感恩,日本慈濟人將慈濟精神展現出來了。不過災後幾個月,發現受災鄉親仍然住在組合屋,重建之路漫長,慈濟雖然發放見舞金,可以在二、三個月的時間,讓他們過得比較輕鬆,接下來還是很期待,在日本政府決定如何安置這群受災的老人家以後,慈濟也可以盡一分心,讓他們有安穩的生活。」上人教日本慈濟人除了持續關心、幫助受災的年長者,亦密切注意當地政府的後續安排,與町長等人多互動,及時將訊息回傳本會。
《證嚴上人衲履足跡》,是「上人之日記」。
靜思精舍常住每日敬侍師側、記錄言行,經融會貫通於心,轉化為字字珠璣,彙整結集,每年四冊,依春、夏、秋、冬四季出版。
本專欄即精簡摘錄自《證嚴上人衲履足跡》,完整版本請關注每季最新出版品。