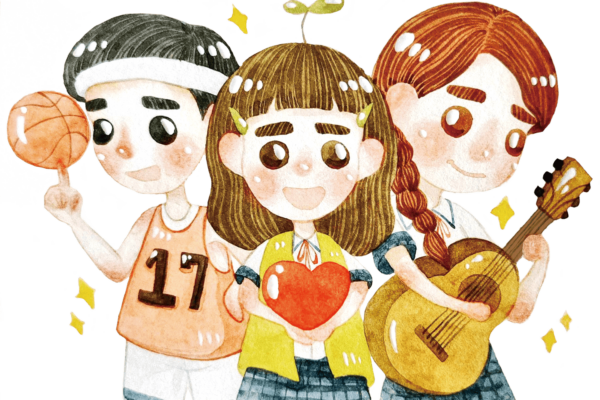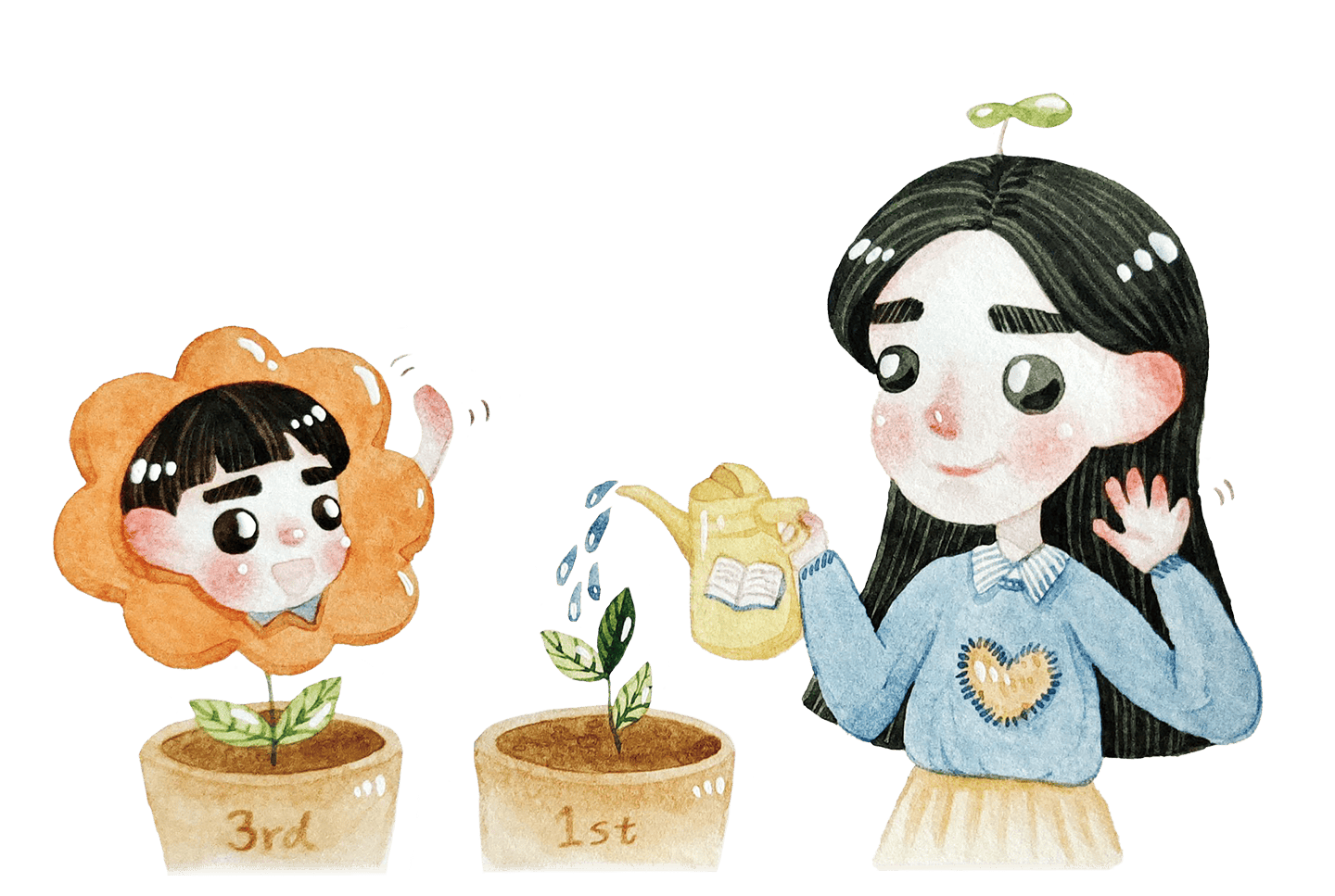
「春風は雨と化す」という言葉がありますが、「ひとたび師と仰いだなら、一生父親のように大事にする」とも言います。しかし、教職もまた職業ですから、境界線を引くべきでしょうか。どこまで責任を果たし、どこで手放すべきでしょうか。
答:私が教師だった頃、よく「セブンイレブン」だと自称していたことを覚えています。生徒と保護者に朝七時から夜の十一時までなら何時でも電話していいと言っていたのです。自宅や学校でのお子さんの行動について相談できる時間をとっていました。唯一、例外がありました。卒業して二年経った生徒の枝さん(仮名)が大きな交通事故に巻きまれ、それを知った他の生徒たちが、不安のあまりどうしたらいいか分からなくなった時でした。夜中の二時でしたが、彼らは「母のような役割」だった私に急いで知らせてきたのです。その夜、私と生徒たちは、焦りと不安の中で眠れない夜を過ごしました。
「教師の心は菩薩と同じです。深い愛と教育に責任を持っています」と證厳法師は諭しています。確かに、「教師」は特別な職業であり、志業でもあるのです。
自律を高めて自愛する
生徒一人ひとりに対応するため、私は自発的に昼休みを犠牲にし、昼寝をせず、他の生徒の邪魔をする生徒を職員室に連れて来て、数学の問題練習や英単語の暗記をさせました。また、生徒たちに「苦を見て福を知る」ことを学ばせるために、休日にボランティア活動に連れて行きました。これらの行動の背景には、生徒たちを心から愛する気持ちがあったからです。
思春期の子どもに自律心を養い、良好な人間関係を育むために、私は生徒たちと「共同で」クラスのルールを決めました。生徒それぞれの環境を尊重する一方で、規則を守る概念を学ばせました。自律心を高めることによってこそ、生徒たちに良い習慣と品格が身に付き、そこから自尊心と自愛が生まれるのです。
クラスのルールが決まると、私は生徒と保護者に手紙を書き、保護者にも知らせると同時に、理解と協力を求めました。そして、それは生徒自身が決めたものであり、ルールの範囲内であれば非難されることを心配する必要はないけれども、ルールに違反した場合は、校則に則って処分を受けるのだと生徒たちに念を押しました。
母親のような教師の責任
学校で私は生徒たちにとって母親のような存在であり、彼らが卒業するとその責任を解かれます。時の洗練を受け、縁の深い子は自然に戻って来ます。そういう類いの深い善縁は賜り物であり、強要ではありません。そして、縁の浅い他の生徒も、自分たちの人生を歩んで行きます。酸いも甘いも、辛さも葛藤も経験しながら、それぞれ無事に暮らしています。
三年生の担任になったことは、神が計らってくれた縁だと思い、私は生徒たちと共に歩んできました。責任の所在ということで、教師としての職務と責任について話しましたが、いつそれを手放したらいいのかは時と状況によります。最後には迷うことなく手放すのです。
愛のある場所にも規則は必要
成功を収めたあらゆる企業が最も重視しているのは「人」であり、管理学を学んだ人は皆、尊重されるべきです。ですから法師は「戒を以て制度とし、愛で管理する」とおっしゃっています。
心理学を学んでいる人も皆、「心の制御がなければ、外的制御はあり得ない」ことを知っています。従って、教室では規則を定めて実行するのは教師であり、子どもが幼ければ幼い程、その影響力は長く続くのです。子どもに一層の注意を払いつつも、原則は絶対に堅持すべきであり、これが教師として最低限守ってきたことなのです。
少子化が進む現代社会では、子どもには正しい指導が必要であり、教育の質はさらに重要になります。それ故、国民の資質向上のためにも、教師は最低限守る規律を抑えていかなければなりません。また、保護者にも、教師を尊敬し、教師の尊厳を損ねないようにしてほしいものです。なぜなら、教師は子どもが卒業すると手放しますが、子どもを育てて来たのは保護者であり、子どもは保護者にとって生涯の「可愛い重荷」だからです。
(慈済月刊六九八期より)