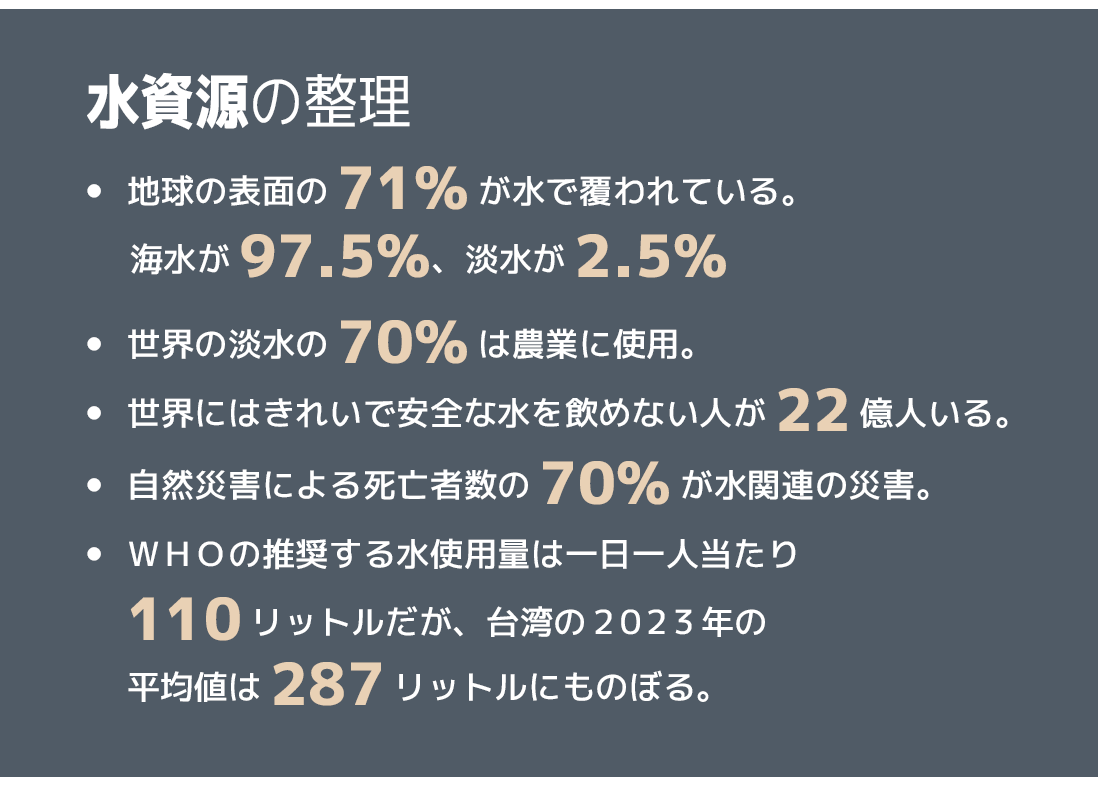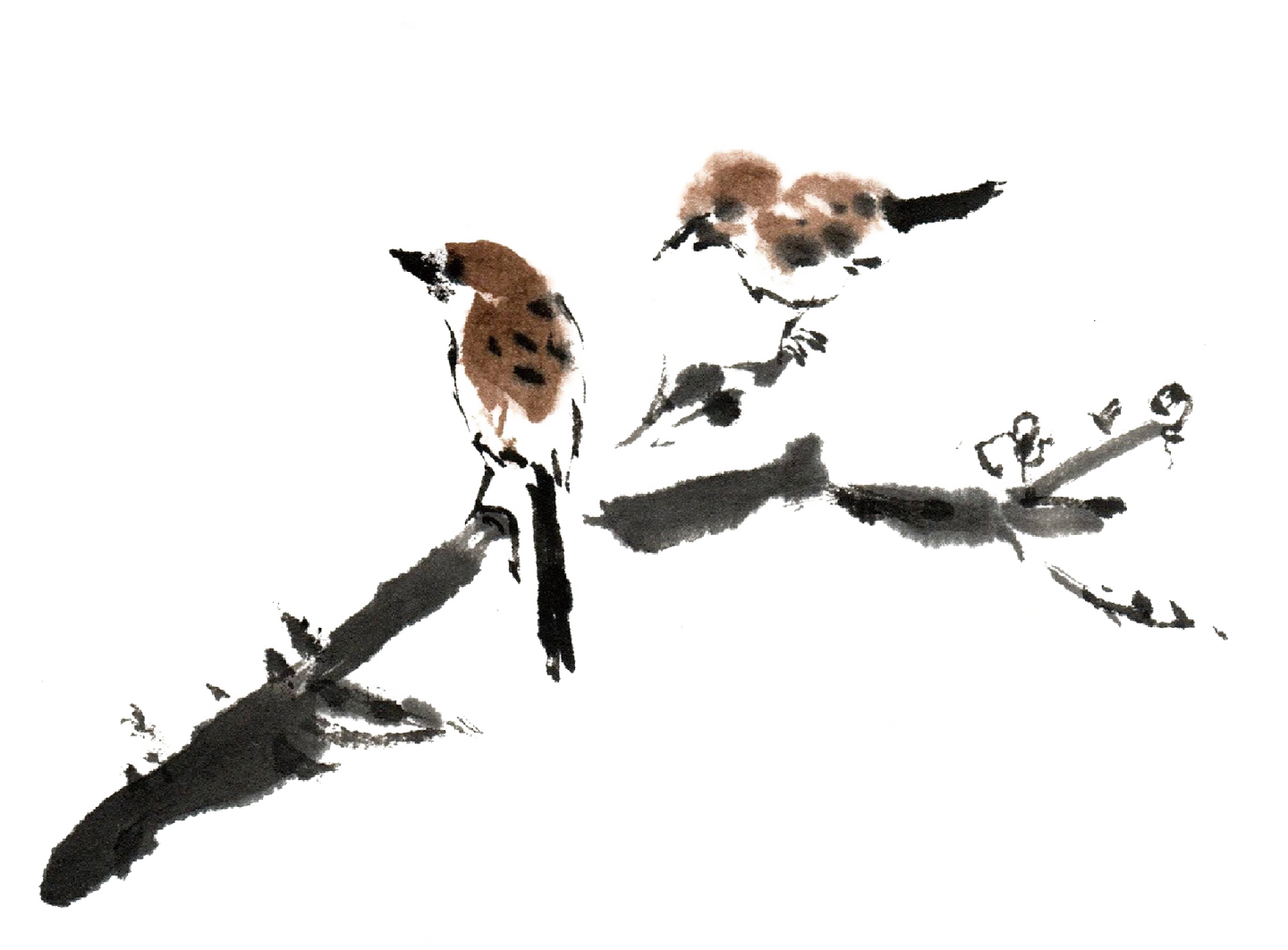
人と人はお互いに関心を寄せ、感謝し合うべきです。お互いの間に摩擦が起きても、感謝の気持ちを持ちましょう。
自分が受け入れ難い誰かに対しても、直ちに心を落ち着かせて感謝の気持ちに変えましょう。感謝で戒律を守って心を定められれば、自ずと智慧が生まれます。
時は経ち、秋が過ぎるともう直ぐ冬で、毎日の日照時間も短くなります。一生の時間は知らず知らずのうちに失われていくため、肝心なのは、今この瞬間を大切にして、警戒心を高めて、時間を善用する人になり、発心すべきことは直ちに発心し、すべき事を行動に移すのです。奉仕すれば得るものがあり、実行しさえすれば良いのです。
心は私たちの修行道場であり、誰もが私たちと共に修行している人たちなのです。人はお互いに関心を寄せ、感謝し合うべきです。例えお互いの間に摩擦が起きても、感謝の気持ちを持たなければいけません。自分が受け入れ難い誰かに対しても、直ちに感謝の気持ちに切り替えるのです。それを「即時修行」と言います。心の中で戒を守り、それが定まれば、自ずと智慧が生まれます。誰もが私たちの修行の成就を助けてくれており、また、人は誰でも成仏できるので、決して人を軽視せず、人を慈しんでください。
正常な春夏秋冬を通して、万物は生気に溢れます。最も重要なことは、誰もが道理に従うことです。近頃の気候と社会は劇的に変化しています。昔は、服を縫って繕ったりしながら着ていたものですが、今は皆体裁を気にします。以前は小学校や中学校を卒業するのは容易ではありませんでしたが、今は教育が広く普及し、海外留学も珍しくなくなりました。
時代の変化に伴って生活スタイルが変わり、求めるものも異なって来ました。かつては、一食にご飯と野菜があれば十分でしたが、今では、千から万ほどもの味があっても、満足できないのです。口の欲を追求するのみならず、衣食住、行動において、利便性を享受しようとするため、大地が供給しなければならない資源は増えるばかりです。
生活はいつも欲念のために争い、大小様々で、「全ては自分のもの」と考え、「欲しい」と思ったら手段を選ばず、「もっと良い物を」と、満足することがありません。まるで灼熱の砂漠のように、心が涸れているので、いくら水をあげても、清涼な気持ちや喜びが得られないのです。
欲念があると競争が起こり、人と人、国と国の間で争いと奪い合いが起こり、社会には安らかな時間などありません。自然災害ならば短い時間で過ぎ去りますが、戦争となれば、安らかな日々はなく、どんなに財産が有っても、故郷から逃げなければなりません。難民が目立たない、社会の片隅にいるのを誰が知っているでしょうか。私はいつも心が苦しくなります。一体何処に彼らの身の拠り所があるのでしょうか?
人類は万物の霊長で、世界に平和をもたらすことができるのも人間なのです。もし少しでも心の偏りがあれば、その差が大きくなって、益々遠くへ行ってしまいます。社会の発展につれ、人の集まりがより大きくなった場合、僅かな差こそが大事なのです。心をしっかり管理することが大切で、少しでも偏ったり、欲があったりすると、ほんの一言が、時には人間(じんかん)に悲劇をもたらすかもしれないのです。
歴史を振り返ってみると、幸も不幸も、人々を利するか、害をもたらすか、全ては一念の差から生み出されています。宗教は人々の概念思想をポジティブに導いてくれます。利益を求める時は、先ず天下、大衆の利益を考えるべきであり、人々が平安であれば、自分も平安になれるのです。
人にはそれぞれの見解があります。たとえ同じ家庭で、同じ両親から生まれた兄弟姉妹でも、異なる考え方を持つことがあります。一家が睦まじくないと親は心配して悩みます。家庭から地域、社会に至るまで、もし考えが異なれば、損得勘定が働いて対立するようになり、是々非々が多くなって、世の中に混乱が広がります。
宗教は人心を調和し、一つの方向性を持っています。善と愛はどの宗教にも共通の精神です。信仰を最も簡単に説明すると、愛であり、博愛、仁愛、大愛、その全ては同様に広くて無尽蔵なのです。どの宗教を信仰するにしろ、互いに尊重して感謝し合うだけでなく、それ以上に合流することで、世界は平等で理想的な社会になれるのです。誰もが宗教の理念に従えば、人間(じんかん)は浄土となり、天国になるでしょう。
世界中の慈済人は、異なる肌の色の人々に接していますが、国家を分かたず、純粋な真実の愛で以て臨んでいます。この世に対する愛おしみの情こそが、「覚有情」なのです。目の前の一時的な情ではなく、永遠で長い情のある大愛です。
この世の苦しみは限りがなく、尽きません。また極端な異常気象が、前例のない深刻な災害をもたらしています。人心に争いの感情が起きると、人間(じんかん)には「濁った気」が生じます。争いがなく、欲を追求せず、無量になり、善行して福を作って「福の気」が大きくなればなるほど、この「福の気」は保護膜のように、人間(じんかん)を守ってくれるのです。
誰かが呼びかけて先頭に立てば、愛の心は啓発されます。あらゆる宗教の正念を結集し、大衆を教育して広い大道に導くのです。敬虔な祈りの力を軽く見てはなりません。その「気」の力が悪を追い払い、善の心を集めて人心の調和をはかり、人間(じんかん)に平和をもたらしてくれるのです。皆さんが心して精進することを願っています。
(慈済月刊六九六期より)

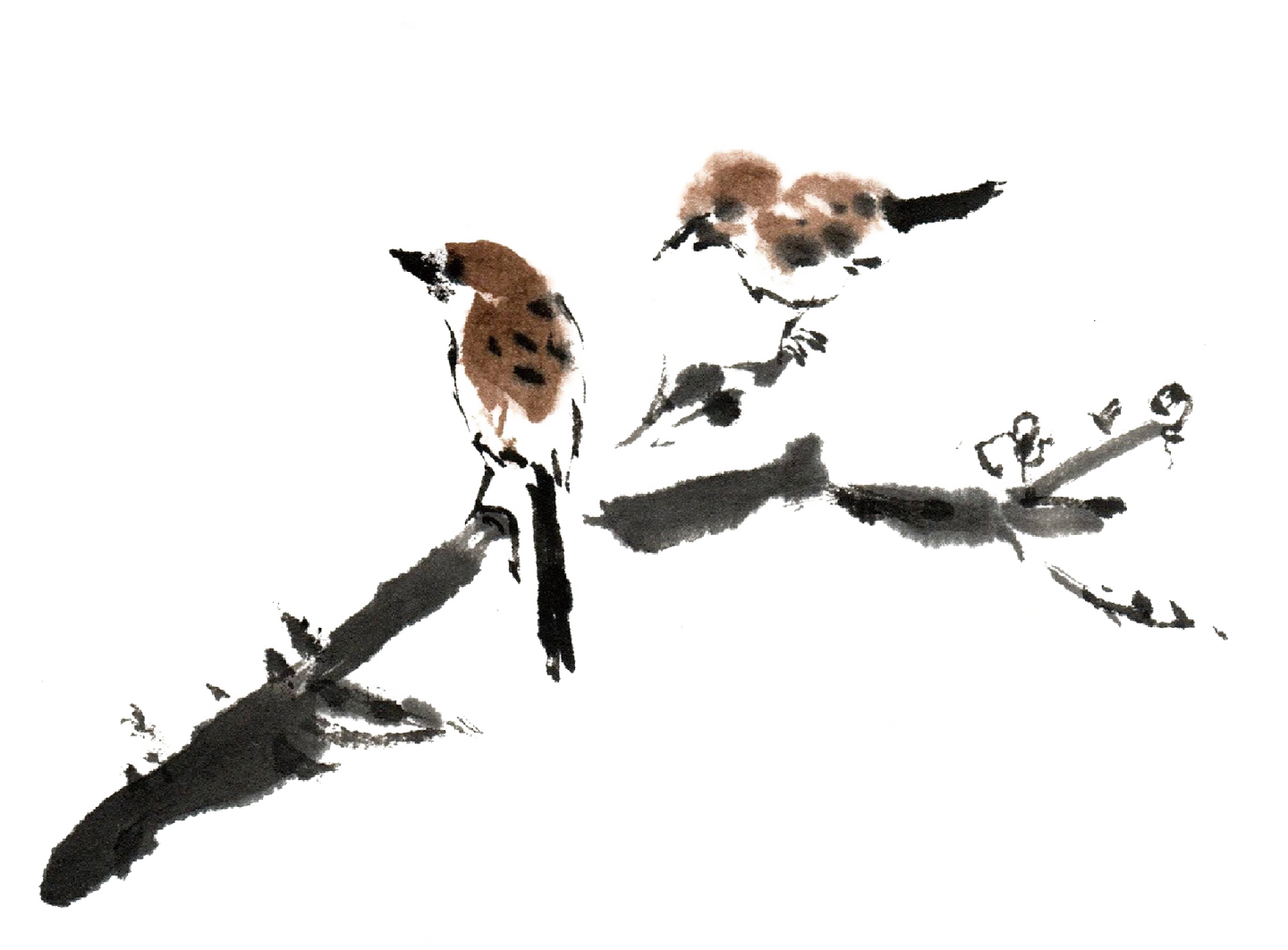
人と人はお互いに関心を寄せ、感謝し合うべきです。お互いの間に摩擦が起きても、感謝の気持ちを持ちましょう。
自分が受け入れ難い誰かに対しても、直ちに心を落ち着かせて感謝の気持ちに変えましょう。感謝で戒律を守って心を定められれば、自ずと智慧が生まれます。
時は経ち、秋が過ぎるともう直ぐ冬で、毎日の日照時間も短くなります。一生の時間は知らず知らずのうちに失われていくため、肝心なのは、今この瞬間を大切にして、警戒心を高めて、時間を善用する人になり、発心すべきことは直ちに発心し、すべき事を行動に移すのです。奉仕すれば得るものがあり、実行しさえすれば良いのです。
心は私たちの修行道場であり、誰もが私たちと共に修行している人たちなのです。人はお互いに関心を寄せ、感謝し合うべきです。例えお互いの間に摩擦が起きても、感謝の気持ちを持たなければいけません。自分が受け入れ難い誰かに対しても、直ちに感謝の気持ちに切り替えるのです。それを「即時修行」と言います。心の中で戒を守り、それが定まれば、自ずと智慧が生まれます。誰もが私たちの修行の成就を助けてくれており、また、人は誰でも成仏できるので、決して人を軽視せず、人を慈しんでください。
正常な春夏秋冬を通して、万物は生気に溢れます。最も重要なことは、誰もが道理に従うことです。近頃の気候と社会は劇的に変化しています。昔は、服を縫って繕ったりしながら着ていたものですが、今は皆体裁を気にします。以前は小学校や中学校を卒業するのは容易ではありませんでしたが、今は教育が広く普及し、海外留学も珍しくなくなりました。
時代の変化に伴って生活スタイルが変わり、求めるものも異なって来ました。かつては、一食にご飯と野菜があれば十分でしたが、今では、千から万ほどもの味があっても、満足できないのです。口の欲を追求するのみならず、衣食住、行動において、利便性を享受しようとするため、大地が供給しなければならない資源は増えるばかりです。
生活はいつも欲念のために争い、大小様々で、「全ては自分のもの」と考え、「欲しい」と思ったら手段を選ばず、「もっと良い物を」と、満足することがありません。まるで灼熱の砂漠のように、心が涸れているので、いくら水をあげても、清涼な気持ちや喜びが得られないのです。
欲念があると競争が起こり、人と人、国と国の間で争いと奪い合いが起こり、社会には安らかな時間などありません。自然災害ならば短い時間で過ぎ去りますが、戦争となれば、安らかな日々はなく、どんなに財産が有っても、故郷から逃げなければなりません。難民が目立たない、社会の片隅にいるのを誰が知っているでしょうか。私はいつも心が苦しくなります。一体何処に彼らの身の拠り所があるのでしょうか?
人類は万物の霊長で、世界に平和をもたらすことができるのも人間なのです。もし少しでも心の偏りがあれば、その差が大きくなって、益々遠くへ行ってしまいます。社会の発展につれ、人の集まりがより大きくなった場合、僅かな差こそが大事なのです。心をしっかり管理することが大切で、少しでも偏ったり、欲があったりすると、ほんの一言が、時には人間(じんかん)に悲劇をもたらすかもしれないのです。
歴史を振り返ってみると、幸も不幸も、人々を利するか、害をもたらすか、全ては一念の差から生み出されています。宗教は人々の概念思想をポジティブに導いてくれます。利益を求める時は、先ず天下、大衆の利益を考えるべきであり、人々が平安であれば、自分も平安になれるのです。
人にはそれぞれの見解があります。たとえ同じ家庭で、同じ両親から生まれた兄弟姉妹でも、異なる考え方を持つことがあります。一家が睦まじくないと親は心配して悩みます。家庭から地域、社会に至るまで、もし考えが異なれば、損得勘定が働いて対立するようになり、是々非々が多くなって、世の中に混乱が広がります。
宗教は人心を調和し、一つの方向性を持っています。善と愛はどの宗教にも共通の精神です。信仰を最も簡単に説明すると、愛であり、博愛、仁愛、大愛、その全ては同様に広くて無尽蔵なのです。どの宗教を信仰するにしろ、互いに尊重して感謝し合うだけでなく、それ以上に合流することで、世界は平等で理想的な社会になれるのです。誰もが宗教の理念に従えば、人間(じんかん)は浄土となり、天国になるでしょう。
世界中の慈済人は、異なる肌の色の人々に接していますが、国家を分かたず、純粋な真実の愛で以て臨んでいます。この世に対する愛おしみの情こそが、「覚有情」なのです。目の前の一時的な情ではなく、永遠で長い情のある大愛です。
この世の苦しみは限りがなく、尽きません。また極端な異常気象が、前例のない深刻な災害をもたらしています。人心に争いの感情が起きると、人間(じんかん)には「濁った気」が生じます。争いがなく、欲を追求せず、無量になり、善行して福を作って「福の気」が大きくなればなるほど、この「福の気」は保護膜のように、人間(じんかん)を守ってくれるのです。
誰かが呼びかけて先頭に立てば、愛の心は啓発されます。あらゆる宗教の正念を結集し、大衆を教育して広い大道に導くのです。敬虔な祈りの力を軽く見てはなりません。その「気」の力が悪を追い払い、善の心を集めて人心の調和をはかり、人間(じんかん)に平和をもたらしてくれるのです。皆さんが心して精進することを願っています。
(慈済月刊六九六期より)