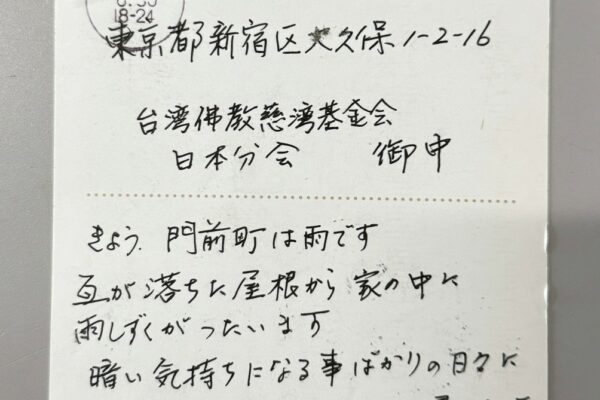人間(じんかん)では、利益を得たなら、それ以上に社会に幸せをもたらして 福の因と縁を途絶えさせないことです。

心が軽やかになる秘訣
上人は、北部の第十三回目の認証式兼歳末祝福会で、皆に人生の価値を「棚卸し」して、人間(じんかん)を利したかどうか、それともボーッとして無駄に過ごして来たかを振り返るように、と言いました。生命を無駄に過ごすことは人生の価値を失うことでもあります。力があれば、奉仕に努めるべきであり、この世を気遣わなければなりません。
「私たちは家庭を守り、事業に専念し、社会を利するような真っ当な事をすべきです。また、一歩踏み込んで、事業で得た利益を社会に還元してこそ、お金儲けに本当の価値が現れるのです」。また上人は、人間(じんかん)に来たのは滅多にない縁であるから、生命の良能を発揮して奉仕すべきであり、この世を利すると共に、社会に福をもたらさなければならない、と言いました。
「この人生で事業に努め、お金儲けできるのは、過去生で福の因を作ったことによるのであり、今生では人と縁が結ばれ、選択によって、成したことが正しければ、お金が儲ります。これを『時應運』(機運に乗じる)または『運應時(時勢に乗じる)』と呼び、時と生命と運命のどれ一つが欠けても成り立ちません。適時に運命に沿えば、過去に植えた福の因によって福が積み重なります。過去に植えた木の種類に従って、それ相応の種子が実り、今この時にこの土地に落ちて日光や空気、水分が得られるのです。そこで因縁と適時の命運によって芽が出て、適時に人間(じんかん)に福をもたらすようになります。そこに人生の価値があるのです。福の因、福の縁があって初めて福を造ることができるのですから、時間を無駄にせず、善の種子を蒔きましょう」。
上人が軽やかな心境を保つ秘訣を語りました。つまり、毎日起きた時に手足を動かし、自由自在に動かせるならば、先ず「感謝」の気持ちが出てきます。昨夜を無事に過ごし、今日も健康に仕事ができることへの感謝です。今日の方向からはぐれず、自分がすべきことをし、仏や法に接し、頂礼(ちょうらい)して仏法を敬い、仏の教育に従うのです。自分の部屋を出て、本堂に向かう時、普通はまだ夜が明けていません。その時、明月を空に見ることもあり、月の満ち欠けを見ながら、時の流れを感じます。人生も世事も無常で、あらゆる物事は時間と共に変化していくため、一刻一刻が平安であることに感謝しなければなりません。

「一日の計は夜明けにあり。毎日朝早く起きた後。心をちゃんと整理するのです。昨日または以前に思う通りにいかなかったことがあっても、それを忘れ、今日も新しい一日が始まり、温かくて明るい朝の光が心の中を照らすようにするのです」。また上人は、「晨語を開示する前はまだ夜が明けていませんが、開示が終わって本堂を出る時は既に、太陽が海面上に顔を出しており、赤みがかった黄色の太陽を見ることができます。その時の光はまだ眩しいものではなく、朝日が山肌や大地を照らし、とても美しい景観を創り出します。それ故、毎日とても満足な気持ちになり、自分は幸福だと感じます。年月が過ぎて歳をとったと感じ、山の向こうに日が沈みかけているものの、それでも時間を無駄にしないよう、自分を励ましています」。
「行脚で移動する際に、車で北から南に向かって海岸線を走っていると、太陽が海の向こうに沈むのを目にすることがあります。その時、私は太陽がいつ完全に沈むのかを注視します。しかし、どんなに注意していても、家に遮られた後、再び海が見えた時、太陽は既に沈んでしまっており、日没はこんなにも速いのかという感じを受けます。ですから、常に太陽の位置に注意していれば、移動している感じがしません。ちょっとでも注意を逸らすと、海面に沈んでしまうのです。その実、人生も同じようなもので、毎日が平安に過ぎて行くことに感謝すべきであり、今を逃さず、未来のために道を切り開くべきです」。
上人は大衆をこう励ましました。「人生は無常で短いものですが、この人生と一個人の力を軽く見てはいけません。小さい蟻は弱くても、方向さえ定まれば、精進して前に進み、何代にもわたってその志は変わらず、最後には須弥山を超えることさえできるのです。慈済人は小さな蟻のように、この五十数年間、こまごました力を結集して四大志業と八大法印を成就させ、人間(じんかん)を利してきました」。
慈済人はまた、淡い光を放つ蛍のようです。数多くの蛍が集まれば、暗い夜は美しいものになります。「自分を大きく見せようとすれば、傲慢になりますが、そうかと言って卑下し、自分を軽く見てもいけません。それは、私たちも生命を使って暗闇を照らす光を放つことができるからです」。また、「『前人が木を植え、後人が涼を取る』と言うように、前人が繁栄する社会の基礎を打ち立ててくれたことに感謝し、今の人がそれを心して繁栄を持続させ、更に次世代にバトンタッチして行くのです。若い人も感謝し、絶えず感謝の気持ちの中で循環する世界を造らなければいけません。
(慈済月刊六六三期より)