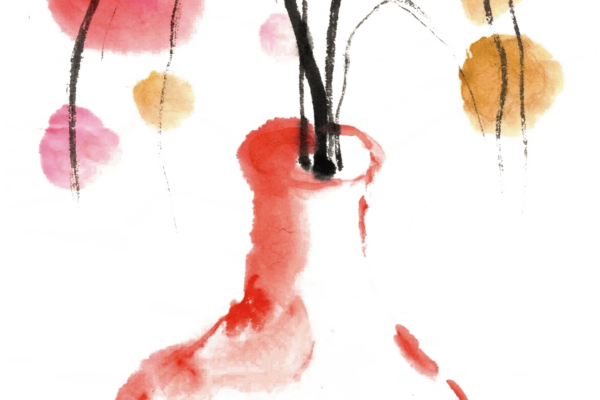陳月恋さんは、一日に何度も出かけて資源回収に励む。定期回収のほかにも、呼ばれればいつでも出かけていく。
七十歳で、体重が三十五キロでも、彼女には本願と力量がある回収物資がビルの何階にあろうと、どんなに多くても、蟻の引っ越しのように、少しずつリサイクルステーションまで運んでいく。
明朝時代に築かれたアモイ城中村にある西潘社福元宮は、保生大帝と媽祖が祭られており、六百年の歴史がある。慈済とも名を同じくするその「保生慈済文化」の理念は、大道に大愛ありという精神を説くものであり、この地の人々に長きにわたって影響を与えてきた。
七十歳の陳月恋(チェン・ユエリエン)さんは、若いころから福元宮の理事長を務め、もう四十年になる。毎朝、夫や家族の世話を済ませると、廟に行って供物台を拭き、お香を立ててロウソクを灯し、お茶を供えてから国の安泰と民の平安を祈る。それが終わると、その日のリサイクル活動を始める。保生大帝の「懸壺済世(医療で人命を救うこと)」と、慈済の志「慈悲為懐(慈悲の心で人に接すること)」は、いずれも同じく人々を守るものだと彼女は考えている。
麻雀をやめて、街に出る
二〇一五年、陳さんは、娘の呉芸娜(ウー・インナ)さんが慈済に参加してリサイクル活動を始めたことを知ると、麻雀も、宝くじを買うことも、街で買い物や食事にお金を費やすこともやめた。そして毎日の暮らしを楽しむようになると、なんだか顔のシミまで薄くなったような気がした。娘は母親に、今までの生活は「命を無駄にしていただけ」だと言った。
娘のこのような変化によって、陳さんは自分も一緒にアモイ慈済リサイクル教育センターを見に行きたくなった。そこで「リサイクル活動は環境をきれいにし、愛を捧げることができる」ことを知った。その日から自分も麻雀と宝くじ、広場でのダンス、タバコをやめ、湖里区にある城中村の西潘社で資源の回収を始めた。そして祖先からの家を空けて、西潘社リサイクルステーションを設けた。

西潘社のリサイクルステーションは、陳さんの自宅で、百年の歴史がある赤煉瓦造りの古民家にあり、周りはアパートに囲まれているが、ボランティアたちはそこで回収物資を整理している。
その家は西潘社の曲がりくねった路地を入り、周囲をビルに囲まれた場所にある。建物の外壁は古く、石灰があちこちで剥がれ落ちている。庭の片隅の花壇の側には、三種類に分別されたガラス瓶の袋が十幾つも積み重ねられてあった。一袋あたり七~八十キロもある。二つある小屋のうち、片方には洋服、靴、布団など雑多なもの、もう片方には瓶や缶、紙などが所狭しと置かれていた。これらの回収品は、近所から持ち込まれたものもあれば、彼女が足を運んで集めてきたものもある。
「ゴトン、ゴトン……」。彼女が歩くたびに、リヤカーが地面にぶつかる音が響く。路上のゴミ箱、市場、住宅地、学校、近所の家々をめぐり、朝から晩まで、雨風をものともせず、腰をかがめて回収していく。
彼女がリサイクル活動を始めた時、村では多くの陰口を叩かれた。賭け事で負けてごみ拾いを始めたと言う人もいれば、乞食のような真似をして子供のメンツを潰していると言う人もいた。清掃員には「ごみばあさん」と罵られ、住宅の警備員には恥知らずと怒鳴られ、追い払われた。
だが彼女は気にすることもなく、堂々と答えた。「人を助け、地球を守る、とても意義ある行為です。盗んでいるわけでも、奪っているわけでもなく、恥ずかしいことなどありません」。
町中を歩いて回収を続け、環境保護を説き続けたところ、周囲の人々も少しずつ理解を示し、協力してくれるようになった。彼女は、日に何度も出かけて資源回収に励み、定期回収のほかにも、呼ばれればいつでも出かけていく。回収物がビルの何階にあっても、どんなに多くても、蟻の引っ越しのように少しずつ運んでいく。
ある時、古紙や古着などの回収品を取りに来てほしいと、ビルの六階に住む住人から電話を受けた彼女は、家事を中断し、リヤカーを引いて回収に向かった。階段を三往復したため、夜になって腰と脚が痛くなり、眠れなかった。
外出する時は回収袋、ガラ袋、手押し車を必ず持っていく。背中に背負った回収袋は、長年使い古して穴が開いている。「もう五年も背負っていますから、慣れました」。この袋には三つの秘密道具が入っている。「小刀と、縄と、ボランティアベストです」。「なぜベストを持っていくのですか?」と聞くと、彼女は「理解できない人に嫌味を言われたら、これを着るか取り出して見せて、私が環境保護をして地球を守り、愛をささげていることを伝えるのです」と笑った。「今では警備員も私のしていることが善行だと理解してくれて、態度も優しくなりました」。

陳月恋さんは、身体は細いが力持ちで、毎月50袋、多い時は100袋近いガラス瓶を回収する。
学校と焼鳥屋に通う
コロナウイルスの感染が蔓延する前、陳さんは毎週月~金曜日の十二時半きっかりに湖里区にある民営の金山小学校に通っていたが、学校の警備員は彼女を見るとすぐに門を開けていた。「地元の人なら誰でも彼女の善行を知っていますよ」。
学校のごみ捨て場には四つのゴミ箱があり、生ごみ用が一つ、一般ごみ用が二つ、リサイクル用が一つとなっている。彼女はゴミ置き場に到着すると、すぐに腕カバーをつけてゴム手袋をはめ、リサイクル用のゴミ箱を運び出し、そこからペットボトル、飲料パック、下書き用紙、作業用紙などを回収していく。たとえ小さな紙の切れ端でも、決して捨てることはしない。
彼女は回収しながらゴミ箱を傾け、最後には頭と体まで突っ込んで、回収できるものはすべて回収し、その場ですぐに分別する。終わるとゴミ箱をモップで拭いて元の場所に戻し、辺りを掃除してから学校を離れる。
警備員を務める遊善雲(ユウ・サンユン)さんは、「夏の暑い時、ごみは汚くて臭います。そこまでするのは、本当に容易なことではありませんよ」と感嘆した。
陳さんはリサイクルステーションに戻って回収物を下ろすと、休むことなく、またリヤカーを引いて出ていく。路地裏の焼鳥屋で酒瓶を回収するのだ。「彼女は真面目で、夏には夜中の一時過ぎに来ることもあります。今の若い人には、そこまですることはできません。彼女の信念には頭が下がります」と焼鳥屋の店長が話してくれた。
また、彼女は酒瓶を一日二回、回収する。普段は夜の十一時頃に二度目の回収に出かけるが、店の前に置かれた酒瓶をガラ袋に入れていくと、一袋が三~四十キロもの重さになる。昼間の疲れで、夕方からしばらく寝ると、一時まで寝過ごしてしまうこともあるが、それでも回収に出かける。いつも「大したことではないし、ほんの気持ちです」と言う彼女には、ボランティアたちも深く感心して賛嘆する。彼女が夜の外出を控えて昼間に回収するようになったのは、新型コロナウイルスが発生してからのことである。

毎週水曜日、西潘社の環境デーになると、庭が回収品で埋まり、小屋の周辺はいつもよりにぎやかになる。ボランティアたちが一生懸命分別して、無事仕事を終えた。(撮影・呉芸娜)
母の歩んだ道を追いかけて
毎週水曜日、西潘社の環境デーになると、小屋の周辺はいつもよりにぎやかになり、中庭にはさまざまな種類の回収物資が山のように積み重ねられる。十数名のボランティアが半日がかりで分別、梱包し、それらを回収車に満載して数往復すると、やっと仕事が無事に終わるということも多い。
「集美」という離島から来た七十歳過ぎのボランティアである紀麗金(ヂー・リージン)さんは、「ここの福田は大きく、分別しなければならない物資もたくさんあります。すべて月恋さんが、見返りを求めることなく、黙々と回収したものです」と言った。ボランティアの黄秀風さんは「月恋さんは、あんな細身でベジタリアンなのに、これほど力と願力があるのですから、私たちも怠けてはいられません。あの母娘は二人とも『頑張り屋さん』なんです」と、心底褒めたたえた。
「母はテキパキとしていて、廟の掃除から病気の父の世話までする他、家のことも全てきちんと片付けます」。行動する母親の背中を見ながら、子供たちはいつの間にか影響を受け、自然に道理を学んだのだと娘さんは言う。
二〇一九年の春節の休みに、彼女は娘さん夫婦と一緒に静思精舎に帰った。「慈済に入る前、テレビで證厳法師を見た時、一目見てとても親しみ深い人だと感じました」。彼女は娘夫婦にこう言った、「證厳法師のお話をよく聞いて、環境保全につとめ、地球を守る方向で行動し続けるのですよ」。
彼女は体が痩せていて、二〇二〇年に歯がすっかり抜け落ちて門歯一本だけになると、食事の量もさらに少なくなったので、体重は三十五キロにも満たなくなった。長年にわたる重労働のために腰を悪くし、骨が神経を圧迫し、静脈瘤が悪化してふくらはぎにはみみず腫れのような青い血管が浮き出ている。「長く歩いたり、気候が変化した時や季節の変わり目には痛みます。まるで誰かに筋肉をつかまれているようです」。
陳月恋さんの左脚には湿布がいっぱい貼られているが、笑いながらこう言った、「毎日痛みますが、気にしません。地面を力いっぱい踏みしめてリサイクル活動に出かければ、痛みは忘れます。慣れているから疲れを感じません」。
「母は痩せていますが、私よりも力持ちで歩くのも速いのです」と娘さんは誇らしげに言った。願う心が力を生む。西潘社のリサイクルステーションでは、一カ月に五十から百袋以上ものガラス瓶を回収している。
高いビルに囲まれた城中村の西潘社は、今年の九月に立ち退きを命じられた。将来そこは運動公園として整備されるという。福元宮の隣に生い茂る背の高いガジュマルの木は、この廟と同じぐらい古い歴史を持っているが、この場所が取り壊されても、これら樹々と廟は近代的な公園に溶け込みながら、将来にわたってこの地の人々を見守り続けることだろう。陳月恋さんは、老いてもなお衰えず憂えず、大愛の精神を広めながら、リサイクル活動に喜びを見出して行くだろう。子孫に浄土を残すために。
(慈済月刊六四八期より二〇二〇年に翻訳)