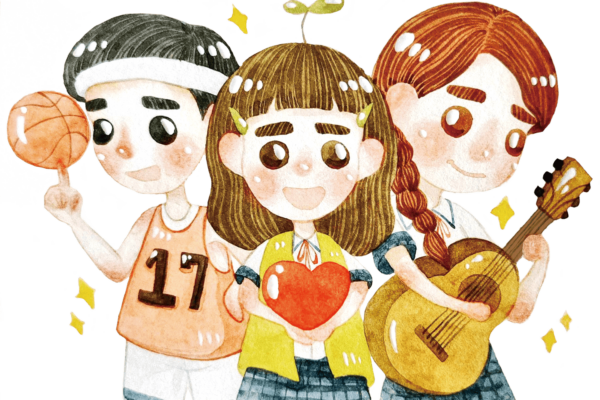編集者の言葉
過去数カ月間の月刊誌『慈済』が報じた時事問題を振り返ると、いつも天災と人災による喜びと悲しみや出会いと別れが織り交ざっているのがわかる。二月号には、トルコのマンナハイ国際学校の成り立ちと様子が紹介された。昨年末に来台したシリア人教師たちは、来る途中で十三年に及ぶ内戦が終結し、自分たちはもはや難民ではないことを知ったのだった。三月号と四月号では、毎年のように住宅に迫るロサンゼルスの山火事について取り上げているが、今年の災害の規模は想像をはるかに超えるものだった。三月号の表紙を飾ったのは、旧正月を前に発生した台湾嘉義県大埔郷の地震被害の様子だ。慈済は、今でも台南の被災地で恒久住宅を建設する計画に取り組んでいる。
月刊誌『慈済』五月号の報道内容を確認すると、世の中が未だ混乱していることにため息が出る。三月二十八日、強い地震がミャンマー中部を襲い、華人の間では「瓦城」という名で知られているマンダレーとその周辺地域では、三千人以上が亡くなった。マレーシア、台湾、インドネシア、中国の慈済ボランティアは、あらゆる手段を尽くして現地に支援物資を届けようとしていたが、国際メディアはアメリカの関税政策による経済的影響に焦点をあてていた。
ミャンマーの軍事政権は四月二日、災害救助を進めるため、四月二十二日まで内戦の一時停止を発表した。すでに被災地に入っていたヤンゴンの慈済ボランティアたちは、停戦を機に積極的に病院や寺院、孤児院、避難所を慰問し、キャンバス生地や福慧ベッド、飲料水、食料などの物資を寄贈した。また、「仕事を与えて支援に代える」方式で村民たちに、被害を受けた寺院や村落に仮設住宅を建てる手伝いを要請した。このほか、国際援助機構や現地の華人団体と意見交換を行い、中長期的支援に向けたさらなる情報を収集した。
直近十年間の世界寄付指数(WGI)の統計によれば、ミャンマーは長い間連続して第一位にランクされており、最も慈善活動に熱心な国と称するに相応しい。一方で、直近の四年間は、内戦や政情不安、物価高騰の中でボランティアは慈善貧困救済を進めてきた。
慈済の世界における慈善活動は、これまで百三十六の国と地域に及んでおり、六十八の国と地域には支部または連絡所を設立している。少しずつゼロから歩み始めて困難な過程を経た甲斐があったと言える。ミャンマーを例に挙げると、二〇〇八年、十万人の犠牲者が出たサイクロン・ナルギスの際は、マレーシアなど各国の慈済ボランティアがあらゆる困難を乗り越え、初めてミャンマーでの被災地緊急援助を行った。その後、彼らが被害を受けた農民を助けるために種籾を配付すると、現地ボランティアになる人が次から次へと現れ、「米貯金」で人助けするという善行を促すようになった。そして、今年マンダレーで大地震が発生すると、彼らは直ちに被災地に駆けつけた。
毎年旧暦三月二十四日は、慈済の創設記念日である。今年の四月二十一日より、慈済は創設六十年目に入った。その日、インドとマレーシア、シンガポール、台湾のボランティアは、インドのラージャグリハにある霊鷲山の頂上で、仏陀が『法華経』を講釈した香堂跡と、静思精舎のボランティア朝の会とをオンラインで結び、梵唄で『無量義経』を敬虔に唱和した。その後、静思精舎と各国の連絡所でも朝山礼拝が行われ、皆は心を合わせ、世界の紛争終結と平穏無事を祈った。
(慈済月刊七〇二期より)