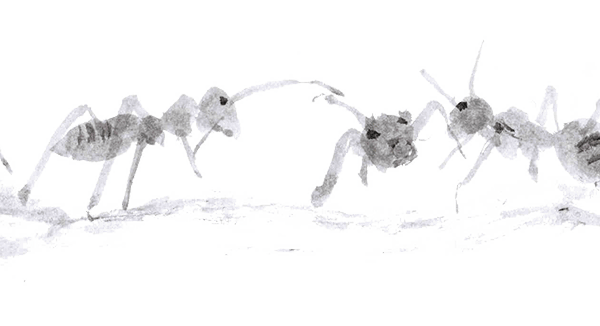記者という仕事の最も魅力的なところは、広く善縁を結べることである。たとえ、それが人生の中の一瞬の出会いであっても、取材相手は私に微笑みや言葉をかけてくれる。
今回オーストラリアを取材して、これまでのイメージを刷新し、希望が見えたと同時に、心の豊かさと喜びを感じた。

今年の国際慈済人医フォーラムは、オーストラリアの慈済ブリスベン連絡所で開催され、オーストラリア全土のボランティアに準備を呼びかけた。慈済医療法人の林俊龍執行長(右端)が、国内外からの来賓に慈済の四大志業を紹介した。(撮影・李雅萍)
これまで證厳法師の開示を聞く機会は多くあったが、必ずしもその真意を完全に理解できたわけではなく、また長年にわたって、慈済人がよく使ってきたおなじみの慈済用語も、私は何度も繰り返し考え、確かめてから使えるようになった。二〇二五年二月二十八日から三月二日にかけて、オーストラリアで開催された「国際慈済人医会フォーラム」での取材は、私にとって「慈済人文素養のレベルアップ」とも言えるものであった。
慈済ブリスベン連絡所の二階はその時、将来的に医療費が払えない人々のケアをする「共同診療センター」にするために、リノベーション中だった。フォーラムの開催期間中、皆このような不便さを理解してくれたので、「同じ目標に向かっている」という一体感と温もりを感じた。
ある日、ニュースの原稿を書き終え、お茶を入れようと席を立った時、偶然に二階の狭い通路で見かけたことがあった。それは数名のベテラン慈済ボランティアたちが同じ方向を見つめて満ち足りた、そして誇らしげな表情を浮かべていたことだった。その視線の先を追っていくと、慈済医療法人の林俊龍(リン・ジュンロン)執行長が、オーストラリアの慈済人医会メンバーを集めて、彼らのフォーラムは大成功だったと賞賛しているところだった。
彼らは大学時代から慈済に関わってきた慈青(慈済青年ボランティア)の先輩たちである。オーストラリアならではといった明るいスタイルで後輩たちをリードし、喜んで奉仕した姿からは、溢れんばかりのエネルギーが伝わってきた。「It’s really, really a gift!(これは本当に、かけがえのない贈り物です)」という林執行長のその言葉で、彼は慈済オーストラリアの将来に、希望が満ちていることを感じたに違いないと私は確信した。
「若い世代が成長し、慈済の使命も担えるようになった」という、これらシニア慈済人の共通の思いを読み取ることは難しくなかった。従って、年長者は栄光のバトンを次世代に渡し、静かに舞台裏で見守り、彼らの活躍を喜ぶだけでいいのだ。慈済オーストラリア人医会の活気ある姿に、印象を刷新した私も、希望が溢れているのを感じた。
台湾で慈済人医会メンバーに同行しての山奥での定期施療や、寒波襲来時に都会の暗闇にいるホームレスのケアを取材するといったことは、記者にとっては日常茶飯事である。そこで出会った医師の多くは中高年で、診療経験が豊富である上に、施療対象とは旧知の仲であるが、また余りにも熟知しているため、お互いのやり取りは水のように淡々としていて、記者の目線からは、何というか、火花のようなものに欠けていた。
しかし、今回のブリスベン取材では、出会った慈済の医師たちが皆、私より若かった。彼らはブリスベン、シドニー、メルボルン、パースなどに在住している。皆、社会のエリートでありながらとても謙虚で礼儀正しく、慈済の志業をしっかりと受け継ぎ、オーストラリアの多様かつ開かれたスタイルで新しい知識を融合させている。そんな彼らの姿に、喜びを感じないわけはない。

フォーラムの歯科ワークショップでは、各国からの参加者が現場で低侵襲修復技術を練習していた。(写真提供・オーストラリア・ブリスベン連絡所)
慈青というゆりかごから慈済大家族へ
「この家は好きに使っていいのよ。寝たい時は寝袋持ってきたらいいし、三、四十人でもカーペットなら寝られるわ。キッチンや冷蔵庫にある物は何でも食べていいのよ。お金は取らないから」。台湾南部出身の情熱的な蘇鄭淑芬(スウー・ヅンスウーフェン)さんが優しく朗らかに言った。
彼女の夫、蘇琪明(スウー・チーミン)さんは、慈済ブリスベンの元責任者で、彼らの住まいは超大型の下宿のようなところで、ブリスベンで勉強する慈済の大学生たちは、殆どそこに来たことがある。次世代の慈青たちをブリスベンで育む「ゆりかご」と言っても過言ではない。
「親は子の手本。私たち年長者は慈青たちの手本なのです。私たちの接し方によって、将来は彼らが次の世代に接する態度が決まります」。蘇琪明さんは嬉しそうに言った。
今回のフォーラムを主に担ったのは、慈青の先輩たちである。内では団結し、外に対してはNPO団体を招いて共に善行をし、さらに地元の行政ともスムーズな連携ルートを築き上げ、慈済の影響力を高めている。このような世代継承は、正しく「青は藍より出でて藍より青し」という言葉を体現しており、偽りのない真心の表れであると感じた。
災害支援には智慧が必要であり、善行にも方法がなくてはならない。台湾とは異なるオーストラリアの社会において、慈済ボランティアたちは、毎回の活動で良い評判を蓄積し、政府や大衆の信頼を獲得してきた。「私はこれまで多くの国に赴任してきましたが、駐在国で災害が起きた時、必ず、真っ先に被災地に駆けつけるのが慈済人でした。被災者に寄り添い、心を癒す支援をし、それに、私たち在外公館の外交業務も支援してくれました」。駐ブリスベン台北経済文化事務所の范厚祿(ファン・ホウルー)所長は、インタビューを受けた時、「ナンバーワン」というジェスチャーをして、目を輝かせて語った。
私が初めてオーストラリアを訪れた時、五十年に一度と言われるサイクロン・アルフレッドに遭遇した。台湾はよく台風に襲われるが、オーストラリアに上陸するサイクロンは、多くはない。「サンシャイン・キャピタル(陽光之都)」とも呼ばれるのがブリスベンである。しかし、そのお陰で私は、慈済ボランティアの迅速な対応動員力を記録することができた。小さいながらも素晴らしいブリスベンの慈済連絡所が、地域住民に安心と安全を与える避難所に変わったことを、目の当たりにしたのだ。
この連絡所は、これまで見てきた中で、最も既成の枠を打ち破った慈済の建物だと言える。現地の建築基準に則っていて、高すぎず、周囲の住宅と調和が取れている上、慈済の特色を取り入れながら多目的な活動ができる空間にしている一方で、オーストラリア社会が重視する公衆ニーズにも配慮している。「入り口から天井のカーブ、両サイドの大きな壁、そして開放的なエリアのガラスデザインからは、この空間が人々を導き、歓迎しているような印象を受けます。まるで、我々が同じ船に乗っているような感覚になるのです。慈済のロゴの一つにあるように」。建築士のジョン・ネイラン氏が語った。
ブリスベン連絡所に入ると、小規模だがジンスーブックカフェがあり、窓辺に座ってコーヒーを楽しむことができる。さらに進むと、「感恩堂(かんおんどう)」があり、そこは慈善活動の中心となる場所である。二階には「合同診療センター」が計画され、医療関係を重点に置いている。三階は「大愛幼稚園」で、広々としたテラスからは空が見え、木に触れることができる。子どもたちは日光の降り注ぐ中で元気いっぱいに走り回っている。
この幼稚園では先生も子どもたちも全員が制服を着用しているというのが、オーストラリアでは稀な光景である。「制服を着る目的は、比較する心を抑えるためです。私たちは大家族であり、子どもたちも入園して帰属感を感じるはずです」。園長の林華妍(リン・フヮイェン)さんが語った。「オーストラリアは多文化で多民族国家なので、幼児教育の段階から他の文化を尊重することを教えています」。慈済の理念である「感謝・尊敬・愛」は、現地の教育カリキュラムとも完全に一致している。正しい価値観であれば、世界中に遍く通用するのである。

今回のフォーラム開会式の時、シスター・アンジェラ(左)の100歳の誕生日を皆で祝福し、30年以上にわたる慈済への支援に感謝の意を表した。(写真提供・オーストラリア・ブリスベン連絡所)
今も続いているストーリー
「一つから無量が生まれる」
オーストラリアの国土面積は世界で六番目に大きく、豊かな天然資源を有し、リゾート大国としても知られているが、人口は二〇二四年になってようやく二千七百万人を超えたばかりである。広大な土地に対して人口は少なく、新たな移民が主な人口増加の源である。慈済志業のオーストラリアにおける発展も移民の歩みと関係している。
一九九〇年、子どもの教育環境を考えた呉照峰(ウー・ヅァオフォン)さんは、台湾からオーストラリアに移住した。彼女は、師匠である證厳法師からのお諭しを心に銘記した。「その国の空の下と大地の上に住むならば、その社会を利し、現地に恩返しすることを理解しなければなりません」。その時、彼女は三十八歳で、「当時は英語がほとんど話せませんでしたが、ベストを尽くしました」。
ブリスベンにあるマター病院に行くと、彼女は、ボランティアをしたいと自ら申し出た。それは、オーストラリアにおける彼女の最初の一歩で、「一つから無量が生まれる」の始まりでもあった。
三十五年前、マター病院の院長を務めていたシスター・アンジェラは、呉さんの善意を観察し、確信し、それから慈済をより深く知りたいと思った。その後、何回か台湾を訪れて、證厳法師に会った。宗教家として、お二人はカトリック教と仏教という異なる宗教に属していても、人道支援に対する志は一致しており、お互いに相手を生涯の親友とみなした。
今回のフォーラム開会式で、ボランティアたちがシスター・アンジェラの百歳の誕生日を祝う計画を立てていると聞いた私は、出発前に彼女に関する資料と映像を調べた。アイルランド出身でありながら、生涯をオーストラリアに捧げた彼女には敬服するばかりで、直接取材できる縁を格別に大切にした。シスター・アンジェラは耳がよく聞こえ、実年齢と不釣り合いなくらいだった。これこそ「愛があれば、老いは寄りつかない」という証だと思った。
インタビューの時に、ちょっとした出来事があった。二階で改装工事をしていて空調の排水音が大きかったのだ。皆が静かにシスターの言葉に耳を傾けていた時、その排水音はまるで川の流れのように響いた。その数秒間、私は心の中で二つのシナリオを思い浮かべた。「一つは、このインタビューを中断すべきだが、失礼になるのでは……。もう一つは、成敗の運命をマイクの集音に任せてみようか?一縷の望みがあるもしれない」。結果として、話を止めたのはシスター・アンジェラの方だった。「私の後ろに流れる川の音は、あなたのインタビューを台無しにしてしまうかもしれないわね」と。その場にいた全員が彼女のユーモアに思わず笑ってしまった。優雅で親しみやすいシスターに取材できたことを、私たちは心から光栄に思った。
呉さんにとって、證厳法師は「智慧の母」であり、シスター・アンジェラは「英語の先生」であった。当初、呉さんは英語がほとんど話せなかったが、今はステージに立って、英語で慈済の理念を語れるようにまでなった。長年、シスター・アンジェラはオーストラリア国内での人脈を活かして、慈済の活動が他の都市へ一歩ずつ広げて行く手助けをした。それに加えて、慈済ボランティアたちが誠実に地道な努力を積んで来たため、今ではシドニー、メルボルン、ブリスベン、パース、ゴールドコースト、アデレードなどのオーストラリアの六大都市に慈済の連絡所があり、前述の四都市には「慈済人医会」が愛の足跡を残している。
長く記者の仕事を続けていると、「長年、頑なに続けてこられた原動力は何ですか?」とよく聞かれる。私は、最前線を取材する魅力というのは、広く善縁を結べることだと思う。たとえそれが人生の中の一瞬の出会いであっても、取材相手のちょっとした笑顔や何気ないひと言があるだけでも、または、私がただの傍観者であったとしても、である。元来はプロの中立的な立場でいようとしていたのが、思いがけず、感動を覚え、心に自ずと力が湧き出て、続けて頑張る能力が啓発されるのだ。
そして、私は證厳法師が引用した仏典の言葉、「我が門に入る者は貧しからず」を、ふと思い出した。私はまだ富める者にはなっていないが、心の豊かさでは、大愛テレビ局の取材で、「我が門に入る者は貧しからず」を体得している。
(慈済月刊七〇三期より)