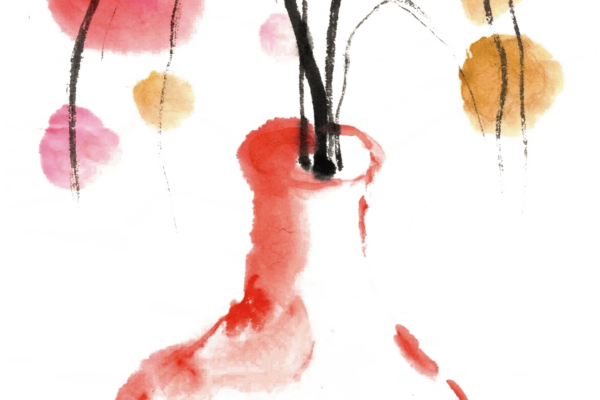編集者の言葉
高齢化社会において死とどう向き合うか。益々多くの人が課題として深く考えるようになった。
医療技術で命を救うのは、逆に生と死の問題を曖昧にしてしまっている。「ニューヨークタイムズ」の記者ケイティ・バトラーは、「天国の扉をたたくとき:穏やかな最期のためにわたしたちができること」という本の中で、一九六〇年代に生命維持装置が発明されてから、半死半生の生命状態を生み出し、「植物人間」と「脳死」という新しい語彙を生み出したと指摘している。治療は命の品質を低下させると同時に、医療コストが跳ね上がり、医師と患者が対立する中、医療スタッフは「命を救う」役割から責任を逃れることはできない。
多くの終末期の患者を含めて、苦痛から解放されるために、行き場をなくした結果として自殺を試みる人は少なくない。しかし、世界保健機関(WHO)などの研究によると、自殺を試みた十から五十人のうち、成功するのは僅か一人だけである。自殺は成功してもしなくても、家族を苦しませ、社会に影響を与える。
中華系の社会では、死に関する話題はいつもタブーである。患者は、親族 との緊密な関係の中で、病から死に近づいた時、複雑な情緒に直面しなければならない。特に「孝行」という家族倫理の影響の下に、患者は生と死を自分の意思で決められるとは限らない。かつて、あるメディアが調査したところ、九十%以上の人は末期に生命維持を放棄することを願っているが、六十%から七十%の人は肉親が少しでも長く生きてくれることを望んでいる。家族が感情的な名残惜しさや心の痛みを経験する時、お互いの意見の不一致によって承諾しようとしなかったことから、患者の願いを素直に受け入れて尊重することが困難になっているようだ。
従って、「死ぬ時期」は知識人たちが勝ち取ろうとする目標となっている。幸いなことに、「患者自主権利法」がやっと二〇一九年一月に施行され、病人の意識がはっきりしている間に、専門の医療チームと相談して、後日、重篤になった時に受けたり拒否したりする医療ケアを選択し、「事前医療行為指示書」に署名することができるようになった。これによって、病状が回復しない場合の道徳的ジレンマを緩和し、「医療法」の枠組みの下に様々な延命措置を拒否できないという患者の単一的な立場が変わることに期待がかかっている。
今期の主題報道に、台北慈済病院で「医療の事前指示書」を最初に署名した人たちの中に、慈済ボランティアの朱文姣(ジュー・ウエンジアオ)さんが含まれている、と紹介されている。肉親を何人も世話をした経験から、彼女は平然と死に向かい合う必要性を深く感じた。また、家族と死について話し合い、お互いの考え方や感じ方を理解し合っている。
話し合いという過程の価値は、お互いが一緒に生命の意義と価値を創造することにある。人間の命には限りがあるが、終焉前に人生という旅を振り返れば、悔いのない歩みを発見することができ、まだ、愛と善念を表現する機会も残されている。
健康な時に良能を發揮し、病気になった時に、前もって自分で如何にして人生を円満に終えるかを決めることで、誰もが生死教育をする講師になることができるのである。このようにして、昔から恐れられ、タブー視されてきた死は、意義に富む「善終(善い最期の迎え方)」に変わり、生きている者に、勇敢に日常に立ち向かう力を発揮させている。
(慈済月刊六五〇期より)