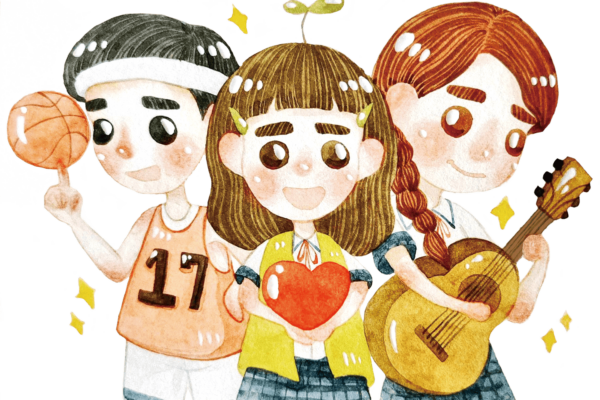編集者の言葉
一月二十二日、花蓮静思精舎では冬季配付と「ウェイルー(旧正月前の団らんの食事会)」が開催された。その日、台湾全土で行われていた五十五回の団らんが円満に終了した。このような心温まる集いが始まったのは、一九六九年からである。今慈済は、台湾全土で二万七千五百世帯をケアしている。毎月の訪問以外に、春節前に新年を迎える準備ができるように買い物カードを贈ると共に、近くの慈済会所に招待して団らんの食事会を催している。慈済という大家庭で皆が一緒に旧年を送り、新年を迎えるのだ。
各コミュニティの記録ボランティアが撮影した写真をよく見ると、慈済人の慎重に事を進める態度と誠実さを感じることができた。年長者や子供のいる家庭がそれぞれ団らんの食事会に参加している様子が、訪問ボランティアを信頼し、受け入れていることを伝えている。
年の瀬といえば、もう一つ心温まる情景を思い出した。昨年十二月、二十名余りのシリア人ボランティアが台湾を訪れ、證厳法師をはじめ国内外の慈済ボランティアたちと座談した。彼らは全員イスラム教徒で、ほとんどがトルコのマンナハイ国際学校の教職員である。十三年間に及ぶシリア内戦の間、彼らは揺るぎない信仰を頼りに避難の苦しみを乗り越えてきたのである。中でも二人の教師の分かち合いは、特に印象的であった。
「トルコに来る前、私は世間一般の人と同じように、安定した仕事に就いて幸せな生活を送り、同じく教師だった妻と二人の子供を育てていました。戦争が起こってからは、少しずつ持っていたものを失い、最後には全てをなくしました。戦争は恐ろしいものです。もう二度と、戦争なんて起きてほしくなく、世界の平和を願っています」。
「避難の道のりは非常に辛いものでした。そして、自分には新しい生活が始まりましたが、シリアにいる家族を思うと悲しくてなりません。父は重い病を患って亡くなりましたが、私は父に再び会うことはできませんでした。何も希望が持てなくなった時、慈済に出会いました。そして、マンナハイで教師を務めるようになりました。この九年間はとても幸せで、感謝に満ちています。私は生徒たちにアラビア語を教えると同時に、良い人間になることや、愛で人助けすることを堅持するよう教えています」。
今月号の「慈済と国連の持続可能な開発目標(SDGs)」シリーズでは、この学校における愛の物語を伝えている。慈済ボランティアと難民の教師たちは、路上で学校に通っていない子どもたちに声をかけたり、家族を養うために工場で働いていた違法労働の児童たちを探し出したりした。この十年間、慈済は三万一千人以上の学生に教育の機会を提供してきた。そのうち数百人が既に大学に進学し、人生を反転させる日がすぐそこに来ている。これは、SDGs4のターゲットである「きびしい暮らしを強いられている子供でも、あらゆる段階の教育や、職業訓練を受けることができるようにする」とSDGs8のターゲットである「あらゆる形の児童労働をなくす」、「すべての人の働く権利を守って、安全に安心して仕事ができる環境を進めていく」、SDGs16のターゲットである「子どもに対する虐待、搾取、人身売買、あらゆる形の暴力や拷問をなくす」と偶然にも一致している。
シリア人ボランティアの分かち合いを振り返ると、法師は皆に、自分の考えが通らないために争いを起こせば、この世に災難をもたらすことになると注意を促した。「人生には喜びもあれば、 悲しみもあります。苦しみは、この世がそういうものであることを私たちに知らせる一種の鍛練です。私たちは常に心を善良に保って、善行に励み、人々が心に愛を持てば、この社会は必ず変わり、平和が訪れるでしょう」。
(慈済月刊六九九期より)