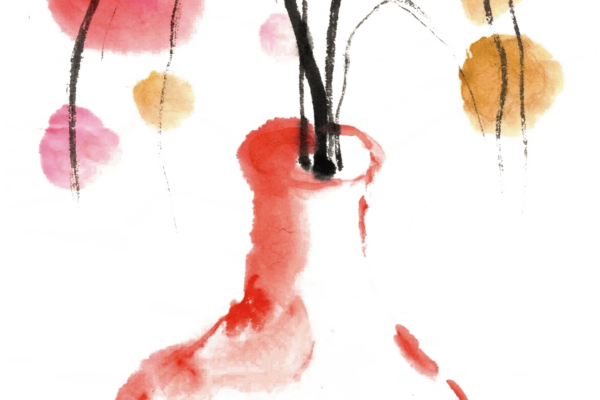目の病気を抱えて、インド・ブッダガヤから戻った。眼科医から、長時間強い紫外線が当たる場所にいたことで起きた疾患だと言われた。たったの一カ月で、このような病気になったのだ。そこで生まれ育った現地の人は、どうしているのだろう?現地に一年半も滞在している年配の師兄師姐(慈済ボランティアの呼称)たちは、どうなのだろうか?

月刊誌『慈済』のカメラマンという仕事は、「郷に入っては郷に従え」で現地の人々と打ち解け、言葉の壁や文化の隔たりを取り除き、人と人の距離を縮める不二法門にあたる。(撮影・楊文輝)
一九八〇年代に大学を卒業し、同級生から記念に一冊の翻訳小説をもらった。ドイツの作家ヘルマン・ヘッセが著作したこの『シッダールタ』を数ページ読んでみたが、何も感じるものはなかった。時が流れ、何度も引っ越しをしたことで、本はどこへいったのか分からなくなった。
二〇二四年三月初め、私は仕事でインド・ブッダガヤを訪れた。一般人からすれば、余り聞き慣れない名前だが、仏教徒にとって、ブッダガヤは聖地である。二千五百年余り前、ブッダはここで成道したのだ。各国の仏教団体は今でもそこに道場や連絡所を設けており、慈済も二〇二三年にその地に連絡拠点を設立した。私は慈済人の活動内容を記録し、映像によって慈済の足跡を歴史に刻む任務を担った。
撮影任務は三月いっぱいまで続き、その後は帰国した。仕事が終わる頃、目に違和感を覚え始めた。黒目と白目の間に小さく膨らんだ白い点があるだけだったが、まばたきする度に、まぶたがその膨らんだ白い点と擦れて、とても不快だった。帰国して直ぐ病院で診察してもらった結果、眼科医から「翼状片」と診断された。長時間紫外線の強い場所での活動によって引き起こされ、熱帯地方の人が最も罹りやすい眼疾患だと言う。
医師は、翼状片は元に戻すことはできず、薬で取り除くこともできず、炎症を止めるだけで、悪化を防止するしかない、と言った。仮に悪化した場合は、手術で取り除くしかないが、再発しないとは保証できない。先ず一週間点眼し、もし白い点がまぶたの開閉に影響しなければ、再診する必要はなく、症状と平和裏に共存することになる。
五ミリリットルの目薬をもらった帰り道、自分はインドには一カ月しか滞在してなかったのにこのような病気に罹ったが、そこで生まれ育った現地の人々はどうしているのだろうと思った。そういう疑問を携えていたので、帰宅するや否やパソコンを起動し、インドで撮影した数万枚の画像ファイルを一心不乱にチェックすることにした。

賑やかに栄えたガヤ市街地の交差点は交通量が多く、電動三輪タクシーやバイク、貨物を満載した三輪車の他、歩行者がひっきりなしに行き交い、我先にと道を通り、容易でない日常の浮世絵を描き出していた。
仏教遺跡の入り口にいる人々
想像通り、画像の中には数多くの現地の人の状況が映っており、その症状が現れていた。一目で分かる眼疾患は白内障、翼状片、失明などで、程度が異なる身体障害や栄養失調等も見られた。最もこれらの疾患がある人々に遭遇し易い場所は、各仏教遺跡の入り口で、彼らは寄り集まって聖地巡礼者や観光客に物乞いをしていた。この点は理解に難くなく、本人の身体障害のみならず、カースト階級において最も底辺に属する彼らは、仏教徒は世の人を憐れみ、慈悲深いと思っているからだ。
インドに滞在した一カ月間、頻繁に仏教遺跡を出入りし、入り口の物乞いとすれ違っていた。友人は、慈悲には智慧が必要であり、焼け石に水では問題を解決できないので、施しをしないように、と再三注意してくれた。友人の言うことはもっともなので、私はその原則を守っていた。しかし、ある日の早朝、ラージギルの霊鷲山で任務を終えて下山し、車に戻った時、一人の痩せこけた女性が両眼を失明した若い人を連れて、車の窓の前まで来て卑しい表情を浮かべ、渇望する眼差しであの乾いた両手を差し出した。その刹那視線が合い、なぜか心が揺さぶられ、一瞬脳裏にアメリカの一世代前の写真家、スティーヴ・マッカリーの或る作品を思い出した。雨の日のインドで車内から外を撮影している時に、一人の女性が子どもを抱いて濡れたまま車のドアの側まで来て何かを求めて手を差し出した様子を写した作品だ……。
私は急いで手をポケットに入れ、このような現地の社会の底辺にいる人々の生活を描写するリアリティーのある場面を、ささやかな心付けで交換しようと思った。しかし、時はすでに遅く、インド人のドライバーはすでに車を発進させてしまった。急いで止めてもらったが、車はすでに移動していた。私は窓を開け、気持ちだけのものを与えると、婦人はそれを受け取り、感謝の気持ちを表したが、失明した男性を連れて、ふらふらした足取りで背を向けて離れて行った。私の企みは失敗した。私は自分のことを硬骨漢だと思っていたが、実のところ、自分の骨には、気づかないくらい小さな優しさが隠れていたのだと、ふと気づいた。
朝日が差す時刻、粗末な手作りの木造の手押し車に横たわった1人の重度障害の子どもが、マハーボディ寺院の前で、善意の人による布施を待っていた。ここで生計を立てるのは容易ではないが、障害者は尚更だ。

慈済が定義する福田
仏典の記載によれば、シッダールタ王子は城を出た時、老人や病人、死者、修行者に出会い、人間(じんかん)の生老病死の苦しみを深く感じ、人生の離苦(りく)の道を考え始めたとある。苦心して長く瞑想しても悟ることができず、やがて月が出た或る晩に、馬に乗って家を離れ、修行の道に入った。最後は転々とした挙句、ブッダガヤで悟りを開いて仏陀となった。
時が過ぎれば、当時の人間(じんかん)の苦しみを知ることはできないが、二千年余り後の今日、仏陀が生活していた空間で、一カ月間見聞きし、触れた生活体験を仏教の歴史記述に照らし合わせると、私の独断的な推測だが、社会の底辺に生きている現地の人々の条件は、さほど大きく変化していないのではないかと考えられる。例えば生活面では、まだ改善する余地が大いにある。慈済の語彙が定義するこの空間は、即ち福田である。空間が大きければ大きいほど、福田も大きいのだ。
慈済のブッダガヤでの活動は、主にシンガポールとマレーシアの師兄師姐が責任を持って行っている。この平均年齢が五十歳前後の慈済人グループには、七十才を超えた人もおり、彼らは食事と宿泊代を自費で負担して、一、二カ月滞在する人もいれば、四、五カ月滞在する人もいる。中にはインドのビザが切れたらシンガポールやマレーシアに帰国するか、隣国のネパールに数日間行って戻って来る人もおり、この広大な福田で、精一杯黙々と奉仕を続けている。
彼らは、地方に行って公衆衛生を推し進め、健康診断サービスを提供し、禁酒を勧めている。また、貧困世帯を訪問し、彼らの生活に関心を寄せ、大愛村を建て、学校を訪問して教育において何が不足しているかという聞き取りを行っている。裁縫クラス、パソコンクラス、英語クラスを開設し、微力ながら尽力することで、現地の社会的弱者層の長い間手のひらを上にしていたライフスタイルが変わって欲しいと切に願っている。
自ら参加することで感じられる
まるで影のように、私は毎日師兄師姐たちの外出に同行し、奔走した。眼疾患があるケア対象者の診察に付き添ったり、体に合う杖を探す障害者を関連の店へ連れて行ったり、大愛村の工事の進捗状況を見に行ったり、学校に赴いて学生の学習状況を理解したり、仏教遺跡の巡礼に同行したりした。
転々と一カ月間過ごして帰国したが、上述した翼状片が見つかった時は、一年ほど滞在している年配の師兄や師姐はどうしているだろうかと案じた。
また、ある友人には、あなたたち慈済人はなぜあのような所に行って、割の合わないことをしているのかと尋ねられた。私は彼ら本人ではないので、代弁することはできないが、現実にこの職場で半世紀を過ごして彼らと共に仕事をこなしながら私が得た体験は、楽しいものだった。というのも、彼らは名利でも生活のためでもなく、そのような現実に左右されず、皆で心を一つにして互いに協力し、純粋に奉仕したいだけなのだ。さらに宗教の心情がもたらす信念によって、彼らはすればするほど法悦に満ちているのである。
それから、師兄師姐たちが遠路はるばるここに来て行っているのは、錦上に花を添えようとしているのではなく、雪中に炭を送っているのであり、対象は助けを必要としている人々なのである。無私の奉仕をすれば、相手も誠意で以て応え、あなたを家族とみなしてくれる。このような関係や感覚は、そこに参加するチャンスがなければ、肌で感じられないものである。
正直に言うと、ブッダの故郷で慈済志業を行っている師兄師姐たちは、実のところ、幸福だ。ここはブッダが成道した場所であり、仏教の発祥地なのだから。人々はここで、二千年余りも仏教の済世を旨とする精神を受け継いできたのだ。他の場所と比べて意義深いと言えるのではないだろうか。
(慈済月刊六九二期より)