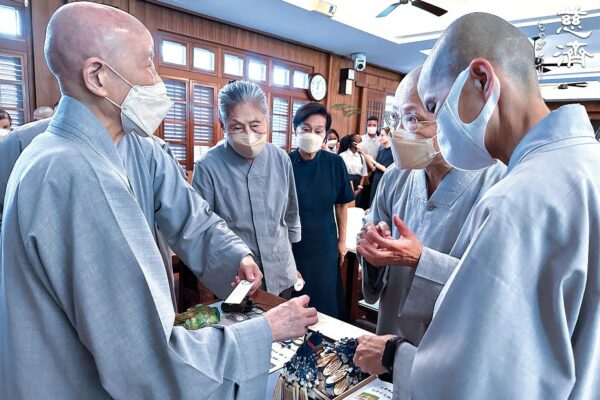慈済移動環境教育車が汐止区の長安小学校にやってきた。子どもたちが手にした行動目標プレートは、リサイクル素材でできている。(撮影・蕭耀華)
今や「必修科目」となった環境教育。慈済の環境教育は口先だけではない。三台の移動環境教育車は、二〇二五年上半期の予約がすでに埋まり、「キャンセル待ち」となっている。
多数の静思堂が現在、国の「環境教育施設」の認定を申請している。また、学生たちに広く参加を呼びかけて、第四回環境保護防災ヒーローPK戦㊟も開催中だ。
㊟競技内容:PaGamOプラットフォームにて、クイズ評価式ゲームをオンラインで競うもの。テーマは「環境保護防災知識」で、出題者は台湾師範大学環境教育研究所の葉欣誠教授。
「
使うとよくない物は何?使い捨て食器と割り箸のような消耗品だよね。じゃあ、私たちが一年間に使うコップを積み重ねると、家が何軒建つかな……?」
慈済ボランティアの曽秀旭(ヅン・シュウシュー)さんが問題を読み終えるよりも早く、反応の速い子どもたちが待ちきれない様子で答えを言った。「環境の5R」について教える時、曽さんは、じっとしていられない子どもたちに、少しの間エネルギーを発散させてから、両手を挙げて復唱してもらった。「使わない、減らす、何度も使う、修理して使う……」。
これは、慈済の移動環境教育車「ネットゼロ未来館」が、新北市汐止区長安小学校で行った巡回展での活気ある一コマだ。広さは屋内の展示スペースとは比べものにならないほど狭いが、内容では決して引けを取らない。「ネットゼロの四大転換項目‥生活、産業、エネルギー、社会」や、自然と人工のカーボンシンクの紹介など、どれも一目で分かる展示になっている。この教育車は古いコンテナを改造したものだ。分かりやすいパネルやビデオがあるので、ボランティアは三時間の講習を受けるだけで、環境保護、ネットゼロ、持続可能性などについて小中学生に説明できる。
長年、汐止の慈済ボランティアと連携してきた長安小学校は、この「秘密道具」を知るや早速申し込み、校門に隣接する空地に駐車場所を設けた。一週間の開催期間中には、各学年がそれぞれ環境学習に訪れたほか、学校に出入りする保護者や業者、近所の人たちにも開放し、一緒に話を聞いたり体験したりすることができた。
一九八〇年代から、員山仔放水路が開通する二〇〇五年までの二十年以上にわたり、台風が来るたびに長安小学校では浸水した。汐止に住む年配の慈済人や、北部の慈済ボランティアたちが数多く校内に集まり、溜まった泥をスコップで少しずつ片付けたものだ。
長安小学校では、災害が最もひどかった当時のことを歴史の教訓としている。洪水で校務が滞ることのないよう、今では事務室やコンピューター教室は三階以上に設置されている。また、環境保護や防災教育には特に力を入れている。包志強(バオ・ヅーチャン)校長は、「本校の運動会や文化祭には千人以上の来訪者を迎えます。活動と組み合わせれば、もっと大きな効果が得られるでしょう」と期待した。
人類の持続可能な未来へ行動を
「ネットゼロ未来館」の他にも、慈済の移動環境教育車には「KOKO㊟のネットゼロ・グリーンライフ館」、二〇二四年十一月に使用が始まったばかりの「循環型経済館」がある。この三台は二〇二五年の半ばまで予約がいっぱいで、多くの団体や学校が「キャンセル待ち」している状態だ。
㊟KOKOは手話を覚えて人間との会話に成功したとされるメスのゴリラの愛称。

関渡静思堂の環境保護防災教育展で、見学に来た子どもたちは、循環型経済など持続可能な開発の知識を学び、楽しい思い出を作った。(撮影・蕭耀華)
台湾でこれほど環境教育が引っ張りだこなのは、なぜだろうか。発端は二〇一一年六月に政府が「環境教育法」を公布したことにあるのかもしれない。世界に先駆けて、環境教育に的を絞った法律を施行したのだ。
環境教育法では、高校以下の生徒と教職員に、毎年四時間以上の環境学習を義務づけている。さらに、二〇一九年の学習指導要領の改訂で、小中学校の学習内容に環境教育の基本的なリテラシーが取り入れられた。持続可能な開発やESGに対する社会の要求も年々高まっている。教育関係者や一般の社会人も環境教育、あるいは持続可能な開発のための教育(ESD)を切実に必要としている。
環境、サステナビリティ、防災分野における教師の指導力向上を支援するため、慈済基金会は嘉義県政府と協力して、環境保護志業及び環境教育を推進しており、現役の教員向けに、三回の「ワークショップ」からなる研修講座を開いている。
講師を務めるのは、慈済基金会専門スタッフで、国家環境教育賞個人の部優秀賞を受賞した陳哲霖(チェン・ツォーリン)さんだ。陳さんが環境保護を学び始めたのは通信業界を退職した後のことで、国立台湾師範大学大学院サステナビリティマネジメントと環境教育研究所で修士号を取得した。現役教師らの親世代に当たる陳さんだが、その授業内容は常に、「簡単、面白い、役に立つ」をモットーとし、たくさんの覚え歌やゲームを取り入れるなど、先生や子どもたちが楽しく、簡単に学べるように工夫されている。
「人類の持続可能性は、校長先生から生徒たちまで、みんなに理解してもらわないといけません。慈済は慈善も環境保護もしていますが、まず環境保護と環境教育を優先してやらなければ、次々に起こる災害に対応しきれません。専門家は、気候変動が悪化し続ければ、人類の文明は終わってしまうと警告しています。どれだけ良い生徒を育て、どれだけ仕事で成功し、いくらお金を稼ぎ、何棟もの豪邸を持ったとしても、ハワイの大火事のように、一夜にして全てが消え去ってしまうかもしれないのです」。
陳さんは慈済人として、国際災害支援活動に参加した時に目の当たりにした驚くべき災害を例に挙げながら、研修に参加した教師や主任に向かって、心を込めて語りかけた。「これからは、環境教育やサステナビリティをどこの部署が担当するかというのではなく、一人一人の先生が教育の責任を担ってください。そして、子どもたちの手本となるよう、学んだ知識を暮らしの中で実践して見せてください」。

2024年、移動環境教育車は嘉義市科学一六八教育博覧会にやってきた。ガイドボランティアは、訪れた先生と生徒に説明し、交流を深め、充実した時間を過ごした。(撮影・蕭智嘉)
生徒は教師を見習う
各校の先生たちは、しばし忙しい校務を忘れ、環境教育の達人と一緒に、手を動かしてゲームを楽しんだ。最新の環境教育の知識と、簡単で面白い実用的なゲーム教材を組み合わせた時、慈済のワークショップは、嘉義県の教育関係者の間で人気の講座になった。
内容面では、慈済の環境教育講座は温故知新と言うことができる。SDGsの十七の目標や環境保護の5R、気候変動などといった重要事項の多くは、すでに学校のカリキュラムに取り入れられており、先生たちも教えたことがあるからだ。しかし、初心に戻り、新しい教材や教授法を学ぶことで、現場ではよりよい授業を行うことができるのだ。
「学びの多いワークショップでした。『気候時計』のことも初めて知りました。秒単位で動いていくので、子どもでも感覚的に理解できると思います」。嘉義県竹崎郷桃源小学校の呂淑女(リュ・スゥーニュ)教務主任は、模範を示した体験を語った。卒業旅行で、羅東夜市を訪れた時、呂さんはマイ弁当箱を持参し、子どもたちもマイ容器に食べたい物を入れ、ホテルに持ち帰って食べたので、使い捨ての食器類は使わなかった。
「私がこうすれば、子どもたちも自然に真似するのです。自分が行動すれば、子どもたちにも通じます。本当にやりたいと思わなければ、子どもたちはやりません。『プラスチックを減らすのって大事なんだな。地球を守るのって大事だな』と、目の前の環境に意識が向けば、自然といろいろやってみようと思えるものです」と呂さんは話している。
国の認定を受けた
静思堂の小さな学び舎
SDGsの十七の目標のうち、環境教育は目標4の「質の高い教育をみんなに」にとって欠かせない部分であり、そのターゲットとして、二〇三〇年までに持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにすることが、全ての学習者に必要だと明確に掲げられている。
現在、台湾の環境教育の内容は、生態系保護や気候変動対策に重点を置いているが、実際に大きな影響力を発揮できるかは、環境学習後に、SDGs目標12の「つくる責任つかう責任」で実践する程度にかかっている。
環境や持続可能な発展について、より多くの子どもや大人に学んでもらうため、慈済では比較的規模の大きいエコセンターに「環境教育センター」として学習展示や体験コーナーを設置した他、国の「環境教育施設場所」認定を目指し、各地の静思堂の設備や展示のレベルアップを図っている。現在すでに高雄静思堂と台中静思堂が認定を受けた他、北部の関渡や双和などの静思堂も申請準備を進めているところだ。
高雄静思堂を見ると、三つの学習ゾーンがあり、そのうちの「低炭素生活館」と「気候変動館」は、環境教育施設で行っているテーマを網羅している。少し変わっているのが「慈悲の科学館」だ。ここは慈済の見所とも言え、福慧間仕切りテントや福慧折り畳み式ベッド、緊急浄水援助艇、全地形対応車(ATV)などが展示され、どれも「現役」で慈済の災害支援活動で活躍しているものだ。
台中静思堂も同じく三つの展示館がある。そのうち、「アースフレンドリー館」では、台湾中部大地震の記録と科学的知識が展示されている。これらの展示と講座「持続可能な生命への道を開く」で、小中学生に地震災害に関する基礎知識を伝えている。また、被災後に建設された大愛の家や希望プロジェクトで建てられた学校に、通気性、緑化、再利用などの「グリーン建築」の理念が、いかに具体化されているかを学ぶことができる。
- 2011年、政府は「環境教育法」を施行したが、国連が2016年から17の持続可能な開発目標(SDGs)の推進を始めたことから、現在の環境教育は、「環境」という名前ではあるが、持続可能な開発に関する内容が含まれている。
- 2019年新学習指導要領では、環境教育を環境倫理、持続可能な開発、気候変動、災害防止、資源とエネルギー持続可能な利用の5つのテーマに分けている。
- 環境教育法では、公的機関、公営企業、高校以下の学校、政府が基金の50%以上を支援する財団法人に対し、すべての職員、教師、生徒に4時間以上の環境学習講座を受講させるよう義務づけている。

慈済は、嘉義県で小中学校教師向けにワークショップを開いている。陳哲霖さん(中)は覚え歌やゲームで、持続可能な開発に関する知識を分かりやすく教えている。ここで学んだことは授業に活かされている。(撮影・黄筱哲)
ハイスペックで人気の関渡展示場
すでに認定された慈済の環境教育施設と「準」環境教育施設の中でも、関渡静思堂の「環境保護防災教育展」は紛れもなく一番人気のある展示区域である。二〇二四年十月に展示されて以来、毎週様々な学校が校外学習に訪れる。ブリーフレポートを聞き終わって、展示ゾーンで「ゲーム」を始める前に、案内人が生徒たちに、「後で汗をかくことになると思いますから、上着を脱いで椅子の上に置いてください」と言った。
「環境保護防災教育展」の展示区域には、十の関門がある。写真パネルだけでなく、VR、ダンスマシン、防災RUNなどの双方向型展示もある。関門「地球が熱を出している」では、温室効果ガスを一番多く排出する「大魔王」を当てるクイズがある。牛や羊、豚、鶏などの牧畜業だろうか。それとも、飛行機や車、船などの輸送業だろうか。
答えを開けてみると、牧畜業から排出される温室効果ガスが十八パーセントを占め、輸送業の十四パーセントを僅かに上回っている。そこまで来ると、子どもたちは、肉を減らして野菜中心の食事をして、なるべく公共交通機関を利用するようにすれば、一石二鳥で二人の魔王を倒し、地球を守る小さな勇者になれることが理解できるのだ。
ゲームクリアの最大の収穫は、有形の賞品ではなく、目に見えない知識と内省である。明徳小学校五年生の思嘉(スージャ)さんは、「家畜の動物が温室効果ガスを出すから、肉を食べると地球温暖化になるのだと、改めて分かりました」と言った。
クラスメートの尹睿(インルェイ)さんは、どんどん進んでいく「気候時計」にとても深い印象が残ったという。「『世界の終わり』が直ぐそこに来ていると知りました。何百年も先のことだと思っていました」と言った。
気候時計は、地球の気温が一・五度上昇するまで、もう五年も残されていないことを示している。状況が改善されなければ、未来はどうなってしまうのだろうか。尹睿さんは、初めは怖いと思ったけど、「きっと止められると思います。資源をリサイクルしたり、肉をあまり食べないようにしたりして、氷河がこれ以上溶けないようにしようと思います」と言った。

関渡環境保護防災教育展では、VRを使って海亀と一緒に海の中を悠々と泳ぐことができる。講座やアウトドア学習、見学などの方法で環境教育が行われている。(撮影・蕭耀華)
世界と共に緑の人材を育てる
樹を育てるには十年、人を育てるには百年かかる。教育は一朝一夕で成果が出るものではない。環境教育やSDGも同じだ。長期的な視点で見れば、世代が代わり、価値観が変化していけば、二、三十年もかからずに大きな変化が現れるかもしれない。
環境部の統計によると、二○○○年に九・七八パーセントだった台湾の資源回収率は、二〇一一年には五十パーセントを超え、今もそれを維持している。教育啓発と奨励政策の成果だ。国民が持続可能な環境保護において、心を一つにして行動するならば、未来は変わるかもしれない。
すでに世界で百四十以上の国と地域が、二〇五〇年までにネットゼロ目標を達成すると宣言している。さらにEUでは、二〇二六年から炭素国境調整メカニズム(CBAM)、即ち「炭素税」の導入である。様々な変化は、政府も企業もそして個人も、誰もがネットゼロやサステナビリティに無知や無関心ではいられないのだと教えている。
慈済大学サステナビリティ事務局の江允智(ジャン・ユンヅー)主任によると、台湾金融監督管理委員会は二〇二五年末から、台湾の全上場企業に対し、温室効果ガスインベントリの結果とSDGsへの影響力の説明を含めたESGレポートの提出を義務づけることを公布した。「大部分の上場企業はサステナビリティ部門を設置するでしょうし、中小企業はそこまででなくても、従業員に研修を受けさせたりはするでしょう。間接的に関連の雇用機会が生まれるはずです」。
慈済大学では、サステナビリティの基礎教養を必修科目「慈済人文」のシラバスに取り入れた他、「サステナビリティと防災修士課程」でも、大学三、四年生向けの選択科目として、八単位のミニカリキュラムを開設した。これらの正規カリキュラムの他、温室効果ガスインベントリ、ESGレポート作成研修講座も開設している。
「二〇二五年から慈済関渡志業パークで開講します。温室効果ガスインベントリ等が必要な企業はぜひ参加してください」と江さんは話している。
また、慈済基金会環境保護推進チームリーダーの張涵鈞(ヅァン・ハンジュン)さんも、より多くの学生に環境問題を知ってもらい、環境教育を深めるために、慈済が二〇二四年に行った「環境保護防災ヒーロー養成プロジェクト・学校における開拓計画」について説明してくれた。この中では、引き続きESD講師の育成を進めていく他、各学校に慈済環境保護教育センターでの体験実習を呼びかけている。また、環境教育のための教材を提供し、プラスチックを使わず、菜食を普及させる「エコ文化祭」の開催を支援している。「卒業旅行や校外学習でも、ぜひ慈済の環境教育施設を見学に来てください。その際は、公共交通を使い、なるべく使い捨ての物を使わない『グリーン旅行』の概念を実践してほしいと思います」。
「拍手する手でリサイクルをしよう」を合い言葉とする身近な環境保全活動から、世界の舞台や学術の殿堂に出るまで、慈済人は環境保全やサステナビリティを語り、常に「知行合一」、「実践したことを話し、言ったことを実践する」を貫いてきた。みんなが必要な知識を楽しく学び、その知識を日々の暮らしの中で真剣に実践することで、変革の力を発揮できることを願っている。「創意工夫で環境教育をし、行動で影響力を発揮しなければなりません」と環境教育達人の陳さんは、みんなと一緒に励まし合った。
(慈済月刊六九八期より)

台中静思堂の展示館で、「緊急避難袋」を完成させるパズルに取り組む子どもたち。(写真提供・呉麗華)