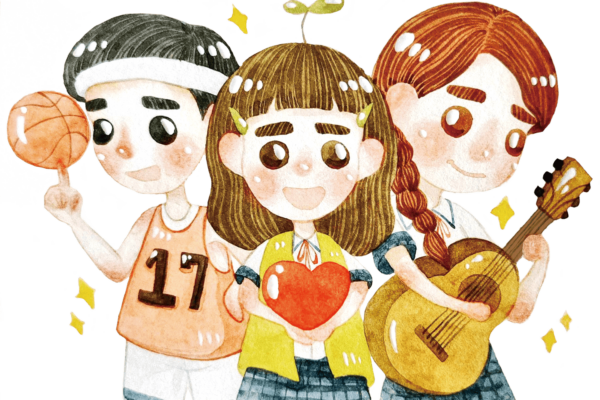私の母、洪玉哖(ホン・ユウニェン)は、出家する縁が三度あったが、願いは叶わなかった。慈済委員の認証を授かってからは、手押し車を押して草屯地区を回り、募金集めやリサイクル活動をした。
腰をかがめる度に「南無阿弥陀仏」と唱えるので、毎日、街角や路地にいても繞仏(にょうぶつ)していることになる。母は仏の弟子であると同時に、模範的な母親であり、私にとってのお手本である。
私の母、洪玉哖(ホン・ユーニエン)は、人生の中で三度、出家して仏道に学ぼうとしたことがあったが、三度とも願いを叶えることができなかった。
彼女は、一九二六年三月十四日に草屯鎮の新庄里の田舎に生まれた。当時の社会は貧しさに加えて男尊女卑の観念があり、勉強したいという彼女の願いは叶わず、長姉と一緒に牛の放牧をしたり、家事に明け暮れたりする日々を送った。母方の祖父は、二男を薬剤師にするために日本に留学させようと、田んぼを売って資金を調達してくれた。後に末の息子も医学部を卒業した。薬剤師と人を救う医師を輩出したことで、洪家は名を揚げた。
母は、病に苦しんでも貧しかったために医者にかかるのは容易でなかったという祖母の姿を、幼い頃から見て育った。人生の苦しみを体験した母は、お寺に行って、法師に剃髪出家の思いを懇願した。しかし、硬く反対した祖父に連れ戻された。こうして、最初の出家の縁は消えてしまった。
一九四五年、母は十九歳で大工職人の謝松釜(シェ・ソンフー)と結婚し、三男四女を儲けた。生活は厳しく、母は出家の願いを断ち切れず、解脱の道を探そうとしたが、子供がまだ幼かったため、父からカンナ削りやノコギリの使い方、ペンキ塗りなどを学び、苦労しながらも夫婦で力を合わせ、家具や勉強机と椅子などを作って生計を立てた。
誠実な性格の父は真面目に仕事をし、手抜きすることがなかったため、収入は多くなかった。母はやりくりして家計を支え、数々の内職をした。後に父が慢性病を患ってから、母は早朝四時に市場に行って、野菜や果物の卸売をしたり、道端で野菜や果物と紙銭を売ったりした。野菜や果物が売れ残った時は、自転車を押して売り歩き、家に帰るのは日が暮れてからだった。
一九九〇年、父が六十六歳で病死し、母は深い悲しみに暮れ、再び人生への未練をなくしてしまった。私たち子供は、母の出家を忍びなく思い、真面目に慈済に打ち込んで、菩薩道を歩むよう勧めた。それ以降、母は慈済に専念するようになり、私たちが帰省する時でも事前に約束しないと会えないこともあった。

仏法を深く信仰した洪玉哖さんと夫の謝松釜さんは、二人とも菩薩戒を受けた仏教徒だった。
毎日手押し車で善行する
読み書きができないことで苦労した母は、教育の重要性を感じ、「たとえ物乞いしてでも、私たちを学校に通わせる」と言ったことがある。新学期の頃になると、いつも七人の子どもの莫大な学費を工面するために、借金したり、頼母子講で資金を調達したりした。草屯鎮で開業医をしていた叔父は、いつも私たちの学費を支援してくれた人で、一家にとって忘れがたい恩人だった。みんなの期待を裏切らず、私たちは全員高等教育を修了し、兄の謝輝龍(シェ・フイロン)は南投竹山秀傳病院の院長を務めるまでになった。
母は、菩薩戒を受けた敬虔な仏教徒で、早くから菜食をしていた。彼女自身の生活は極めて質素だったが、周囲の仏教寺院へ供養したいと尽力し、お経を唱え、法器を叩くことを学び、多くの経典を暗誦することができるようになった。草屯鎮で初めての慈済の種子である張河圳(ヅァン・ホーヅン)師兄は、よく私たちの家に来て慈済の話をした。慈済が花蓮で病院を建設していた頃、母は慈済列車に乗って花蓮を訪れてとても感銘を受け、直ちに病室一つ分の建設費三十万台湾ドルを集めた。一九八九年に慈済委員になった時、私たちは既に成長して自立していたが、母は悠々自適の暮らしに甘んじることなく、證厳法師の後ろについて、人々に奉仕した。
一九九〇年、證厳法師は「拍手する手で環境保護をしましょう」と呼びかけた。母はその教えを実行に移し、道路が彼女の道場となり、四輪車を押して街中を歩きまわった。彼女は、自分で栽培した野菜や仕入れた果物を販売しながら資源を回収したり、募金や会費集めをしたりした。そして、腰をかがめてペットボトルやダンボールなど資源ゴミを拾う度に、「阿弥陀仏」と唱えていた。それが彼女なりの拝仏であった。このようにして、毎日街角や路地で仏法を実践していたので、草屯鎮の多くの人は母のことを知っていて、非常に多くの人が彼女の会員になった。
彼女は、あちこちで資源回収をする途中でバスにぶつけられて入院したことがある。また、バイクに乗った若者が母の後をつけ、ペットボトルを手渡すと同時に首にかけていた金のネックレスを奪ったので、母は転んで怪我をしたこともある。しかし、どんな事があっても、彼女の堅い信念は揺るがなかった。
母は料理が得意で、一度食べた料理は全て調理でき、周囲からコック長と称賛された。私の二人の兄が結婚した時、母は自ら宴席の料理を作って来客をもてなした。そして、国内外で大きな災害が発生し、慈済が支援活動をした時も、ベジタリアンちまきやスープ、昔ながらのタケノコマントウなどを作ってチャリティ販売をした。今でも家族は、母が作ったちまきや薬膳スープの味を懐かしむ。母の右に出る味には出会ったことが無い。
戦争を経験した母は、被災者の苦しみを、身をもって感じていた。平成八年台風九号や921地震、平成二十一年の八八水害の時は、料理のチャリティー販売をしたりした他、誰にでも慈済のことを語り、募金集めをしたりして、あらゆる機会を逃さなかった。毎月、会費を集めに行く日、母は早朝から長男の輝龍、または私の妹の謝素芬(シェ・スーフェン)に頼んで手推し車と一緒に新庄村まで運んでもらい、そこから歩いて会費集めと資源回収をした後、草屯市街地まで歩いて帰宅する。時には夜の十一時を回ることもあって、一日に十数キロを歩いており、その並外れた気力は人々を驚かせた。
洪玉哖さん(中央)は気前よく布施をし、2005年の歳末祝福会で名誉董事の称号を授かった。

七十七歳で海外ボランティア
草屯鎮における母の善行は、多くの人々に感動を与え、集った会員は四、五百人にも達した。最初は募金ノートの記入を人に頼んでいたが、やがて光栄小学校の夜間部に通って読み書きを勉強するようになった。在学の三年間、一度も欠席したことがなく、卒業の時は、成績優秀者に贈られる賞状までもらった。
彼女は慈済病院でボランティアをする事に喜びを感じ、花蓮、大林、台中のどこでも母の姿が見られた。初めは花蓮慈済病院の地下室でシーツの縫製を手伝い、暫くして病室ボランティアをした。彼女は、自身の人生経歴や聞いた仏法をシェアして患者の心を落ち着かせた。患者の笑顔を見られるだけで、母は大きな達成感を感じた。ある日のボランティア朝の会で、母は勇敢にも壇上に上がって自分の人生を分かち合った。その時、人々は初めて、彼女の素晴らしい人生を聞き、仏法が心に入り、それを実践しているのが人間菩薩であることを知った。
彼女は海外での施療活動に参加したかったが、證厳法師は母の年齢を考慮し、長距離移動が負担になるのではないかと心配した。彼女は、大丈夫だということを証明するために、中国の黄山に登り、写真を撮って来て法師に見せた。二〇〇三年、彼女は長男の謝輝龍院長と一緒に、インドネシアでの施療活動に参加した。少し休憩するようボランティアに勧められても、母は「高い航空券を買ってやって来たのは、手伝いをするためです」と言った。
二〇〇五年、母を主人公にした大愛ドラマ『好願連年』が放映された。彼女は、自分が歩んできた人生なのだからその内容をよく知っており、見る必要はないと言って、いつも通り夜遅くまで資源回収をしていた。兄は、母は視力が悪く、夜は危ないと心配して、よく探しに出かけた。私たちの心配を知った法師は、毎晩必ず『好願連年』を見なさいと母に言づけた。法師を深く愛する母は、おとなしく早目に帰宅するようになった。

百歳近い洪玉哖さんが子供や孫たちと一緒に撮った写真。(写真提供・謝輝龍)
善行に導いてくれた母に感謝
母は九十歳を過ぎても仏の教えに従って奉仕し続け、いつも愛を募る募金をすることと仏法を聞いて精進することだけ考えていた。やがて、ほぼ全盲になり、認知症も進んでいたが、耳で仏法を聞いて精進し、亡くなる直前になっても、『心経』や『大悲咒』・『阿弥陀経』を唱えることができた。
看護師である妹の謝素英(シェ・スーイン)は、長庚大学看護学部副教授を務めている。母は、九十一歳で手術を受けて以来、新北市林口区で妹と同居するようになった。素英は母を連れて、念仏会やリサイクルステーションで活動に参加したが、母は募金集めに行きたいとよく口にしていた。
二〇二四年の八月三日、母は自宅で息を引き取った。「何もせずに死ぬよりも、死ぬまで奉仕する方がいい」という自分への約束を守った。六度万行を成し遂げた母は仏の弟子であり、台湾の模範的な母親だと言えよう。全国から推薦された「善人善行」の代表にもなり、私にとってもお手本である。
母は一生、私たち家族のために働き過ぎていたので、三十歳を過ぎた頃、子宮から大量出血した。手術後、父は母を連れて二回も占いに連れて行った。占い師は、「この人はもうこの世にはいない」と断言しながらも、確かに目の前にいる母を見て不思議だと言った。「この世には占いが効かない人が二種類あります。一種類は修行者で、もう一種類は常に善行をしている人です」。
たとえ生活が苦しくても、母は変わらずに善行をしていたので、それが子どもたちに大きく影響して全員が仏教徒になり、人助けに喜びを感じている。私たちは、慈済に導いてくれた母に、心から感謝している。彼女の勇猛な精進ぶりには及ばない。怠けてはいけないと励まし、「上人が担っている責任はとても重く、みんなで分担し合えばその重荷が軽くなり、過去の業も消えるようになる」と母は常に言っていた。
母は生涯にわたって多くの人と良縁を結んで来たため、草屯鎮の自宅で行われた告別式の日には五百人あまりが母を見送ってくれた。母の大いなる心願は、「来世は弘法利生する法師になること」だった。私は、母が既にこの世に生まれ変わっていると信じている。
(慈済月刊六九五期より)

洪玉哖さんは手押し車を押して野菜や果物を売りながら、道すがら資源を回収し、環境保護活動をした。(撮影・林義澤)