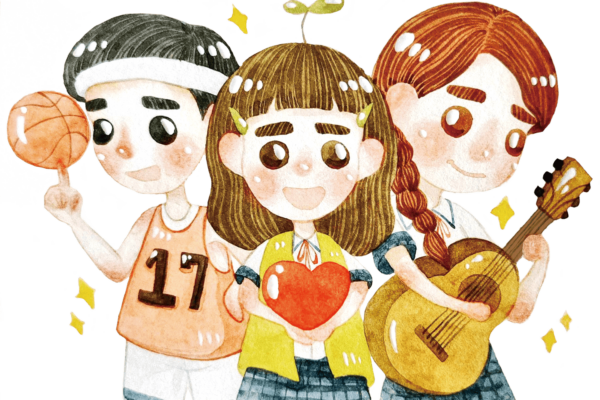メディアには、人々の知識を広げるだけでなく、
智慧を開花させる役目もあり、
誠実に善行して模範を示すことで人々を感動させ、
悟りへと導くのです。

無力感を抱きつつも諦めない
三月二十七日の人文志策会で上人は、大愛テレビを設立したことにより、確実に慈済の四大志業の声を発信し、大愛テレビの伝播の力で大衆に宣伝することができるようになったと言いました。「人間(じんかん)のために、私たちの理想とは何なのかを伝える力を得たのです。四大志業は共同体であり、横のつながりを深めて、人心の浄化のために力を合わせる必要があります」。
「今の世の中を見ていると、やるべきことがたくさんあると感じると同時に、無力感も感じます。しかし、みんなが力をもっと結集させれば、目標を達成できるでしょう。昔の子供たちは、友達をおみこしのように担いで遊んでいました。二人で両手を組み、三人目の子供を持ち上げるのです。私たちは力を合わせ、良い言葉や良い雰囲気を広め、人々が良い行いをし、良い言葉を口にして正しい道を歩むよう促し、社会に良い『歓迎の雰囲気』を生み出すことが大事です。良い人と良い行いが溢れる世界になってこそ、菩薩の世界ではないでしょうか」。
「全てのテレビ局は人々に知識を広げて豊かにすることができますが、智慧を啓発することは容易ではありません。しかし、大愛テレビは智慧を発揮する大愛によって人心を浄化することができます。今の世の中に聡明な人はたくさんいますが、彼らの欲望は高まる傾向にあるため、もし彼らが仏法を求め、善知識を求めるようになれば、間違いなく人心を浄化できるでしょう。もし貪欲であれば、無限に貪り続け、永遠に欲を求めて、奪い合うことになります。毎日国際ニュースを見ていると、非常に心配になり、無力感を感じます。私たちは今、良い因縁を大切にしてそれを善用し、人文志業の持つ伝播という良能を発揮して、仏法を広めることしかできません」。
上人は慈済の創設当時の様子を語りました。信用を築くために新聞の形で半月刊紙を発行し、五元や十元の寄付でも明細をきちんと掲載しました。これが人文志業の最初の形でした。「その時、あらゆる寄付者の名前が掲載されており、名前を掲載したくない人には『隠名氏(匿名氏)』と書きました。ある時、何人かの『隠名氏(匿名氏)』がいましたが、どの慈済委員が寄付を集めたのかは、全て明確に記録しました」。
「仏教では『信は道の源、功徳の母』と言いますが、信じる心こそあらゆる善行が育つ根源なのです」。従って、全ては「信」から始まるのです。慈済人文志業の報道が全ての人々に信頼してもらえるようになれば、その誠実に善行する模範的な姿が人々に感動を与えるのです。

喧騒の中の静けさ
三月二十八日、新泰区の師兄や師姉たちが、林口静思堂の建設状況とコミュニティの運営、静思書軒(ジンスー・ブックカフェ)の計画について報告しました。上人は、清潔で優雅な環境を保つようにと指示しました。人心を浄化するために地域の道場とジンスー・ブックカフェを設立するのですから、街の喧騒の中にあっても、そこに入ると心が落ち着く空間であってほしいのです。
そこで、ブックカフェでの飲食の提供に関して、上人は、煙や油汚れが周囲の環境に影響しないようにすること、静かな空間で話をしたい人のためにコーヒーやお茶を提供したり、子供たちにも静かで清潔な場所で読書ができるようにしたりすることを期待しました。最も重要なのは、その空間から慈済の精神や思想が伝わり、入ってきた人々に、本を読むだけでなく、世界中にある慈済の拠点地図を見てもらい、各国の慈済の足跡や各道場の発展状況を理解できるようにすることだと語りました。
「慈済がなぜ静思堂を建設するのか、分かっていない人が多いので、私たちは、慈済道場がその地域でどのように人心を浄化しているのかを、皆に知ってもらうことにしました。例えば、林口静思堂の場合、当地区には幾つかのチームがありますから、それぞれのチームに担当地区の活動について分かち合ってもらいましょう。どの家庭にも歴史があります。師兄や師姉がどのように発心し、家庭を和やかにしたのかを分かち合うと、それは教育になります。慈済人の精神理念を示し、特色を出すことが大切です」。
「私たちは静思堂で慈済の情を広め、人間(じんかん)菩薩の貢献を語り継ぐのです。仏陀が教えた菩薩法、慈済人はそれを二千五百年余り後の現代に実践していますが、その行いは自分のためではありません。見返りを求めない奉仕をし、さらに互いに感謝し合えば、感謝と喜びの気持ちに満たされていくのです」。
間取りがどのように人文的な雰囲気を醸し出すかについて、上人はこう述べました。「人々が一目見て喜びを感じられるようにすることです。人はいつも視覚で『形や色』をとらえていますから、物の配置が美しければ、見る人は近づいてもっと理解したいと思うようになるものです。中に入って感じる優雅で静かな雰囲気や、座って静かに語り合う様子も、人を惹きつけるものです。傍に立っているだけで楽しくなって、やがて椅子を持ってきて座って聞くようになります。この空間にいれば、人々は耳や目から仏法を吸収することができるでしょう。良い言葉を発し、そこで聞いた慈済の活動を他の人に伝えるようになるでしょう。これが弘法するということなのです」。
上人は言いました。「林口静思堂は、街の喧騒の中にありますが、近づくと梵唄が聞こえ、静けさの中に妙音が響き、また、世界を舞台にした慈済の奉仕活動について展示があり、慈済人がその内容を語り、慈済の茶道、花道、書道講座を学びたい人々を、人間菩薩を、迎え入れる場所です。ですから、心して取り組んでください」。
(慈済月刊七〇二期より)