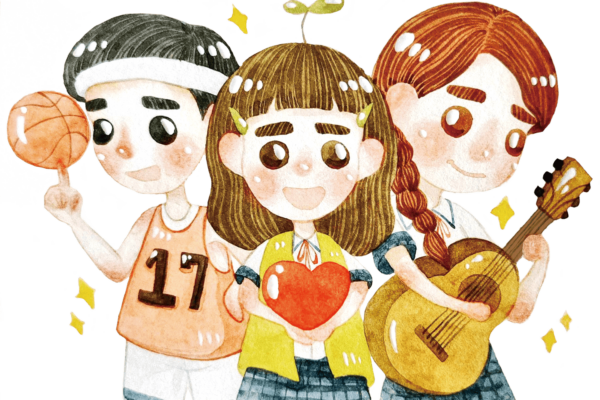石月英(スー・ユェイン)さんは、かつて夫の罵りに耐えられず、結婚証明書を破ったことがある。現在、二人は手をつないで善行し、夫の曽永福(ツン・ヨンフー)さんは彼女の最も心が通じ合う伴侶である。曽さんが、「彼女がいないとダメなんです!」と言えば、石さんは、「彼を見捨てることはしません!彼が元気になって、一緒にリサイクル活動することを望んでいます」と言った。
辛丑の年の春節が近づいた、ある日の午後、暖かい冬の太陽が厦門市湖里区にある蔡塘社地区の路地に差し込み、絶え間ない人通りも少なくなって、大きなガジュマルの樹の枝と葉だけがゆっくりと風に揺れていた。まもなく取り壊される蔡塘社のほとんどの店舗は既に閉店していた。六十七歳の石月英さんと七十歳の曽永福さん夫婦は、カートを引いて行ったり来たりしながら資源ゴミの回収をしていた姿が、その路地に幾ばくかの活気を添えていた。
一日に五〜六軒から資源ごみを回収するが、量が多い所は二往復する必要がある。幅一メートルに満たない路地で、石さんが前でカートを引っ張り、曽さんが後ろから片手でそれを押し、もう一方の手で壁を伝いながら、左足への負担を和らげて、びっこを引いて歩いていく。毎回一緒に来ても、妻に手を貸すことぐらいしかできないが、楽しく、疲れは感じない。
「こんなにたくさん有るの!」。山のように積まれた服とさまざまな段ボール箱、ラッピング袋を見て、石さんは目を細めて笑った。彼女は箱を分解して小さく畳んでから、大きい袋に入れた。片手に再利用可能な紙袋を持ち、もう一方の手で腰よりも高い袋をつかみ、引っぱって階段を降りて行くと、時折カチャカチャという音がした。
一階で待っていた曽さんは、彼女から物資の入った大きな袋を受けとって、カートの側まで引っ張って行った。そして、二人で回収物をカートに載せてからしっかりとくくりつけた。道がでこぼこで、重いカートが大きく揺れるので、曽さんは袋を手で抑えながら移動の補助をした。
路地を出て、比較的平らな村道に出ると、石さんは電話を受け取り、振り返って夫に 「ここで待っていて。私が先ずこのカートを持って帰ってから、あなたを迎えに来るから。そしたらまた上の方へ行って回収に行きましょう」と言った。曽さんはうなずいて「分かった、分かった」と返答し、カートが動き出すと、「ゆっくりでいいよ」と付け加えた。そして聞き分けの良い子のように路地角で静かに待った。石さんは、人生の大半でひどく嫌っていた夫を振り返りながら、今、自分の心には感謝と喜びだけが感じられた

石月英さんと曽永福さんは、結婚して45年間互いに支え合い、街のあちこちで力を合わせて資源ゴミの回収をしている。
リサイクル活動 呼べばすぐ来る勤さん
石さんは主婦だが、三軒の不動産を持っていて、家賃の収入があるため、生活に不自由はない。だが、慈済に入る前はひどく悩んでいた。
石さんは二十二歳で結婚した。彼女の名前に夫の実家の上の嫁と同じ文字があったことから、夫は横暴にも、女性は勤勉に家事をするのが当たり前と考え、彼女を「お勤」と呼んだ。彼女は名前と同じくらい「勤勉に」働いた。例えば、朝は暗いうちから農作業し、家事も勤勉にこなしたが、それでも夫からは認めてもらえず、関心を持たれることもなかった。
夫の曽さんは三食お酒が欠かせない人で、昼も夜も飲んでいた。外で飲み過ぎて道路の電信柱にぶつかって、額に大きなコブを作った上、電信柱に謝ったことがある。家で飲み過ぎた時は、ソファを屋外に運び出し、近所の人が不思議に思って尋ねると、「大掃除だよ!」と答えたので、近所の人々から「酒壺」と呼ばれるようになった。
石さんはいつも怒りをこらえ、泣き暮らしていた。長女が十カ月の時、彼女は夫の罵りに耐えられず、怒りで結婚証明書を破ってしまった。その悔しさと孤独感を訴える人もなく、何千万回も自分に「なぜこんな人と結婚したのだろう?」と問いかけた。
夫を避けるために、石さんは毎日家事を終えると、外出してマージャンをしたり、宝くじを買ったり、ダンスホールで踊ったりした。そのような暮らしをしても、生活の悩みは消えなかっただけでなく、ギャンブルの勝敗によって気分も大きく上下した。また、低血圧のためによく吐き気を催すほどの目眩を起こし、よくベッドから起き上がることさえできなかった。
二〇一一年の初め、同じ村の王明珠(ワン・ミンツゥー)さんが石さんを、慈済厦門支部の改装職人たちの食事を作ろうと誘った。その期間、證厳法師の「地球を守ろう」というお諭しを聞いた。その短い言葉に石さんは突然気づいた。「地球は長く生活する場所であり、ゴミを分別しなければ、間もなくゴミの山の中に住むようになる」と思った。そうやってリサイクル活動を始めてから十年が経った。
二〇一七年から今まで、石さんは六回、骨折したが、リサイクルの仕事は同じように続けた。そのうち一回は家で転んで左足の小指を骨折した。二〇一九年には肩甲骨の痛みでマッサージ治療を受けたら、マッサージ師が力を入れすぎて肋骨を骨折してしまった。その後、回収物を背負ったり、持ち上げたり、運んだりする時、彼女は痛みで眉をひそめたので、慈済ボランティアで従姉妹の石晟治(シー・チェンツー)さんが「紙類を運ぶ時、いつも辛そうだけど、どうしたの?」と尋ねた。石さんは、従姉妹にリサイクル活動を休むよう言われるのを恐れて、本当のことを言わなかった。
去年の暮れ、彼女はリサイクル活動の時に力を入れ過ぎて再び肋骨を骨折してしまった。「お医者さんから、小さい声で話し、何事もあまり力を入れないようにと注意されました」。そう言い終わると、彼女は痛みを忘れたかように、片手でダンボールを持って行ってしまった。
「法師様がこれほど慈悲深く、地球を愛しているのを見ると、感動して涙が出てきます。行動すれば間違いないのです!環境保全の仕事はとても楽しいのです!」彼女は、慈済でリサイクルをしながら法師の説く法を学んでいる。そして、マージャンなどの賭け事の習慣は止め、一心に環境保全に没頭している。以前のマージャン仲間の蔡恋楽(ツァイ・リェンロー)さんは、「以前はマージャンに呼べば直ぐ来てくれたけど、今は来てくれません。リサイクルを頼べば、すぐ来てくれます!」と笑いながら言った。

曽さんは変形性関節炎を患っているため、歩くと脚が痛む。歩道橋を上り下りする時は、石さんの手をしっかりと握る。
「酒壺」から「福おじさん」になるまで
石さんはリサイクル活動や菜食することから、慈済の良さを心から感じた。もし夫に仏法を聞かせて、飲酒の習慣や気性を改めさせることができるならば、体も健康になるだろうと考えた。そこで、慈済の活動から家に帰るたびに、慈済で見聞きしたことを夫に話すようにした。
曽さんは自分の耳を指さして、「当時は話しが左耳から入って右耳から出ていって、まじめに聞いていませんでした」と言った。二〇一二年に、石さんと灌仏会の親孝行感謝活動に参加した時、その整然として壮大な光景を目の当たりにした。そこでは誰もが笑顔を保ち、それまで感じたことのない雰囲気に包まれていた。そのようにして、慈済支部に行って野菜の栽培を手伝い始めた。ある日、土を掘り返していた時、年配のボランティアが彼に果物を持って来てくれたが、にこやかな表情をしていた。その一皿の果物が彼を感動させた。「ここの人はなんて優しいのだろう!」と感じた。それ以来、リサイクルセンターに「福おじさん」が一人増えた。かつての「酒壺」は「慈済リサイクルボランティア」に変身したのである。
曽さんは十九歳の時に左膝を負傷し、歳をとるにつれ、変形性膝関節炎になり、左脚がしびれて持ち上がらなくなり、支えがないと歩けなくなった。外出することは曽さんにとって試練となった。痛みに耐え、一歩一歩歩かなければならないのだ。
「しっかり手を繋ぐ」ことで、石さんは夫と「手を繋ぐ」だけでなく、彼の「脚」にもなっている。例えば、バスに乗る時、石さんがドアの側に立って腕を差し出し、曽さんがその腕を掴みながら乗車できるようにしている。また、バスを降りる時は、彼女が先に下りて、ドアの側で彼を待ち、自分の手で夫の体重を支えて、下車を助けている。
痩せた石さんは、夫に引っ張られてよろめき、腕にはいつも数珠や腕時計の跡がくっきり付き、痺れて持ち上げることができなくなる時もあるが、それでも夫を連れて外出する。夫と手を繋ぎ、石さんは、「彼を見捨てることはしません!私は多分前世で彼をいじめすぎて、借りを作ったのでしょう。今世では出来るだけ我慢して、彼を連れてリサイクル活動に参加します。彼が健康で、一緒にリサイクルの仕事をしたいのです」。

城中村蔡塘社地区の道はでこぼこで、重いカートはひっくり返りそうになる。石さんが先導し、曽さんが資源物を支えて落ちないようにしている。カートの前後に寄り添った夫婦の姿が見えた。
風の日も雨の日も、外出して資源を回収する
曽さんがリサイクルと菜食を始めた時、隣人は曽さんをあざ笑って言った。「子供が親不幸だから、食べ物がないのだろう。だからゴミ拾いしているのだ」。「以前は貧しくて食べ物もなかったけど、今は生活がよくなったのに菜食するなんて、だまされているのよ」。曽さんは惑わされなかった。彼は、リサイクル活動は環境にやさしく、地球をきれいにすることであり、子孫の模範になるのだと分かっているからだ。
歩くのは不自由だが、曽さんは法師の静思語にある「何もしなければ難しいと感じ、歩かなければ、道は遠い」という言葉を忘れることはない。毎日六時半に彼は袋を持って一階まで下り、息子が住んでいる七階建てのアパートに行って、賃貸住人たちの資源ごみを回収しに行く。階段の手すりを掴んで一階ずつ上って行く。
福おじさんの歩みは速くはないが、目は遠くを見ている。夜が明け切らない時、廊下には照明がなくても、彼は階段口から、遠くに資源物があるのを見つける。彼は一歩ずつよろめきながら壁伝いに回収に行く。階段を上るのは容易ではなく、下りる時はさらに難しい。左手で壁を伝い、右手に物資を持ち、階段一段を二歩で下る。右足が先で、続けて左脚を動かす。一段下りるごとに、袋が右のふくらはぎに当たり、何回も当たると痛くなる。
早朝に集めた小さな収穫を見て、福さんは笑顔で言った。「以前は一回で搬送が終らないと二往復していました。今日は少ないですが、集めないとゴミ箱に捨てられてしまい、無駄になってしまいます。だから、風の日も雨の日も回収に行くのです」。
「彼はとても頑張っています。外出してリサイクルをしたいと言うのです。何回転んだか分かりません。以前は歩くことができませんでしたが、今は大分良くなりました」。石さんは嬉しく思うと同時に心が痛む。ある日、ゴミ箱の側で資源を拾っていた時、不注意に転んでしまい、鋼管が右の腰の辺りに刺さってしまった。幸いに服が破れただけで、曽さんは立ち上がって回収を続けた。「私はもう酒壺じゃない、曽永福です!」と彼が言った。
長女の曽恵仁(ツン・フイレン)さんも父親を称賛している。「父は以前、とても気性が激しい人でしたが、今は大分良くなりました。私たちの話にもよく耳を傾けてくれ、以前のようにせっかちではなくなりました」。

曽さんは石さんに感謝している。「彼女がいなければ、今の私はいません。彼女が奉仕すると、私も嬉しいのです。私は歳を取っても、役に立ちたいのです」。
しっかりした足取りで、
永遠に幸福な人生に向かって歩く
街を歩き回ってリサイクル拠点に戻ると、福おじさんは座って分別を始める。彼の前には鉄類、右にプラスチックを入れるカゴが置かれ、ペットボトルを取ると右前方の集積区域に放り投げ、左足の横は様々な紙類である。石さんは時折、回収資源を彼の側に置き、資源に囲まれたことで、彼は手際よくなり、リサイクルのスビートも上がる。
夫婦の間に会話は多くないが、石さんはいつも彼に何をすべきかを知っている。曽さんは、「彼女がいないと生きて行けません!」と言った。石さんは微笑んで長い間、世話をしてきた子供のような老人を見て、「ごみのような私たちの家庭をリサイクルしてくれた法師様に感謝したいのです」と言った。
石さんの携帯が鳴り、隣人が回収物を取りに来てくれるよう頼んできた。石さんが何も言わない前に、曽さんは立ち上がって、出発の準備をした。
人の背の高さほどもある回収資源を積んだカートを引いて、石さんは水を飲む暇もなく、荷物を降ろすと再び回収に出かけ、結局、五往復した。額の汗を拭いながら、「リサイクルは苦労ではありませんよ。やることがない方が心配です!」。環境保全の仕事が以前の耐え難い生活を変えてくれ、喜んで奉仕する幸せを見つけた。
夕日が傾き、夕焼けの光が蜘蛛巣のように張り巡らされた電線を通り抜けて、蔡塘社地区の路地に差し込み、でこぼこの道を照らした。二人のお年寄りはカートを押しながら手を繋ぎ、揺るぎない心でもって、テンポの異なる、しっかりした足取りで進んでいた。静かな村道に笑い声と、カートの「ゴトゴト」という音との合奏がこだました……。
(慈済月刊六五三期より)