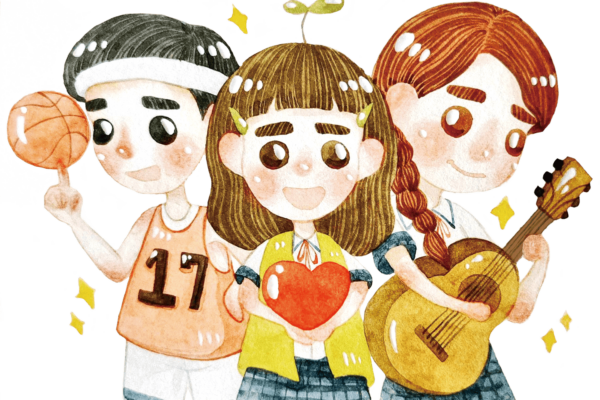慈済ボランティアは昨年12月19日に、ジャミィヤ・ファイジユル・イスラムスクールで、カバンや文房具等の物資を配付した。(攝影・李妙紅)
仏陀の誕生地であるルンビニの住民を思いやらないではいられない。食糧不足、医療の欠乏、就学できない状況下にある貧しく廃れた農村は、苦難が多く、世界中の慈済人が仏恩と師の恩に報いるため、慈悲の心願を真実の道にして、一歩一歩仏の国へ帰ろうと歩んでいる。
シンガポールとマレーシアのボランティアは、慈済ネパール特別チームを結成して、二〇二二年四月二十八日から二〇二三年旧暦の大晦日まで、総勢五十九人が七チームに分かれてリレー式にルンビニを訪れ、交代で駐在した。百日以上、彼らは東南アジア人には耐えられないほどの暑い夏を経験し、東南アジア人には我慢できないほどの寒い冬を、歯を食いしばって過ごした。
ボランティアは十一月四日から六日にかけて、初めて施療を行い、延べ三千二百人に奉仕した。村民が口伝えしたことで、最後の日の午前七時半には既に四十人が入口の前に並んでいたが、その中にはインドとの国境付近から来た人もいた。今回の施療で地元の人に、慈済について基本的なことを知ってもらうことができた。
十二月三日、ボランティアは、ケア世帯全てに十種類の物資を届けて、初めての冬季配付活動を終えた。配付当日の昼に年越しの会食をして、終わると用意した車でそれぞれの家に送迎した。皆の顔に喜びが溢れていた。
現地の就学率は非常に低く、ボランティアが訪れた公立学校の校長によると、約三分の二の子供が小学校教育を終えることができず、中学でも三分の一しか卒業できないという。冬の寒い中、ボランティアは暖かい上着を着て学校へと就学支援の相談に行ったのだが、多くの子供は薄い制服を着て、裸足やぞうりで登校していた。また、カバンも非常に粗末で、米袋で代用している子もいた。ボランティアは訪問中に、一部の子供たちが栄養不良になっているのを目にした。学校側は昼の給食を提供しているが、経費が足りず、お腹いっぱい食べさせるのは難しかったのだ。
子供たちが紙に食べ物を載せ、木の葉をスプーン代わりにして牛乳を飲んでいるのを見て忍びなく思ったボランティアは、食器類を配付することにした。また、子供たちが尊厳を持って学校に通えるように、セーター、靴、それからカバン、辞典と文房具を贈った。
村に着いて住民の家に入ると、二千六百年前の仏陀が経験した時空に戻ったような気がした。ボランティアは心の中で、なぜ仏陀の故郷の人たちは今もこんなに貧しいのだろうか、なぜ不平等なカースト制度が今も存在しているのだろうか、と問うた。


ルンビニ慈済連絡所近くで、2世帯の家族が野宿していた。その中の1人の母親は、生まれたばかりの赤子を抱いて火の傍で暖をとっていた。現地のネパール人でさえ仕事を見つけるのは難しく、彼女たちのようなインドからの違法移民は、物乞いをして生活するしかない。(撮影・呉南凱)
因縁がある以上、把握すべき
二〇二三年一月二十五日、旧正月の四日目、慈済マレーシア支部副執行長の陳済連(チェン・ジーリエン)さんは、再びチームを引き連れてネパールを訪れた。彼は二〇一八年九月十日に台湾へ戻った時のことを振り返った。ルンビニでの透析センターの支援建設について證厳法師に報告すると、法師は、「私が生きている間に、ネパールで慈済の発展を見ることができるでしょうか」と開示した。というのも、仏陀の精神と仏法教義がある故に、今こうして慈済があるからだ。その時、陳さんはこの因縁を把握して、仏陀の故郷に恩返ししなければならないと感じた。
ネパールでコロナ禍が最も厳しかった時期、慈済は十回も医療物資を空運して支援すると共に、食糧配付も行った。ルンビニの住民の七割が援助を受けた。ネパールの国境は二〇二二年四月にやっと開かれ、マレーシアとシンガポールの慈済ボランティアは直ちに合流してネパールに入り、ゼロから出発して、援助の道を切り開いたのである。
マレーシア・ケダ州のボランティアである荘慮昶(ジュアン・リューチャン)医師は、公立病院で要職についていて、年休は三十五日しかないが、彼女はネパールに四十九日も滞在した。クアラルンプールのボランティア、胡桂雲(フー・グイユン)さんは、ルンビニに行くことができると知って、真っ先に、現地に駐在することを志願した。後継の人たちがより良い道を歩めるようにしたかったのだ。ルンビニとの間を頻繁に往復しているマレーシア・ペナン州のボランティア王慈惟(ワン・ツーウェイ)さんは、率直に語った。
「チームは様々な試練に出会いましたが、皆、善念で以て、『ネパールの現地では、私たちは家業も事業もなく、一つの事をするだけです。それは慈済の志業です』と言いました」。
慈済シンガポール支部の副執行長である邱建義(チウ・ジエンイー)さんと李国香(リー・グオシアン)さんの夫婦が、昨年八月十七日にシンガポールからネパールを訪れた時は、エンジニアの呉南凱(ウー・ナンカイ)さんと、リタイアした七十歳の看護師長林金燕(リン・ジンイエン)さんも同行した。ネパールの規定では、外国人は最長百五十日しか滞在できず、邱さんは百四十二日目にネパールを離れてシンガポールに戻った。
「慈済シンガポール支部の劉瑞士(リウ・ルイシ)執行長から電話で、ネパールに行って奉仕しないかと聞かれた時、私はどのくらいですかと聞き返しました。かなり長い期間駐在する必要があるということだったので、それなら先ず、家業と事業も含めて、あらゆる事を手放さなければならないだろう、と思いました」。邱さんは、シンガポールに戻る予定は決めず、ネパール行きの片道航空券を買ったのだった。自分に逃げ道を与えなければ、慈済の道を切り開くことに、より専念できるからだ。
「私は三十年続けた事業を二週間以内に廃業しました。そして子供たちに、お前たちはもう大人だし、私には数十年も残っていないのだから、と告げました。彼らは私の願いを支持してくれました。やはり一番大事なのは、家内の意見を尊重することですから」。
「私は家内に、ネパールに行きたいと何度も言いました。家族全員の生活が私一人にかかっていたため、彼女が心配するのも理解できます。その後、劉執行長は私の悩みを知って、家内と三十分間話し合いました。それで彼女は心配しなくなりました。さらに、驚くべきことですが、家内は私と一緒に行きたいと言い出したのです。結婚を機に仕事を辞め、家事と慈済のボランティアだけをして穏やかに暮らしていた彼女が、ルンビニに駐在することは、容易なことではないはずです」。
李さんが邱さんの傍にいるので、邱さんは後顧の憂いがなくなっただけでなく、夫婦でチームの後ろ盾にもなっている。夫婦は毎朝、皆の朝食を用意し、夜も連絡所や宿舎、食堂の整理整頓をしてくれており、「本当に感謝している」と陳さんが言った。
現地の生活形態は原始的で貧しく、ボランティアたちは毎日、ケアプロジェクトで忙しい。深夜に灯りを消して眠りに落ちると、蟻が体を這っても蚊に刺されても分からないほどだ。李さんも慈済ボランティアだから、不満は一言もない。
「私は何も分からず、何もできませんが、この縁を大切にして、主人の後ろ盾になっています」。
「因縁」と言う言葉は、邱さんにとって感慨深いものがある。
「この任務は私の心を大きく動かしました。この先の道のりがどのようなものかは、誰にも分かりません。しかし、仏恩に報いるのは『因』であり、『縁』は自分で把握しなければならないと信じています」。

●幹線道路脇にある、ルンビニ・ケウタリヤ村のシュリー・ゴータマ・ブッダ中学校は、幼児から中学生に7年間の教育を提供している。全校319人の学生のうち、1割の34人が中途退学するそうだ。ボランティアが1軒ずつ家庭訪問した結果、最終的に5人の保護者が子供を復学させることに同意した。それだけでなく、ボランティアは学校に戻って生徒が復学した後の状況に関心を寄せ、再び家庭訪問して保護者の支持に感謝した。
慈済ボランティアは、シュリー・ゴータマ・ブッダ中学校に復学した生徒の家を訪問して関心を寄せると共に、父親の病状を気遣った。(撮影・李国香)

慈済ボランティアが田舎へ訪問ケアに行った時、ある子供が頭に白癬ができているのを見て、悪化防止の薬を薬局で買い、シンガポールからの医療スタッフ・林金燕さんが子供の治療をした。(撮影・李国香)
昨年11月上旬、ルンビニの仏教施療センターで、慈済による施療が行われた時、瀕死状態のお年寄りがオート三輪車で運ばれてきた。(撮影・攸尼斯)


昨年の初冬、ボランティアはシッダールタ小学校で、カバンと文房具、防寒服を配付し、来場者が子供たちと交流した。(撮影・李麗心)
愛を以て語り始め、長い情に繋げる
当地に駐在する時、最も難しいのは言葉の問題だ、と呉南凱さんと邱建義さんは言う。ボランティアは中国語と英語を話すが、現地の方言が多いため、たとえ首都カトマンズから来たボランティアでも、ネパール語は話せても、方言は分からないため、ルンビニ現地のボランティアを募ることがとても重要になってくる。
そこで、ボランティアチームは積極的にコミュニティーや学校と連絡を取り合い、コミュニティーの実情に深く関わると共に、慈済が一九九三年という早い時期に、ネパールで水害が発生し、社会が不安定だった時に、大愛村を建てたことを住民に知ってもらった。そして、二〇一五年に世界を震撼させたマグニチュード七・八の大地震で、ボランティアは再び災害支援チームを結成し、多数回被災地に駆けつけた。二〇一九年、慈済はルンビニ国際仏教協会の血液透析センターと施療センターの新ビルを支援建設した。
二〇二二年八月十八日、ルンビニに慈済連絡所ができると、一歩踏み込んで、菩薩(ボランティア)を大々的に募った。ボランティアは人に会う度に、慈済のことを話した結果、年末までに延べ四百六人の現地ボランティアが集まった。十二月二十四日には初回の「慈済新参入ボランティア研修会」が開かれ、教師、医療スタッフ、学生、企業家など百十二人が参加した。
二〇二二年十二月十六日から今年一月二十四日まで、三回学校での配付活動が行われ、二十八校の一万一千百人の貧しい学生を支援した。これは公立学校の八割以上の学生を支援したことに相当する。三回目の配付期間、シンガポールとマレーシアのボランティアたちは正月で帰国していたため、十二校五千人余りへのセーターの配付は、現地ボランティアに託した。
カバンは大中小の三つのサイズを用意し、セーターと靴も子供たちの体に合わせなければならず、ボランティアはクラスに入って丁寧に寸法を測った。また、練習ノート、鉛筆、ボールペン、定規などの文房具も用意し、わざわざインドに行って辞典を購入するなどして、必要な品を備えた。
配付活動総指揮のマレーシアボランティア、郭糧鳴(グオ・リャンミン)さんによると、仕入れチームは店にも協力を要請し、数軒の学用品業者も喜んでボランティアを引き受けた。例えば、文房具納入業者のラメーシさんは本を寄付しただけでなく、何度も学校での配付活動を手伝ってくれた。そして、筆入れ製造業者やカバンメーカーも支持を表明し、材料を提供して子供たちが好む筆入れを作ったりした。地元で善意の人たちが次々に現れ、三十五人の方言が話せる地元ボランティアは、喜んで梱包や配付を手伝った。子供たちのために、皆が志を同じくし、愛が込められた。
お互いに感謝の気持ちを込めて礼を交わし、子供たちは嬉しそうにカバンを持って帰って行った。今まで味わったことのない驚きと喜びは、感謝、尊重、愛の雰囲気の中で皆の心を温めた。配付の数日後、再度学校を訪れた時、マレーシアボランティアの張瑞詩さんは、子供たちがきちんと制服を着ているのを目にした。もう厚さの異なる服や裸足姿はそこにはなく、皆、明るい笑顔を浮かべていた。そしてそれよりも感動したのは、教室の外に丁寧に、整然と真新しい黒の皮靴が並べられていたことである。
シッダールタ小学校のアルタフ校長先生は、以前冬の間、生徒の出席率は六割しかなかったが、暖かい服をもらってからは九割に上昇した、と言った。十二月二十二日、ボランティアはこの学校で冬の親子運動会を催し、四十五世帯が参加した。「親が半日間子供に付き添うことは、今までなかったことです。シッダールタ小学校は以前とは違うのです。生徒は楽しく、教師も保護者も喜んでおり、学校の運営側も満足しています。全て慈済が来てくれたお陰です」と校長先生が言った。
「なぜお釈迦様の生誕地の住民がこんなにも大変な生活をしているのか」という疑問に対して、ボランティアはまだ答えが出ないかもしれないが、帰国する時、皆、再度来て、学校に通っていない子供たちを見つけ、慈済のケア世帯と医療ケースを訪ね、大愛村と老朽化した校舎の建設を支援し、新参入ボランティアが慈善、医療と教育などの志業の任務につけるよう付き添うことを誓った。彼らにとって、これは法師の志を継ぐだけでなく、仏恩に報いることでもあるのだ。(資料提供・呉南凱、李麗心、黄玲玲、李怡君、李素月、葉灑瀛、袁淑珍、曽千瑜、呉秀玲、陳秋吟)
(慈済月刊六七六期より)

2022年12月3日、慈済はルンビニ連絡所で初めて冬季配付と年越しの会食を催し、ケア世帯に物資を贈った。(撮影・攸尼斯)