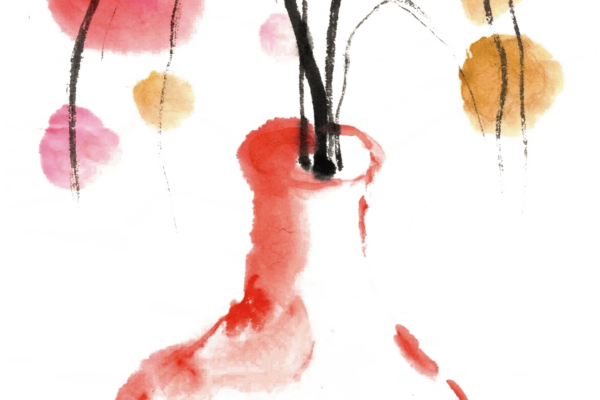富山県富山市にある「デイサービスこのゆびとーまれ」に来る人は、高齢者も子供も身障者もいる。
このように入所者を分けずにケアする方式は、後に政府から「地域共生」の模範とみなされるようになった。
超高齢化社会に直面して、益々多くの国民が、将来は政府に頼るだけでは生活できないので、各自が貢献して助け合う地域社会を作ることで、自分のためにも大衆のためにも帰属感を見つけなければならないと感じている。
秋風が吹く二〇二二年十一月、日本はまだ、コロナ禍が深く影を落としていた。北陸の富山県にあるデイサービスセンターは従業員がコロナに感染したため、十日間の運営停止を余儀なくされた。
「構わん!センターに連れてってくれ!」、「そこに行かなきゃ、寂しいんだよ!」……介護スタッフが全利用者の健康状態をチェックしていた時、家族が諭すのも聞かず、大声でセンターに行くと言い張る人もいれば、自分の気持ちを話すうちに涙を流す一人暮らしの人もいた。
「毎日、当然のことのように通うデイサービスセンターは、本当になくてはならない場所なんだなぁ!」と当時、高熱を出して二日間寝込んでいた、阪井由佳子さんは心の中で思った。彼女は「デイケアハウスにぎやか」の責任者で、利用者全員が無事だと聞いてホッとすると同時に、自分の肩に載った責任の重さを感じた。
この設立されて二十五年になるデイサービスセンターには、どんな魔法があるのだろう?利用者は一日も欠かさず訪れたがっているのである。豪華で配慮の行き届いたスペースと設備?それとも多種多様なクラス?または全方位的な完璧なサービス?これら全て、「デイケアハウスにぎやか」にはない。ここにあるのは、大家族のような「にぎやかさ」だけである。
彼らの一日はこうやって始まる。「おはよう!」「帰ってきたの?」朝早くから続々と家族たちに送られて来て、皆が挨拶を交わす。或る職員らしき中年男性が機転を利かせてコーヒーを持って来た。各自、自分たちで体温を計って受付でサインすると、座り慣れた場所に座って世間話をしたり、新聞を読んだり、静かに窓の外を照らす日光を見つめたりしながら、自分のしたいことをしていて、皆で集まって講座を受けたり、活動に参加したりする必要はない。
「みんな、家に居るように気ままです。家では予定表なんて要らないでしょ?」阪井さんは、ここは一般的なデイサービスセンターのように日課表通りに体操をしたりするのとは違う、と説明しながら、絶えず周囲に気を配り、或るお年寄りのために針に糸を通してあげたと思ったら、或る脳性麻痺の中年女性がヨロヨロしながら立ち上がったので、駆け寄って手を貸していた。
「混合ケア」がこのセンターの最大の特色である。一般のところは利用者を分類している。高齢者は高齢者のデイケア、身障者は身障者、特殊児童は特殊児童というように。しかし、「デイケアハウスにぎやか」の利用者十人には、認知症の高齢者や中高年の身障者もいれば、学校が終わるとやって来る小学生など、年齢も障害のある無しも区別されることはない。「ごった混ぜ」がごく日常的なのである。
正午近く、「菅母さん、人参の皮むきを手伝ってくれませんか?」と厨房で大忙しの職員が訊いた。九十三歳の菅母さんは直ぐゆっくりした足取りで食事の準備に参加した。普通のセンターなら、ケアするのは職員であり、利用者はサービスを受けるだけである。しかしここは、能力があって、その気さえあれば、利用者も貢献することができ、改めて「必要とされている」という自分の価値を感じることができるのだ。
また、阪井さんはこう付け加えた。例えば朝、皆にコーヒーを入れている村川さんは、当初は体に障害があって、「ケアされるために」ここに来ていたのである。しかし、何か手伝うことが好きな性格で、職員たちも彼の「ケア(お手伝い)」に感謝している。
「にぎやか」に来る楽しみは何か、と利用者に訊いたところ、「ここのお風呂が気持ちいいのです」とか「昼食にビールが飲めることです」と言う人がいたが、「皆さんと一緒にいるのがとても楽しいんです」と言う人が何人もいた。それはむしろ「体の養生」よりも「心の養生」に近いと言える。

「デイケアハウスにぎやか」に通って10年以上になる、93歳の菅母さんは、食後に針と糸で縫いものを始めた。彼女が使っていた晒しが男物のパンツだと知った時、皆しばらく大笑いした。
あらゆる人を混合ケアする
こういうコミュニティーの中にあって、少人数(十から二十人)で、家庭の雰囲気があり、高齢者も身障者も子供も同じ空間で過ごし、互いに助け合う関係が出来上がるデイサービスを「富山型デイサービス」方式と呼んでいる。目下、富山県には百三十カ所あり、日本全国には二千七百十二カ所ある。
富山型デイサービスを始めたのは、一九九三年に設立された「デイサービスこのゆびとーまれ」である。初めは幾つかのサービスは法律では規定外であったが、後に制度に取り入れられるようになった。二十九年前、三人の介護師が歩き始めた小さな一歩が、国の制度を動かしたのである。
「介護師は、特別に高齢者や身障者または子供を区別することなく、ケアの必要があれば、皆喜んで手を貸します」。七十一歳で少し猫背の惣万佳代子さんは「デイサービスこのゆびとーまれ」の責任者の一人である。センターの創設時はまだ若かったが、今は彼女もシルバー世代である。変わっていないのは「どんな人も受け入れる」という初心である。
ただ、政府の社会保障制度は以前から分類別になっていて、異なったグループには異なった法律を適用し、デイサービスセンターは一つのグループを引き受けるしかなかった。例えば、同じスペースで高齢者や身障者、子供を一緒に受け入れた場合、政府の補助が申請できなかったのである。それでも、彼女ら三人は理念を実現させるために、制度の限界を超えて、「デイサービスこのゆびとーまれ」を立ち上げたのである。
視察に来た人たちからよくこんな質問が出る。「まず高齢者のデイケアサービスから始めて、その次に身障者と子供を受け入れるという順番にしなかったのはなぜですか?」もう一人の責任者である西村和美さんが、「コミュニティーでケアを必要としているのは高齢者だけではありません。最初の利用者は障害を持った子供でした」と説明した。
「最初は政府の認可が下りませんでしたが、それでも私たちは方向が間違っているとは思わず、こういう形式のケアはあって当然だと信じていました」と惣万さんが言った。それは介護師の使命感がそうさせたのでなく、彼女たちは、子供の頃に地域の人がお年寄りや特殊な人たちと交流していた光景を取り戻したかっただけだったのだ。
「もし、ここを続けることができなかったら、富山の恥ですからね」。民間からの支持の声が次第に高まると共に、混合ケアの利用者に対する効果が加わり、富山県政府は法令の改正を始めた。「デイサービスこのゆびとーまれ」に補助金が出るようになったことが、富山型デイサービス方式を生み出す後押しとなった。二○一八年、政府は正式に、富山型デイサービスをモデルとして「共生型サービス」を推進した。それによって、福祉施設が同時に高齢者と身障者の社会福祉保険を適用し、柔軟に多種多様なケアのニーズに応えることができるようになった。
「デイサービスこのゆびとーまれ」は設立当初、どんな補助も受けられなかった時、利用料は一日二千五百円で、半日で千五百円だった。後に制度に組み入れられ、二○○○年に全国でデイサービスが保険の適用を認められるようになった。高齢者の利用料は「要介護」の等級に沿って、利用者の自己負担が一割から三割までとなり、ケア施設が地方自治体に残りの七割から九割を申請できるため、双方とも負担をかなり軽減できるようになった。
だが地方によって内容は異なり、費用も違う。富山県の或る「要介護二」(立ち上がりや歩行が自力では困難、排泄や入浴ケアなど部分的に介護が必要)という高齢者を例にとると、一日の利用料は七〜八時間で合計九千三百四十八円にもなるが、個人の自己負担は九百三十五円で済む。

「デイサービスこのゆびとーまれ」では、高齢者は世話をされるだけでなく、子供たちとの交流によって、生きている意義を感じ取ることができる。
お年寄りは介護されるだけでなく、必要とされている
「デイサービスこのゆびとーまれ」の午後は、かしましく走ったり飛び跳ねたりする光景と、休息している光景が入り混じっていた。ダウン症の男の子が急に、認知症のお婆さんに駆け寄って甘えると、お婆さんは彼の頭を撫でながら、言葉を掛けた。また、身障者の青年と職員があちこち駆け回って他の人の手伝いをしたり、センターの事務整理をしたりしていたが、皆、顔が輝いていた。
「高齢者福祉に関する研究をしている学者が最も心配しているのは、体が弱っている高齢者と精力旺盛な子供が同じ空間にいれば、事故が起き易いということですが、『起きない』と私は断言できます」。惣万さんによれば、二十九年前に創設して以来、一度だけ認知症の高齢者が不注意で転んで骨折したことがある。この数字は一般のデイサービスセンターと比べても非常に低い。「混在しているがために、職員は一層警戒心を高めているのかもしれません」。
介護士の惣万佳代子さん(右)と西村和美さん(左)が29年前に「デイサービスこのゆびとーまれ」を立ち上げた。

高齢者にとっては、ケアされる以外に、子供たちと触れ合い、彼らの成長を目にすることで「必要とされる」ことを感じ、「生きていく」意義を見出しているのである。身障者の青年は、自分に合った労働で、そこに帰属感を感じている。そして、子供は大人の指導の下に、高齢者や身障者との付き合い方を学んでいる。
宮崎弘美さんも十一年前、先輩介護士である惣万佳代子さんの感化を受けて、富山型デイサービス「大空と大地のぽぴー村」を立ち上げた。それ以前は大きいデイサービスセンターで働いていたが、その一般的な施設では、一年に一、二回幼稚園児が来て、高齢者のために演技するぐらいで、それは一時的な活動に過ぎず、真の交流とは言えなかった。大人でも、小家庭で育った子供たちに、どうやってお年寄りと接し、お年寄りを避けないようにさせるかを教える術を持っていないのだ。
宮崎さんは毎日、十数人の高齢者と特殊児童の世話をしている。「それは大変ですよ。でも楽しいんです」。六十六歳の彼女は笑顔でこう言った、「子供たちにはいつも、『私がここに座るようになった時は、美味しいものを持って会いに来てね!』と言います」。
もちろん、富山型デイサービスに疑問を持つ人もいる。「高齢者や身障者、子供は皆それぞれ異なったケアを必要としているのに、職員はそれに対応する能力を全て持っているのですか?」。
「大人と子供のニーズは七割方似通っています。コミュニティーのクリニックが大人も子供も診るようなものです」。以前、病院で二十数年間看護師を務めた惣万佳代子さんは、「ここは『生活の場』です。基礎的なケアテクニック以外に、もっと大事なのはさまざまな人と上手に接することです」と言った。
「デイケアハウスにぎやか」の責任者である阪井由佳子さんによれば、もし、職員が何もかもしてあげたら、逆に利用者が本来持っている機能を奪うことになるため、本人がその能力を発揮した上で他の人が適時に手伝うようにすべきだという。どうやってケアするかは、人それぞれの状況から学び取り、それを進化させるのである。「プロのテクニックよりも、私は『その人のことを考えてケアする能力』を重視しています」。
例を挙げると、今年二十一歳で、幼児教育専門学校を卒業したばかりの田中來都さんは、介護をゼロから学び始めたのだが、彼の持ち前の朗らかさと思いやりは、デイサービスセンターのあらゆる人が賞賛している。「僕は『仕事』しているという感じはなく、皆さんと一緒に生活している感じですかねー」。田中さんは、「僕はゼロから出発して、今では一日に八人のお年寄りをお風呂に入れるまでになりました。充実感を得ています」と言った。
住宅街にあって、コミュニティーの介護サービスニーズを満たしている富山型デイサービスは、地元との関係は密接だが、直ちに達成できるわけではなく、時間を掛ける必要があった。阪井さんによれば、初め向かいに住んでいる人はとても反対していたそうだ。自分の家のお年寄りが一般の介護施設に行き始めてから、「デイケアハウスにぎやか」の特色に気づき、最後にはお年寄りを彼女たちに預けるようになり、双方の関係が良好になったという。(続く)
(経典雑誌二九三期より)