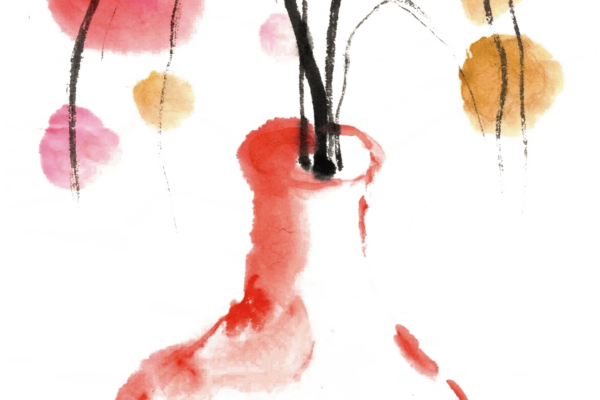(絵・林淑女)
ひとしずくを軽く見ないこと、また、自分も軽視しないことです。 蛍の光は微弱であっても、群れを成せば暗闇を照らすことができます。 お互いに励まし合って、愛で世界を覆いましょう。
毎年のこの頃、溢れる感謝と敬虔の思いになります。去りゆく年の平穏無事に感謝し、さらに敬虔な心で新たな年を迎えたいものです。毎日のように目を開けた瞬間、私の心にあるのは「感謝」の一言です。手足を動かし、息を整えてからベッドを下り、両足を地に着け、体を真っ直ぐにして立ち、足を踏み出して歩きます。その全ての動作がいつもと変わらないという平穏に、私は改めて感謝するのです。なぜなら今日もまた、この世のために行動することができるからです。
命は一呼吸する間にあり、一秒一秒がとても大切なのです。時間と人の命は密接に関わっているのですが、人は時間に対して無関心です。時は金なりと言われますが、人は平等にその光陰に恵まれているのですから、大切にし、感謝して正しいことをするべきです。心にある福田に善の種を蒔いて大切に耕せば、人生における功徳の林となるのです。
もし、ぼんやりとして、何も知らずに一生を過ごせば、善が僅かで、悪がとても大きく占めるかもしれません。自分の人生を振り返ってみてください。人生の中で、最も価値があったのはどんな事だったのか、どれだけ人を利することをしたか、これが私たちの生命の価値です。
人生の価値を振り返ってみて、生命が役に立ったのであれば、自分に対して感謝し、まだできていないのら、直ちに始めれば間に合います。今、何歳かを気にする必要はなく、まだ奉仕する力があるならば、やれば良いのです。そうすれば、生命の価値が増します。
コロナ禍の期間に、ミャンマーの慈済ボランティアと慈青たちが農村部へ配付に行った時のことです。三輪車夫のウオンミペさんは、以前は一家を養うことができましたが、観光業が不景気になってから、運搬工として働くようになりました。一日あたりの収入は現地貨幣の千九百チャット(約百三十円)です。彼も布施したいと思い、力仕事で得た工賃の半分を献金しました。なぜなら彼は自分よりも貧しい人がいることを知っていたからです。
人助けをしたいという善念とこの工賃の半分(約六十五円)には、とても大きな価値がありす。人助けするのはお金持ちだけでしょうか。救われる人は貧困者に限られたことでしょうか。そうとは限りません。善行しようと思っても、受け取ってくれる人がいなければ、身辺に物資がいっぱいあっても、何の用もなさないのです。必要とする人がいれば、私も施しをすることができ、お互いに喜べるのです。良いことをするのはお金持ちの権利ではありません。手足を動かせば、全てこの世を利することができるのです。
人助けをしない人は心豊かになることはありません。喜捨する気持ちで奉仕すれば、貧しくなったと感じることはありません。ある「米貯金」に呼応したミャンマーのお婆さんは、ご飯に水だけという貧しさにあっても、毎日ご飯を炊く時、その手で一握りのお米を分けて、人助けをしており、そこに彼女は喜びを感じています。人々はその姿に心打たれ、共感を覚えています。
一粒の米だけでも、真心をもって奉仕すれば、そこには功徳があるのです。もし私たちの社会の誰もが僅かでも力を尽くせば、世の中は貧困で飢えに苦しむ人が大きく減るでしょう。貧(ひん)と貪(どん)という字は、僅かに違います。考え方を変えて消費を抑え、福を多く造り、日々小銭を貯めても生活には影響しませんが、それが集まれば人間(じんかん)に大きな福をもたらすことができるのです。
ひとしずくの力量を軽んじてはなりません。慈済は五十五年前に「五十銭」から始まり、互いに励まし合い、災難があるとすかさず奉仕し、生活に困っている人には長期ケアをしました。今日までの慈済の足跡を、台湾を起点に世界地図で見てみると、それはまるで天下にまたたく蛍の光のようです。絶えず暗闇を照らし、地球に愛を敷き詰めています。
また、自分を軽んじてはなりません。蛍が一匹や二匹では明るくならなくても、群れをなして同時に飛び立てば、道を照らして人を導くことができます。群れを成す蟻も須彌山を登る志を持つことができるように、愛が結集すれば、至る所で福を造ることができます。「観世音菩薩聞聲救苦(観世音菩薩は苦しみの声を聞けば救いの手を伸ばす)」。今の私たちは、「千処祈求千処現(千の所で救いを求められれば、千の所に現れる)」まではまだできていませんが、発心立願して、行ける所なら必ずたどり着かなければなりません。世間の状況をよく理解して、人々の苦難に関心を寄せ、日々善念を絶やさないことです。善行して、人助けをするのだ、と自分を祝福する人が福を造るのです。福のある人は魂と生命を永遠に輝かせることができます。皆さんも益々精進なさってください。
(慈済月刊六六一期より)